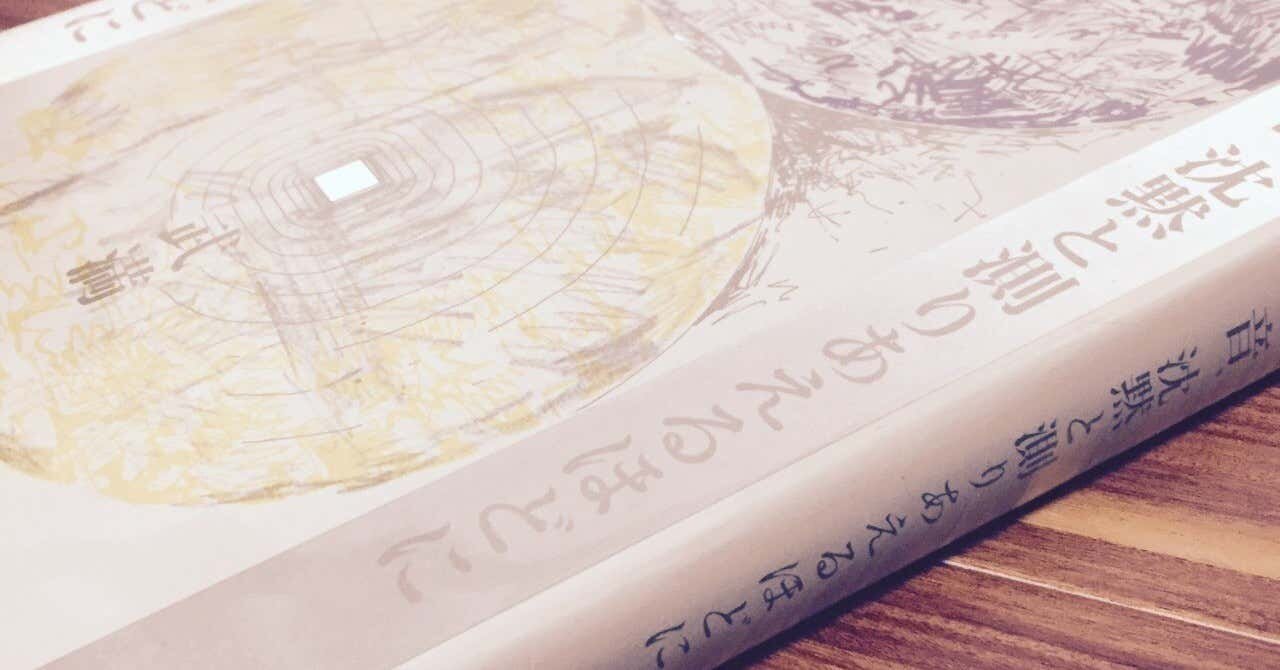「君はちゃんと吃ることができるからいい」
そう言われたのはもう8年前のこと。当時は「はぁ…」と頷くしか返事ができなかったが、今でも折に触れて思い出す。
この言葉を僕に言ったのは、西きょうじさん。軽井沢に住んで、東京に通って予備校講師をしている、ちょっと変わった人だ。実際に授業を受けたことはないけれど、ひょんなことから紹介してもらい、以来ちょくちょくお酒を飲む仲になった。
西さんに言われたことは、「実感の伴わない知識まで、さも自分の考えかのように流暢に喋るよりは、下手くそでゆっくりでも、自分の実感から言葉を絞り出そうとできることの方がよっぽどいい」と、そういうニュアンスだったと思う。
だけど当時の僕は、むしろ「そのようにしか話せない」自分にひどく悩んでいた。流暢に、明瞭に話せる人になりたかった。スムーズに対人コミュニケーションを成立させられる人が羨ましかった。
頭の中と胸の内ではたくさんの思考と気持ちが渦巻くけど、それをうまく言葉に出来ないから吃る。結果、他人には伝わらない。「何が言いたいのか、お前の話はわかりにくい」と周りからよく言われていた。幼少期から青年期にかけて、そうしたコミュニケーション不全を多く経験してきたが、西さんとこの話をしたときは、それがより顕在化していた時期だった。
2011年。東日本大震災が起こった年であり、僕が大学を卒業して、大学院に行かずに石巻に移る選択をした年だ。
海と大地が大きく揺れた。それだけでなく、社会全体も、人の心も揺れていた。
地震と津波によってあっさりと崩され、飲み込まれていく街。圧倒的な自然の猛威は、大地の表面にしがみついて暮らす人間の無力さ、小ささを知らしめた。「安全神話」と地方への搾取構造によって成り立っていた電力供給。原発事故は、僕たちが生きる社会が虚構の上に成り立っていたという現実を突きつけた。
「前提」が揺さぶられ、未来が見えなくなったとき、自分はどうあるべきなのか。
それぞれに思うところはあっただろうが、大学同級生のほとんどは、就職や進学など、すでに決まっていた進路にそのまま進み、新しい生活をスタートした。3月11日から4月1日ー震災が起きてから卒業し、新年度が始まるまでわずか20日間という日数は、立ち止まって考えるにも、他の道を検討・選択するにも短すぎる時間だった。
僕はというと、彼らのように就職・進学するでもなく、休学・留年するでもない、「はざま」の時間を過ごしていた(別稿で書いた通り、当時海外大学院に合格していたが、渡航までに半年ほどの時間があった。結局、留学は延期し、ほどなくして石巻に移り住むことになる)。
行動するにしても、立ち止まるにしても、道を変えるにしても、何かを「選ぶ」ことは、他の可能性を一度断ち切るということだ。100点満点、望みが全て叶う選択などきっとないのだろう。だから、少なくとも選んだ道に後悔しないために、自分にとっての「正解」にするために日々を一生懸命生きるのだ。それはわかる、理屈としてはわかる。わかるんだけど、本当にそれだけなんだろうか…。
何かを選んだら、それを正解にするというシナリオしかないのだろうか。選びながらもためらう、前に進みながらも迷う、そういうあり方は、許されないのだろうか。
震災や原発事故をめぐる社会の言説、3.11以後にもどうあれ続いていく東京の日常。マクロからミクロ、そのどこにもフィットする感覚を持てなかった僕は、もともとの口下手の域を越えて、より一層吃るようになった。
うまく話せないならどうするか。書くしかない。発する言葉にしっくり来ていないから書く。伝えられていない感触が残るから書く。ブログに、Twitterに、とにかくそこにインターネットがあったから書いた。今ではそれが仕事になっているのだから皮肉だが、当時は誰かのためではなく、ただただ自分の生存のためだった。東京に残っていた頃も、石巻に移り住んでからも、日々誰かと関わりはし、しかしそこでは相変わらず口下手で、そんな日常の合間にほそぼそと、そしてぼそぼそと書いた。書くことが自分にとって楽しいわけではなかったし、それが何に繋がるのかもわからない。だから、吃ることが「いいことだ」なんて言ってもらっても、なかなか素直には喜べなかった。
*
西さんが言ってくれた言葉が腑に落ちて納得できたのは、それから1年ほど経った後、『自分の仕事をつくる』『かかわり方のまなび方』などの著者である西村佳哲さんによる3日間のワークショップに参加させてもらったときのことだ。西村さんは、さまざまな生き方、働き方をしている人たちへのインタビューをされてきた方だ。ワークショップは、インタビューの細かな手法や技術を学ぶのではなく、一人ひとりの「きくこと」に対する解像度を上げていこう、という試みだった。
そこで教わったことは3つ。「先回りしない」「相手についていく」「沈黙を恐れない」
その人が黙っていたり、言いあぐねているときは、待たなきゃいけない。言葉以前の「気持ち」が言葉になるまでの時間だから。お腹のなかに手を入れて、自分の気持ちにしっくりくる言葉を、「これかな?」「いいや、これかな?」と探り当てている時間だから。言葉が花開く瞬間を、聞き手が先回りして奪わないこと。そんな風なことを西村さんはおっしゃっていた。
この考え方を教わったとき、気持ちがずいぶんと楽になったのを覚えている。吃ることは、自分が自分らしい言葉を紡ぎ出すために”必要”な時間なんだということ。僕にとって書くことは、自分の中の気持ちを確かめる作業だったのだということ。その場その場ではうまく話せなくても、決して伝えることを諦めていたわけではなかったということ。
自分の中で、「話す」と「聞く」と「書く」が交差した瞬間だった。今、曲がりなりにも僕が仕事としてインタビューや執筆をできているのは、そうした経験があったからこそなのかもしれない。自分も、相手も、それぞれのペースで言葉を探している。上手に、早く話す必要はないのだ。
*
そこから更に数年。アメリカに渡り、日本に帰ってきて、26歳で今の会社に入り、いろんな仕事を経験する。クライアントとのミーティング、研修講師、会社説明会、チームマネジメントetc.人前で話すことも増え、自分でもそれを意識することもないまま、いつの間にかどもりは消えていた。
悩みながら、居場所を転々としながら、20代後半にしてようやく就職した分、凸凹な自分をうまく活かせる場所に、ようやく出会えたなという感覚がある。かかわる一人ひとりの多様性、困難に向き合う上での一人ひとりの痛みや悩みを大事にしてくれる組織だと思う。
とはいえ、スピード感はある。ビジョンを持って、明快に言うべきことを言う。その場その場で意思決定をして物事を前に進める。ためらいよりも決断が、思索よりも行動がどうしても大きな比重を占めやすくなる。
それでも仕事にやりがいはあるし、テーマも自分の関心と重なっている。忙しいけれど自分は適応できるだろう、適応できている。そう思っていたら、昨年にガタが来た。適応障害という診断。「適応できている」と思っていたら、身体は悲鳴をあげている。動機や息切れ、憂うつ感。やるべきこと、できること、やりたいことのバランス不全。やりたいことと外れているわけではないけれど、そのスピードや表現型は合っているのか。
そしてこのタイミングで、また「吃り」が出るようになった。上司や妻との会話で、うまく話せない。どもってしまう。違和感に気づいていながら考えないようにしてきたツケが利息付きでまとめて返ってきた。そんな夏だった。
身体を休める、薬を飲む、業務調整をする、そういうまっとうなケアの積み重ねで、適応障害の心身症状は次第に収まっていった。心や身体にのしかかっていたストレッサーを一つ一つ取り除いたり緩和したりして、回復していくための余白をつくる。そうすれば次第にエネルギーが戻ってくる。けれど、同じタイミングで再び現れた吃りについては、どうもそれらの症状とは性質が違うような気がした。休めば治るというものではなく、僕が他者と話し、関わることの根底に関わっているような感覚が拭えないでいた。
この吃りという現象をどう捉えて、自分はどう付き合っていくのか。そのヒントを得たのは、ちょうどこの時期に知り合った、『どもる体』著者の伊藤亜紗さんとの対談だ。意気投合したのは、”立て板に水”のように上手に話せているときのほうが違和感がある、ということだ。
“「私、大学の講義も3年で内容を全部変えているんですよ。”立て板に水”みたいに話せるようになってきちゃうと、学生に対して申し訳ない気持ちになるし、苦しい。新しいものにしてたどたどしくしゃべらないと伝わってない気がするんです。」
「仕事に慣れてくるとしゃべりが上手になってきますよね。同じことを繰り返し言っているようで…。単純に労力対効果でいったら効率良くなっているからいいことなはずなのに、逆に『このままでいいんだろうか』って思っちゃいます(笑)。」
「自分の輪郭を更新したくなるような感じですね。形成されてきたパターンや枠…ある種、自分の枷にもなっているものがずれたときが楽しいし、生きてる感がある。」
https://h-navi.jp/column/article/35027019 ”
生きてる感。
そうか、僕はどもっている自分が、たぶんちょっと、好きなのだな。生きてる感じがするから。
「君はちゃんと吃ることができるからいい」という西さんの言葉を思い出す。「言いあぐねているときは、”気持ち”が言葉になるまでの時間だから、待たなきゃいけない」という。西村さんのワークショップを思い出す。
しっくり来る言葉がうまく見つからず、吃ったり、たどたどしく話したりしている時間は、身体的には決して楽ではない。手近な仮置きの言葉に置き換えたほうが楽な場面もある。だけどそこでちょっとだけ踏ん張って、吃る体に自分を委ねてみる。もぞもぞと脱皮をするような感覚で言葉を探す。吃りながら訥々と言葉を発している時間は、自分が誠実でいられている感覚がする。
適応障害を発症したときに吃りも再発したのは、単なるストレス反応というより、「納得しきっていないことを話すことはできないぞ」という、身体からのメッセージだったのかもしれない。
吃りが多く出るときは、立ち止まって自分のあり方を見つめ直すチャンスである。ちょっと面倒で生きづらいかもしれないけれど、思考停止せず、誠実に生きてくためのシグナルとして、吃りはかけがえのない隣人なのだ。
*
それから1年。これを書いている今では体調もずいぶん回復し、吃りも日常的にはあまり出ない。
だけど時折、「隠れ吃音」と言っていいぐらいのささやかな吃りが表出することがある。いや、正確にはそういうときはむしろ積極的に吃りにいっているかもしれない。安心して吃れる相手と、そうでない人、あるいは場所・話題がある気がする。
流暢に話したほうが良い場面もある。それが悪いわけではないけれど、そればっかりだと息苦しくなる。吃りは「そろそろ息をしたいぞー」という体からのリクエストなのかもしれない。どもっているときのほうが身体的には息苦しいはずなのに、それが「息をする」ってことなのは、変な感じがするけれど。
鎧を着るときと脱ぐとき、鎧を脱いだ上で、さらにもぞもぞとぎこちなく脱皮するプロセスすらも見せられるとき。お互いにとって大事なテーマを、すぐに答えが出なくてもいいから、ゆっくりじっくり探りたいとき。そういうときは、吃るぐらいがきっとちょうど良い。
話すことは、共鳴することなのかもしれないな。
身の回りに何人かいる「隠れ吃音仲間」のかすかなシグナルは、周りの人はほとんど気づかない、僕たちだけのちょっとした秘密だ。
““どもりはあともどりではない。前進だ。”
武満徹『音、沈黙と測りあえるほどに』, 1971年, 新潮社”