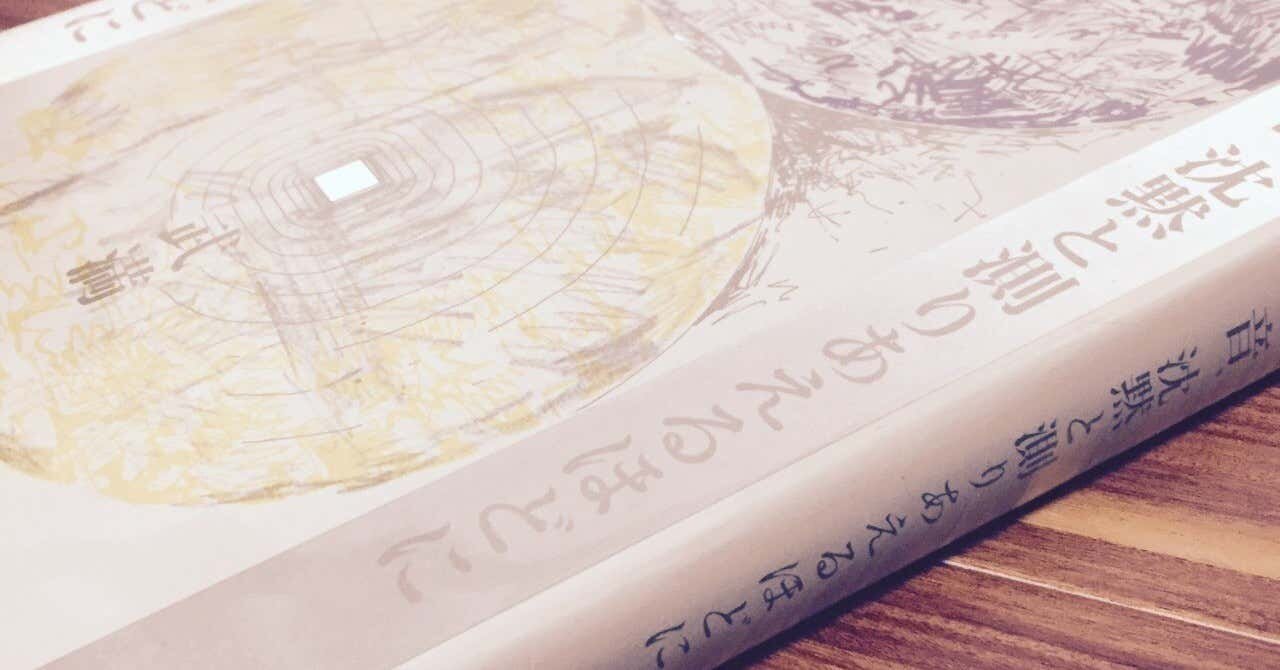「冬季うつってあるじゃん、それの夏版みたいな状態だったんだな、俺は。夏季うつだ、夏季うつ」
と、リビングに寝転がりながらぼやいてみたら、
「それはね、ただのうつだよ」
とツマに返された。正しい。ツマの言うことはだいたいいつも正しい。
自分の痛みに名前をつける。浦河べてるの家の当事者研究に教わったこと
咳が出ない。曇天の下、ただひたすらに続く国道235号線を走る道中でふと気づいた。オフィスから物理的に離れるだけでこんなにわかりやすく収まるのかよと笑ってしまう。そしてようやく、ああ自分はやはり相当に無理をしていたのだなという事実を受け止める。
Read moreそれぞれに傷んできた。しかしまぁ、生きてる、大丈夫
だいたい月に1度か2度、しばらく会ったり連絡取ったりしていなかったなぁという友人から、ふと連絡をもらう。風が吹いたんだろう。
Read moreわたしと発達障害 - 「名付け」のない診断域外をさまよいながら
約1年前から、コンサータ(薬名:メチルフェニデート)を処方されて毎朝飲んでいる。発達障害の一つとされる、ADHD(注意欠如・多動性障害)の症状に対して処方される薬で、脳内の神経伝達物質の働きを良くして、集中しやすくするというもの。
日々、ただ生きているだけで色んなものに注意を持っていかれて、脳みそが常に忙しい。幸か不幸か、瞬発力と処理速度はあるので、来たものをどんどん打ち返していく形で、色んなプロジェクトを同時並行で進めることは出来るのだけど、それぞれで発生する重たい案件(主に原稿とか原稿とか原稿とか)は、いつも〆切ギリギリの過集中で乗り切って、終わったらドッと疲れる、みたいなことになる。いや、〆切ギリギリというのは半分ウソで、周囲のみなさんの本当に本当に寛大な便宜によって、それぞれに〆切を延ばしてもらったり待ってもらったりしながらどうにかこうにか、懺悔と謝罪を重ねて、生きている。
薬が効いてちょっとでも楽になるならそりゃあありがたい、ということで、適応障害がきっかけで診てもらっている主治医に相談して、途中からコンサータも処方してもらった。最初は18mgで、なかなか効果の実感がないので途中から36mgに増やした。飲むと、気持ちシャキンとするかな、という感じ。目立った副作用は今のところ出ていないので服薬を続けているけれど、とはいえ色んなものに追われる毎日なのは変わらない。難儀だ。
通院についても服薬についても、自身の特性の凸凹についても、特段隠してはいない。かといって自分からアピールすることもない。日常のコミュニケーションの中で話題になれば話しはする。自分にとってはその程度の要素でしかない。ただ、こんな風に聞かれたときは、言葉の座りの悪さに、もにょもにょしてしまう。
「お薬が出てるってことは、悠平さんも発達障害なんですか?」
「うーん、まぁ、そうねぇ、そういうことになるのかもねぇ」
なぜもにょもにょするのか。それはひとえに、「発達障害」という概念が示すもの、その言葉の用法、「診断」=名付けに込める期待、当事者性・当事者意識といったものが、あまりにも多様だからだ。そして、実際に自分の困り感が、「発達”障害”」とか「ADHD(注意欠如多動性”障害”」とか「ASD(自閉症スペクトラム”障害”)」といった、”障害”と表現することが妥当なのかというと、けっこう微妙なレベル感だからだ。なので、「われ発達障害当事者ぞ」と声高に言うのもなんかこうしっくりこないなぁというか、ちょっと遠慮しちゃうなぁ、という感じなのである。
*
そもそも「発達障害」とは何か…という話を厳密に突き詰めていくと手に負えなくなるので、ひとまずの現時点で概ね社会的な合意の取りやすいラインでの記述に留めさせてほしい。
発達障害は、先天的な脳機能の発達のアンバランスさ・凸凹≒「特性」と、周囲の「環境」とのミスマッチによって、日常生活や社会生活に支障や困難が生まれる障害であると言われている。
日本では「発達障害」というカテゴリーは、その中に大きく「ADHD(注意欠如・多動性障害」、「ASD(自閉症スペクトラム障害)」、「LD(学習障害)」の3つのグループを含んだものという想定で用いられることが多い。ただこれは、海外ではあまり見られない日本特有の整理・用法であり、更には行政上の定義・分類と、医師が診断する際の定義・分類も完全には重ならず、なかなか扱いが難しいことも留意しておきたい。
ともあれひとまずは、先天的な凸凹と環境の相互作用によって生きづらさや障害を感じる人たちがいて、その人たちの特徴や困難さを捉え、名付け、医療や行政で支援するために、あるいは当事者・保護者たちが仲間とつながるために、「発達障害」というカテゴリーが、現在の日本社会で広く共有され、使用されているということは事実だと言っていいだろう(話すと長くなるので詳しく知りたい人はこちらの記事でも入り口にしていただいて各自どうぞ)
自分が、あるいは家族や身近な人が「発達障害かも?」と思ったときにはどうするか。書籍やインターネット上のコンテンツを参考に理解を深めたり、必要そうな対策をとってみて、それで楽になるということも勿論ある。しかし、困り感が強い場合は、自己診断で留めず、医療機関にかかって検査や診断を受けることが推奨される。医師をはじめとする専門家の目を通すことで、自分自身を適切に理解する助けになったり、他の病気や障害の可能性を見極めることができたりするからだ(必ずしも医師の目が100%ということではない)。
じゃあ医師は何を基準に私たちが発達障害かどうかを診るかというと、さまざまな研究をもとに作成される「診断基準」というものがあって、それを拠り所にして診る。発達障害に関しては、『DSM(精神障害の診断・統計マニュアル)』または『ICD(国際疾病分類)』というものが使われていて、それぞれ版を重ねるごとに診断カテゴリや診断基準も変わっていく。
たとえばADHD(注意欠如・多動性障害)の、『DSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル第5版)』における診断基準は概ね以下の通りだ。
①不注意および/または多動性―衝動性の症状によって、生活に支障が出たり、発達が妨げられたりしている
②12歳までに、不注意または、多動性―衝動性の症状が見られた
③家庭や学校、職場などの2つ以上の環境で、不注意または、多動性―衝動性の症状が見られる
④症状が社会的、学業的、もしくは職業的機能を損ねている明らかな証拠がある
⑤統合失調症や他の精神障害の経過で生じたのではなく、それらで説明することもできない
https://h-navi.jp/column/article/126 より。
さらに詳しい記述はDSM-5そのものをあたってほしい
ここでポイントなのは、代表的な症状に当てはまることと、社会生活に支障をきたすほどの不適応・困難さがあること、その両方が必要だということ。
つまり、ADHDなりASDなり、その特徴として挙げられる典型的な症状やエピソードが見られるだけでは診断基準に満たず、それが「障害」といえるほどの困難さがあってはじめて、診断がくだされることになるのだ。
そもそもの特性の凸凹は誰しもあるのだが、その中でも凸凹の度合いが大きい人たちというのが、先天的に一定割合生まれてくる。僕もその一人だろう。ただ、それが即、障害ー困難や生きづらさに繋がるかというと、そうとは限らない。環境の影響もかなり大きいのだ。
同じような凸凹の強さ・傾向であっても、環境によってはそれが目立たなかったり、逆に強みになることもあったりして、障害を感じないケースは多くある。逆に、凸凹の度合いはそれほどではないとしても、環境とのミスマッチが大きければ不適応を起こすことも十分にある。また、先天的な凸凹が強かったとしても、後天的なスキル獲得や道具の活用によって、生きづらさを軽減することはできる。それゆえ、同じような特性がある人でも、それが発見され、診断や支援を受けられたかどうかや、どんな環境で過ごしたかによって、個々人の予後は大きく異なってくるのだ。
また、バイオマーカー(生理学的指標)がないため、上記の同じ診断基準を参照していても、医師ごとに判断の仕方はどうしても異なってくる。属人性を排除しにくいのも発達障害診断の特徴だ。
これらが、自分が「発達障害なの?」と問われたときに、迷いなくYESと答えることを難しくしている要因だろう。特性の凸凹や、それによる困り感は間違いなくあるんだけど、どうにかこうにか、自分が生きやすい環境や働き方を見出して、社会適応出来ていると言えば出来ている。「障害」の診断基準にハマるかというと、微妙なラインだ。自分の調子が悪いときに受診するか、比較的広めに判断する医師にかかったら、診断書が出ることもある、というぐらいの立ち位置だと思う。
*
実際に、「発達障害の診断を取ろう」という目的を持って受診したことが、これまで2回ある。
1度目は、今から4年前のことだ。
子ども〜成人まで、発達障害特性のある色んな人たちと関わる仕事をする会社に入って数年。仕事を通して発達障害のことを知り、学び、理解を深めていくたびに、どんどん「これ、俺やん」という感覚が強まっていく。27,8年生きてきて、色んな失敗、つまづき、しくじりを重ねながらも、どうにかこうにか働いて暮らしているけど、どうにも世界とうまくフィットしていない感覚がある。なんだかずーっと、生きることが「ぎこちない」。自分のこの主観的な経験は、誰しも経験する程度問題なのか、それとも、発達障害というもので説明ができるものなのか。診断が出るかどうかはわからないけれど、少なくともその確認がしたい。自分のことを理解したい。そんな欲求が日増しに強くなった。
仲良くなった同僚の一人が診断を受けたという病院を紹介してもらって、そこに行くことにした。
職場から片道2時間弱。電車に揺られて鎌倉へ。ひょうひょうとしたおじいちゃん先生が院長の、小さなクリニックだった。
院長との診察が1回。訥々と、自分が感じていること、これまでのこと、現在のことを話す。後日、心理士によるWAIS(ウェクスラー式知能検査)を実施。2時間程度、色んな課題をやって帰る。また別の日に、WAISの検査結果と心理士の所見を受け取る。一番高い項目と一番低い項目の差が30ほど開いていた。所見に書かれた状態像、困難例、支援例は、いずれも、まぁそうだよな、という内容だった。終わってからまた院長先生との診察へ。また訥々と、近況を話す。
「どうかな、自分のことが少しわかってきたかな」
「そうですね、まぁだいたい」
そのまま診察は終わった。WAISの検査結果とは別に、この人はADHDですよとかASDですよとか、「診断書」が出るのかとおもったら、特に何も出されなかった。質問して、お願いすればなにか違った展開になったのかもしれないけど、凸凹はわかったし、なにか福祉制度を利用したいわけでもないし、まぁこんなものなのか、と思って通院を終了した。
通院を終えてから1,2ヶ月ぐらいの間、同僚や友人、監修の先生などに、雑談がてら、受診したことを話したりWAISの検査結果を見せたりした時期がある。日頃の僕の様子を知っている人たちなので、「まぁ、そうだろうねぇ笑」とか「言語性たっか!笑」とか「知覚統合が低めなのね。言語理解とこれだけ差があったらしんどいよね」とか、まぁそんな感じでライトに楽しみながらフィードバックをくれた。
「たとえるなら右腕の筋力だけめっちゃ発達してて、そのちからで色々乗り切ってきたんだけど、反動でずっと背中が痛い、みたいな感じだろうなと思って見てたよ」
友人の一人のこの表現がとてもしっくりきて、「ああ、そうそう、そんな感じ!」と、自分のしんどさを説明してもらえて気持ちが楽になったのを覚えている。
そこからしばらくは、「診断がほしい」という気持ちはなくなった。相変わらず色んな場面で困り感は発生するんだけど、色々経験を積んで自分で対処できるようになったり、チームで働くことで補完し合える環境になったり、結婚して日常生活の安心が得られたりと、人生全体が少しずつ進捗するにつれて「自分が発達障害かどうか」ということが重大トピックではなくなっていった、というのが適切だろうか。
傾向があるかないかと言われれば、明らかにあるし、親しい友人間でお互いの凸凹エピソードをネタに笑い合うことはあるけれど、わざわざその一面を強調するほどでもない。まぁまぁ社会適応できるようになった「発達凸凹さん」という認識でそこから数年を過ごした。
「やっぱり、発達障害の診断も取ろうかな」
そう思って再び専門医にかかったのは、今から1年半ほど前。
その少し前に、仕事での無理がたたり、心身の調子を崩して「適応障害」の診断を受けたのがきっかけで、再び「そのこと」を考えるようになった。
うつ病、適応障害、パニック障害etc.などの精神疾患になった成人が、受診・休養をきっかけに、基底にある先天的な発達障害特性に気づき、診断を受けたというパターンはけっこう多い。精神疾患がいわゆる「二次障害」として、自分にシグナルを与えてくれた、というプロセスだ。
身の回りの知人・友人にも、仕事を通して出会い、インタビューをした人にも、そのルートを辿った人は少なくなかった。自分が体調を崩した当時は「あ、これ自分も同じパターンだわ」と、苦笑いしたものである。
企業で働いて、管理職にもなって、色々工夫しながらどうにかこうにか適応できていたはずだったのだけど、やっぱりしんどさはなくならない。「診断」がどうしてもほしいってことじゃないけど、スッキリした方がなんとなく楽な気がする。診断が出たからといって、その結果に振り回されることもないだろうし、自分の中で疑問や不安があるわけではないけれど、答え合わせぐらいのつもりで発達障害の診断ももらっとくか。そんなふうに考えた。
適応障害がきっかけで受診し、今も毎月通っているクリニックの主治医に相談をした。
「先生のお知り合いで、発達障害の専門医がいる精神科、紹介してもらえませんか」
「うん、いいけど、悠平くんぐらい自己理解してて対処も出来ているレベルだったら、診てもらってもあまり変わらないと思うよ?」
「まぁ、そうですよねー、たぶんそうなんですけど、なんというか、色々あったし、もう一度受けてみたいなぁって」
「わかった。じゃあ連絡しとくから、〇〇クリニックの△△先生で予約して行ってみて」
予約をして、都内某所のクリニックへ。
適応障害になってからの通院歴、これまでの経緯、自覚症状や困りごとをバーっとWordに書き出して印刷し、数年前に受けたWAISの結果と一緒に持参。「うおー俺は今回こそ診断取るぞー!適応障害とADHDとASDのトリプルホルダーじゃーい!」みたいなテンションでツマにチャットを送り、電車に乗りこむ。いま振り返れば妙にやる気満々すぎる患者である。めんどくせえなこいつ。
以前、同僚に教えてもらって行った鎌倉のクリニックよりずっと大規模な場所だった。ロビーで少し待ち、名前を呼ばれて部屋に入る。
「今日はどうされました?」
ガタイも良く、眼光鋭い先生だった。先ほどの強気はどこへやら、ちょっと緊張しながら資料一式をお渡しし、自分が書いた文章に指差しながら、しどろもどろに説明した。
「まぁその…こうこうこういう仕事をしていて、以前も傾向あるかなと思ってWAISも受けた結果がこれなんですけど、最近適応障害になって治療中なんですが、やっぱりベースに発達障害もあるんじゃないかと思って、改めて診ていただきたいというか…いやあの、こうやって自分でエピソード書き出すとバイアスかかって診断基準に寄せちゃうってのはわかってるんですけどね、なので先生には割り引いて聞いていただきつつですけど、でもやっぱり…」あーだこーだあーだこーだ。
振り返るとやっぱり、我ながらめんどくさい患者である。書いていて変な汗が出てきた。
その先生は、主治医の申し送り書やWAISの結果も見ながら、僕の話を黙って聞いていたが、しばらくして口を開いた。
「なるほど、はい、はい、おっしゃることはわかりました。じゃあちょっと改めて質問しますね」
先生は診察用紙にやや大きな字で「ADHD」「ASD」と並べて書き、それぞれマルで囲んだ。
「あなたは自分で、ADHDとASDどっちが強いと思ってますか?」
「ADHDですね。どっちもあると思いますけど、強いのはADHDでしょう」
「そうですか…。僕の見立てはね、明らかにこっち(ASD)」
そう言いながら先生は ADHD < ASD と大きく不等号を書き足した。
「表出する困りごとの背景として、大きく衝動性と常同性どっちが効いてるかといったら、あなたの場合は圧倒的に常同性の方」
えー、マジすか。いや、混合型だろうなぁと思ってはいたけど、そっち(ASD)の方が強いとは思ってなかった…(という話を、帰ってきてツマや同僚、友人に話したら「え、そりゃ絶対そうでしょw」「ADHDもあると思うけどさ、ASD性もめっちゃあるw」「むしろASDの方が強いって自覚なかったのかw」と爆笑された。あ、はい)。
「それから、これもやってごらん」
続けて先生は、A3裏表1枚のチェックリストを差し出した。10セクターに分かれた質問が全部で80問ほどある。該当するものに○をつけていき、集計する。それは、パーソナリティ障害のスクリーニングを行うための簡易質問シートだった。
「どう?」
「はい、集計できました。うわぁ…」
ほとんどのセクターでは0個か1個しか○がつかなかったのだが、演技性パーソナリティ障害、自己愛性パーソナリティ障害に該当するセクターの質問だけたくさん○がついた。
「なにか生きていく上での不適応や生きづらさを感じるとき、そこにはストレス、身体特性、精神疾患、発達障害、と色んな要因があるんだけど、一番見落とされがちなのがパーソナリティ。最近はみなさん発達障害かも?って思って来られることが多いんですけどね。理想も高くて、色々周囲に気を遣って、でもギャップが感じてしんどいんでしょう」
演技性…自己愛性…うん、まぁ確かに言われてみれば、そう、そういう傾向は、ある…。パーソナリティ障害、かぁ…それは盲点だった。
自分でつけた○の数と集計結果を眺めながら、頭の中がぐるぐる回転していた。
「ただあなたはね、話していても好印象ですし、ここまで色々工夫して知性で補正されてこられたんでしょう。発達障害にせよパーソナリティ障害にせよ、その傾向はあっても、決して『障害』ってほどの状態ではないと思いますよ」
「はぁ…」
障害ってほどではない。うん、うん、まぁ、そうだろう。発達障害の診断基準は知っているし、今やったばかりのパーソナリティ障害チェックリストも、単なるスクリーニング用の簡易テストだ。「障害」と医学的に診断されるほどの不適応は来たしていないと言われれば、確かにまぁ、その程度なのかもしれない。
もともと「答え合わせ」ぐらいのつもりで来た。診断が出ようと出まいと、自分の傾向と対策は特に変わらない。それはわかっていたはずなんだけど、なんだか足場を踏み外したような感覚がする。ADHDとASDの強弱の見立てが外れていたからなのか、「パーソナリティ障害」カテゴリからの不意打ちを食らったからなのか、理由はよくわからない。
「ここに来るってことは、苦労はされてきたんでしょう。困ってるからここに来たんだと思いますよ。でもね、あなたはすでに自分の知性で十分に補正されてますから、『障害』って思わなくても良いんじゃないですかね」
「そうですかぁ。なるほど…。それでえっと、僕の診断名はどうなるんでしょうか。診断書に書かれる名前というか」
「診断書って、あなた、障害者手帳がほしいとか、休職したいとか、職場でこんな配慮がほしいとか、目的があればそれに応じて書きますけど、何に使います?」
「いや、なにか別に支援を受けたいとかそういうわけじゃないんですけど、発達障害ってグレーゾーンだの確定診断だの巷ではややこしいので、なんというか、自己紹介的に…」
「みなさんね、発達障害の確定診断がほしいって来られるんですけど、あなたもご存知の通りスペクトラムですから、確定診断なんてものはないんですよ。支援が必要なら書きますけど、必要あります?」
「いやー、そうですね、ないっすね…。たしかにスペクトラム、そうですよねぇ。いや、はい、大丈夫です。ええとまぁでも、パーソナリティの傾向とか、新しい発見があって面白かったです。ありがとうございました」
それこそ知性で補正しながら、ポジティブな収穫の確認と、感謝の意を言葉にして部屋を出た。
2回目の「発達障害診断チャレンジ」も、そんな感じで、わかりやすい「名付け」はもらえないまま終了した。
後日、いつものクリニックの通院日に、苦笑いしながら事の顛末を主治医の先生に報告した。
「うん、まぁ事前に言った通りの結果だったね(笑)」
「いやー、自分も仕事柄スペクトラムだっていつも言ってましたしね、そりゃそうだって感じなんですけど。自分のこととなると、名付けがほしいって思うことがあるんですよね。専門医の先生に言ってもらって諦めがついた感じがします。色んな凸凹があるけどどれもグレーゾーン、みたいな曖昧な立ち位置で自分はこれからも生きていくんだろうなって。まさかパーソナリティ傾向もあるとは思ってませんでしたよ(笑)」
「まぁまた自分の新しい一面が見えたのはよかったんじゃない。あと、僕もコンサータ出す資格は持ってるから、不注意・衝動性が自分で気になるなら、試しに少量から出すことできるけど?」
「え、先生も出せるんすか!」
…という感じで現在に至る。
自分の心身の不調や凸凹については、これまで別の記事でも色々と書いてきたが、改めて列挙してみるとこんな感じだ。
適応障害: 診断書が出たのち、療養・回復し、現在は診断域外、レクサプロ(SSRI)服薬継続
ADHD: 傾向あり、診断域外、コンサータ(メチルフェニデート)服薬継続
ASD: 傾向あり、診断域外
パーソナリティ障害: 演技性・自己愛性パーソナリティの傾向あり、診断域外
その他: 隠れ吃音(普段は目立たないが、たまに出る)
薬は飲んでいる。障害者手帳は持っていない。一般枠の雇用で就労していたが、現在は自営業で曖昧に食っている。
「障害」というほどではないにせよ、上記の凸凹もあって心身の波はやや大きく、「疲れやすい」身体と共に生きている。
「医療」のメガネでも「福祉」のメガネでも、どの障害にも当たらない。「診断基準」の少し外側、ふわふわした名前のない場所が僕の立ち位置になるのだろう。
「ここに来るってことは、苦労はされてきたんでしょう。困ってるからここに来たんだと思いますよ」
精神科の先生に言われた言葉をしばしば思い出す。
名付けがあろうとなかろうと、自分の凸凹自体は変わらない。取れる対策も大きくは変わらない。
じゃあどうして、2度も受診をしたのか。
それはやっぱり、「名前がない」ことの生きづらさがあったんだろう。
*
医師による診断が出るかどうか。障害者手帳(精神保健福祉手帳)を取得するどうか。障害者雇用枠での就職をするかどうか。
発達障害の「名付け」に付随する、医療・行政・労働市場におけるそれぞれの選択肢。もちろんこれらは必ずしも全て選ばなくても良い。また、診断と手帳に関しては望んだからといって取れるとは限らない。当然、発達障害の「当事者」一人ひとりがどんな「名前」を社会的に付与されているかはさまざまであるし、名付けに対する思い入れも人それぞれ違う。同じ人間でも、年月を重ねる中で距離感が変わっていく。
「大人になってから診断を受けて、ようやくバラバラのパーツがつながりはじめた。そんな感覚」
「やっぱり診断が、『名前』がほしい。スペクトラムだとかグレーゾーンだとか、そんなこと職場の人にはとても理解してもらえない」
「診断を受けてからしばらくは、なんでも特性に紐付けて自分を説明しようとしてたけど、今はもう、飽きちゃった。自分の一部でしかないなって」
「最初は障害者雇用枠で入ったんですけど、手帳の更新忘れちゃって(笑)そのまま一般枠になりましたが、職場はもうわかってくれてるんで」
「実はこないだ、手帳返納したんですよ。そのまま使ってても良いんだろうけど、なんとなく、自分の区切りとして」
身の回りの知人・友人たちの、「発達障害とわたし」にまつわる、色々なエピソードを聞かせてもらってきた。それぞれがそれぞれに苦労してきて、どうにかこうにか生き延びている。彼らと出会い、部分的に経験を共有し、ときに「あるあるネタ」で笑いながら、ときに愚痴を言いながら、同じ時代を生きていることを有り難く思う。と同時に、あいかわらず「名付け」が定まらない自分のふわふわした立ち位置をめんどくさく思う。
別にめちゃくちゃこだわってるわけでも、困ってるわけでもないんだけど、さ。
医師の診断も出て「当事者として」の語りを出来る友人がうらやましいという気持ちと
「自分はまぁ、診断なくて困ってるほどでもないからなぁ」と、周囲の理解が得られなくて悩んでいるグレーゾーン当事者への妙な遠慮と
(あまり好きな言葉ではないが)「支援者」側に片足突っ込んでいるゆえの、職業倫理的な自己抑制と
医師や行政の名付けがない中で「適当」に自己診断で名乗ることに抵抗する、自分のASD的特性と(これは皮肉)
そういういろんな立場や思考がないまぜになって、ずっと「足場がない」感じでふわふわと生きている。
…ここまで書いてきたが、特にスッキリする結論は出そうにない。ただ、この文章を書き始めるまでの4,5年で、またこの文章を逡巡しながらちょびちょびと書き進める中で、少しずつ、少しずつ、「まぁそんなもんだよな、仕方ないよな」という諦念が分厚くなってきていて、それはきっと悪いことではないのだろう。
そもそもがスペクトラムで、環境によって凸凹は強みとも弱みともなるのだから、結局、当事者も医師も、誰も「名乗る」ことへの許可・お墨付きを与えることなんてできないのが、「発達障害」というものだ。診断名や、典型例では説明できない多面的な自分の姿がたくさんあることに目を向けてからがむしろ本番で、「名付け」はスタート地点でしかない。
名前を見つけて、説明できる要素が増えていくこと。
説明しきれない部分が残るのを許容できるようになること。
原因がどうであれ、対策を取って楽になる場面が増えていくこと。
凸凹をならして平らにしようとするのではなく、凸凹のままでも生きていく方法や環境を見つけていくこと。
そういうことをこの4,5年の間に、いや、「発達障害」という概念に出合う前も含めたこの32年間の人生で、色々と身につけて頑張ってきたのが今の自分だ。どうにかこうにか生き延びてきた。そのことだけは、自分で肯定してやりたいと思う。
アラサーになって、これから段々と老いていく。それもまた、悪いことではない。
体力も落ちるから、無理せず過ごせる、自分に合った居場所だけが自ずと残っていくだろう。
「年取ったら定型発達も発達障害も一緒くたに、みんなポンコツになっていくから、発達凸凹なんか目立たなくなるよ!」と笑いながら励ましてくれた先輩もいた。
ここ数年は特にしんどかったが、振り返ってみればそもそも、「健康」であるという感覚を持てていた記憶がほとんどない。
しかし、歳を重ねるごとに、しんどいながらもしぶとく生き延びていくゾンビ的なレジリエンスは高まっているように思う。
きっとこれからも、名前のつかないマイルドな生きづらさはずっと抱えて生きていくのだろうけれど、これだけ予行演習を重ねたならば、さして恐れることでもないのかもしれない。
診断書は病の「はじまり」にしか出ない。では「終わり」とはいつなのか
僕が「適応障害」と診断されたのはもう2年以上前のことだ。職場に行けば咳が出て、ミーティング前には動悸が走る。「あ、これはダメだ」と気づいて受診した。先生に診断書を出してもらい、職場に報告と相談をし、その時点で出来る限りの業務調整・負荷軽減を試みて、どうにか残りの半年を乗り切った。診断を受けた直後、いわゆる急性期は1,2週間に1回の頻度で通院し、先生に細かく状況共有しながら回復の道筋を立てていたが、程なくして落ち着いてきた、というか、もっともしんどい時期は乗り切ることができたと判断したので、通院頻度を月に1度に落として、そこから現在に至るまで通院・服薬を続けている。
診断を受けた当時のようなわかりやすい症状はもう出ていないし、日々の仕事や生活にも大きな支障はない。異動をしたり、独立したり、この2年で働き方を徐々に変えていき、発症当時のようなストレスがかかる状況にはない。さて、そんな僕はまだ「適応障害」なのだろうか?僕は「病気」なのか、「健康」なのか、どちらなのだろうか?
1つ目の問いは簡単で、答えは「NO」だ。疾患には「診断基準」というものがあり、それに該当すると医師が判断すれば、あなたは○○障害ですね、と診断がくだされる。適応障害の場合は以下のような診断基準になるが、これに照らし合わせると僕はもう該当しないと言って良いだろう。
以下のA〜Eをすべて満たす必要がある。
A. はっきりと確認できるストレス因子に反応して、そのストレス因子の始まりから3ヶ月以内に情緒面または行動面の症状が出現
B. これらの症状や行動は臨床的に意味のあるもので、それは以下のうち1つまたは両方の証拠がある。
(1) そのストレス因子に暴露されたときに予想されるものをはるかに超えた苦痛
(2) 社会的または職業的(学業上の)機能の著しい障害
C. ストレス関連性障害は他の精神疾患の基準を満たしていないこと。すでに精神疾患を患っている場合には、それが悪化した状態ではない。
D. 症状は、死別反応を示すものではない
E. そのストレス因子(またはその結果)がひとたび終結すると、症状がその後さらに6ヶ月以上持続することはない
『精神疾患の診断・統計マニュア ル第 5 版(DSM-5)』より
疾患ごとに診断基準は異なるが、精神疾患においては、抑うつとか気力の減退といった具体的な症状のエピソードだけでなく、それがどの程度持続しているかという「時間」の観点、それが日常生活に著しい支障をきたしているかという、「障害」の観点が診断基準に含まれているのが特徴だ。乱暴に言ってしまえば、「別に仕事や社会生活には支障出てないですよー」という状態であれば、診断基準からは外れることになるのだ。
では、2つ目の問いはどうだろう?「適応障害」ではもうないとして、じゃあ僕は「病気」なのか「健康」なのか。これがなかなか難しい。診断を受けた直後の急性期からはとうに脱した。しかし「病前」に元通りかというと、決してそんなことはない。
まず、疲れやすくなった。無理のない範囲で運動をするようにはしているが、一度調子を崩して、ガクッと落ちた体力は、なかなかすぐに回復しない。
それから、ストレスがかかったときの身体反応が出やすくなったように思う。ちょっとヘビーな出来事に直面すると、すぐ汗や動悸が出てくるようになった。抑うつ状態というほどではないけれど、憂鬱な気分を抑えて、よしやるぞ、となるまでにけっこうな時間がかかる。「気合で乗り切る」という言葉があるが、乗り切るための気力の最大値がそもそも減ってしまったし、かつそれがチャージされるまでの時間がかかるようになったという感覚だ。
「仕事」に使える時間の総量はかなり少なくなった。一番頭がスッキリしていて生産性が高いのは午前中だが、朝型になったというより、夜にはもう仕事ができるエネルギーが残っていないのだ、という方が正しいだろう。晩ごはんを食べたらもう身体が完全に「寝る」モードになって、その後パソコンを開いて作業をしようと思ってもまったく機能しない。早朝の電車に乗ってオフィスに行き、夜遅くまで働いて終電近くで帰る、みたいな働き方はもう二度とできないと思う。そもそも、そんな働き方をする方が異常ではないかと今となっては思うし、本来、これぐらいの労働量で十分なんじゃないかとも感じる。元々そんなに身体が丈夫な方ではなかったし、診断を受けたことがちょうど良いブレーキになってくれたとも言えるだろう。ただ、スタートアップや新規事業などで、昼夜を問わずしゃかりき働いているような年若い後輩たちを見て、彼らと同じ土俵ではとても働けないなぁ、という寂しさに似た感情を抱くことが、時たまある。
そして、今も通院・服薬を続けている。これが診断後に新しく加わった、「日常」のルーチンだ。
僕に処方されているのは、レクサプロ(一般名:エスシタロプラム)という薬で、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)と呼ばれる抗うつ薬の一つだ。夕食後、寝る前に1錠、10mgを飲むことになっている。最初のうちはなかなか習慣化できず、週の半分ぐらいは飲み忘れてしまい、通院のたびに薬を余らせてしまった報告をして「コラッ」と先生に突っ込まれていたが、今となってはすっかり日常の一部となった(たまに夜飲み忘れて翌朝飲んでいるのはナイショだ。あと、やっぱりたまに、たまーにだけど完全に飲み忘れることもあるのもナイショだ)。
途中から「自立支援医療」にも申請をし、受給者証を取得した。通院による継続的な治療が必要な人が申請・利用できる制度で、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されるものだ。精神疾患の治療は長期におよぶことも少なくないため、経済的な不安を軽くすることで、体調の安定や治療への専念をサポートしようという趣旨で作られた公的支援である。今も通院を続けているので、この制度の恩恵に預かっている。
ストレス因からは離れ、不適応状態ではなくなった。通院・服薬は継続し、公的支援も利用しているが、疲れやすかったり、たまに症状が現れたりする以外には、特段困ったことはなく、概ね安定して就労できている。というのが、「適応障害」の診断から2年強が経った僕のステータスだ(途中からADHD症状に対応する薬であるコンサータも処方されたが、その件については別の機会にまた詳しく書く)。
さて、今のこの「状態」をどう表現したら良いだろうか。適応”障害”ではないけれど、自分は「健康」です!と言うには憚られる。かといって何の「病気」かと言われると特定も難しい。治療、回復、寛解、完治…色んな言葉があるけれど、どれもしっくりこない。病気と健康のあいだにある、名付けようもない曖昧な状態を漂っている。そんな感覚だ。
「だいぶ調子が戻ってきた感じがするけど、この薬はいつまで飲むのが良いのだろうか」
「ゆうへいにとっては、やっぱりお薬はどこかで『やめるもの』って存在なんだね」
診断から1年ほど経った頃だろうか。家で薬を飲みながら何気なくつぶやいた一言に対する、ツマの返しが印象に残っている。
そうか、俺は断薬を希望しているのか。
いや、「希望」というほどはっきりした意思ではない。
でもやはり、「飲まなくてよくなる日」が来るといいなぁ、と無意識下では思っているのかもしれない。
つまり、僕の中にはまだ、今この状態が「異常」で、飲まない状態が「正常」というか、本来の自分なのだ、という感覚が残っている、ということなのだろうか。
精神疾患というものの性質上、自分の人生にそれまでなかったものが途中から(後天的に)出てきた感じがするから、「元に戻る」ことを無意識に指向してしまうのだろうか。
ツマにそう言われた時に、こんな風にいくつかの思考がほぼ同時に頭の中に浮かんできた。今も時おり、同じような逡巡をすることがある、
もちろん、薬をやめることが「ゴール」とは限らないことは十分にわかっている。診断を受けた直後、躊躇いもなくそのことを開示できたのも(家族や上司だけでなく部下や同僚、果てはブログに書いて全世界に公開した)、病気に対するネガティブな意識が比較的薄かったからだろう。それはここ数年、さまざまな疾患・障害と共に生きる人たちを訪ね、話を聞き、関係を結んできたことが影響している。
「回復とは、回復し続けること」
「病気を克服しようとするのではなく、隣人として共に生きていく」
「元に戻るというより、別の地点に向かって再発達する」
先輩たちから受け取ってきた色んな言葉が、今も僕を支えてくれているのは確かなのだ。
それでも時折、「薬をやめる」ことを将来のシナリオとして考えるのはなぜなのだろう。
どうしてたかだか寝る前10mgのお薬に、それもすっかり習慣化した存在に、未だ「異物感」「ヨソモノ感」を抱いているのだろうか。
疾患の種類や症状によっては、薬は始めたりやめたりするものでなく、「飲み続ける」ことが生きるのに不可欠だということも少なくない。薬以外にも、体の成長に合わせて義手・義足を変えるとか、視力の変化に応じてメガネやコンタクトレンズの度数を変えるとか(これは僕も経験している)、僕たち人間は、身体の色んな凸凹を、医学や工学によって補いながら生きている。
それに、何かを習慣的に取り入れるという点では、コーヒーやお酒、タバコといった嗜好品もたくさんある。さっき薬のことを「異物」と書いたが、飲むときになんの苦痛も苦労もないし、身体に入ったあとは、それが溶けてどう作用しているかを感じることもできない。その点ではアルコールのほうがよっぽど「異物感」あるだろう。
ただその分、掴みどころがない感じがなんとなく気持ち悪いというか、気持ち悪いっていうより気になるっていうか、どういうことなんだろうな、という感じがずっと残っている。診断名と身体感覚の不一致とでも言えばいいだろうか。
あぁつまり、問題は「薬」そのものではなくて、「薬を飲んでいる自分」に対するぴったりの”名前”がない、ということなのだな。
当初与えられた名前である「適応障害」の基準からは、とっくに脱している。しかし未だに通院と服薬は続けている、この状態には名前がないのである。
病気に対する治療やケアは、もちろん医師や薬だけがするものではない。心理療法は医師以外でも出来るし、食事・睡眠・運動といった日常的な生活習慣を整えるのは自分や家族といった家庭でやることだ。自助グループや当事者研究などで、似た経験を持つ仲間たちと対話することも、症状の理解、ひいては安定に大きく寄与してくれる。そう考えると、医師にしかできないことは実はそんなに多くなくて、要は「診断」と「薬の処方」だけである。しかし、だからこそそれが大きな存在感を持っている、とも言える。
「診断」を下す、目の前の患者の状態に「○○病」「△△障害」といった名前を与えるという行為は、その特徴や要因を特定し、適切な治療や支援に繋げるために行われる(健康ではない、というだけでなく、他の疾患の可能性を排除する、という意味もある)。診断前後の僕自身は連続した存在であるが、「名前」を与えられることによって、病人としてはじめて本格的な治療の入り口に立つという意味では、「生まれ変わる瞬間」でもあるのだ。そして多くの場合、「診断」と薬の「処方」はセットで行われる。
医師にしかできないこと、「診断」と「薬の処方」、この2つが入り口でセットになっていることが、僕の「病人」としての自覚を形成した。しかし診断は「点」であり、服薬生活は「線」である。
医師による名付けー診断書は、病気の「はじまり」にしか出ない。では「おわり」はいつなのか。そうか、これが僕のモヤモヤの正体だったのか。
たかが名付けひとつがなんだ、名前がなくなったことがなんだ、と、ここまで書きながら逡巡してきた自分がバカバカしくも思えてくるが、それほど「名前」というものは力を持っているということを改めて痛感する。「病気を自分のアイデンティティの全てにすると危ういよ」なんてことは、よく言われるアドバイスであるし、僕も同じようなことを直接・間接に他者に向けて言ったことがあるが、当事者からすると、そう簡単なことではないのである。嗚呼、じんせい。
さて、違和感の正体がわかったところでどうするか。自分の意識を縛っているバイアスを一度「自覚」すれば、そこから脱することは比較的たやすい。「診断」と「服薬」は近接しているが別物である。僕が疾患の診断域から外れていることと、服薬を続けていることは矛盾しない。あとは体調を踏まえて、服薬を続けるか止めるかは、医師と相談して決めれば良いだけの話である。
そこで、先月の通院日に少し「変化」を起こしてみた。
「…最近は、仕事もそんな感じでぼちぼちやってますわ」
「まぁ、順調な感じですね」
これまで書いてきたとおり、症状は安定しているので、月に一度の通院は、お薬を出してもらうついでに世間話をする、プチメンテナンス日ぐらいの感覚だ。そのまま終わっても良いのだけど、相談してみることにした。
「おかげさまで安定はしているわけですけど、お薬については、どう考えればいいんでしょう。このまま飲み続けるものと考えるのか、減薬・断薬を目標にセットするのか…」
「そうだね、難しいのだけれど、ここから先は本当に、自分の自信次第で判断するという領域になるね。もう明らかに”不適応”は起こしていないから、日々過ごす中で自分の身体の声を聞いて、もう大丈夫、いけるぞと思うなら、一度薬をストップして様子を見るのも良いと思う。ただ、向こう数ヶ月以内に仕事の山場があったり、けっこうストレスがかかることが予想できるなら、急に辞めない方が安全かな」
「なるほど…そうですねぇ、ちょっと最近忙しくて、少ししんどくなる日も出てきてるから、次の一ヶ月はまだお薬飲んでおこうと思います。来月来たときに、またその時の状態で判断する、という感じでいきたいと思います」
スパッと決めてくれるわけではなく、しかし判断基準は提示してくれる先生の返答を受けて、僕の答えは「服薬継続」だった。
うーんやっぱりまだかぁ。ちょっとだけ残念な気持ちを抱きつつも、その意思決定をした自分の判断力には安心感を覚えた。
「病前」とは程遠い、しかしそこそこ安定した「低空飛行」を続けてきたこの2年。かつてのように思いっきり走ったり跳んだりはできないが、自分を無理に追い込んで潰れることもない。自分の状態を見極める感受性と、無理をしすぎずにどうにかこうにか生きていく力は高まった。これも一つの「発達」と言っても良いだろうか。
いずれにせよ、ここから先はある程度「決め」の問題であるし、「決め」たあと(通院や服薬をストップした後)も日常は続く。
昔より心身の調子に気をつけて過ごしていくことが大事、ということは変わらない。歳もとったし。これからもっと老いていくし。
診断書は、病の「はじまり」にしか出ない。では「終わり」とはいつなのか。
”そりゃあやっぱり、「死ぬとき」じゃないかなぁ。”
僕のぼやきへの友人の返答がきっと真理だな、と思う。
これからも僕らは、衰えながら、痛みながら、弱りながら、それでもだましだまし、生きていくのだ。
-----------------------------------------------------------------------------
本記事は、鈴木悠平単著『弱いままでも生きてゆける(仮)』出版に向けた断片として書き記した。
適応障害からの回復のプロセス等については、こちらのマガジンにも収録している。
概念としてのHSPの危うさと、それが「求められている」ということと
HSP(とHSC)、数年前ぐらいからじわじわ話題になり、目に見える範囲でもHSPを自認する個人の語りが増えてきたように思うが、話題になったり収まったりまた話題になったりの小さなサイクルの中で、その都度、医学の観点からの危うさを指摘する声も出ているし、色々とうーんという概念ではあるのだが、とはいえHSPが一定の人たちに「求められている」という現象も踏まえて整理が必要だなぁと思う。
HSPは、まだ医学的な疾患概念として十分に精査・吟味されておらず、その状態で雑に流布することが、他の疾患の見落としや、それによって適切な治療や支援に繋がらなくリスクも踏まえると、僕もどちらかというと「診断」や「普及」に対しては批判的に見ている方だ。
一方で、HSPの「名付け」がしっくり来る、安心するという個人の主観的体験と語りが増えていることにも重要な意味があるのだろうし、その実態をうまく解きほぐしたり、橋渡ししたりできればなぁとも思う。
他の疾患カテゴリとの類似点・相違点など、現時点で分かっていること・分からないこと整理しつつ、HSPと自認する多様な個人の感覚と、名付けの「その後」の物語を並べていくと見えてくるものがありそうだ。概念として粗さがあるものの、一人ひとりの生活単位で見れば、HSPという「名付け」を取っ掛かりに、結果として別の疾患カテゴリにちゃんと接続して収まる人もいるだろうし、医学的診断はどうあれ、HSP自認のもと、しんどくならないように色々と生活の工夫をしていく余地もあるだろう。
概念整理はちゃんと丁寧にせなあかんよと思う人なので、雑なブームになっていくことにモヤる一方で、医師が専門家クラスタに籠もって内輪で批判してる間に、一般レベルでどんどん広がっていくことが、将来的に当事者・医療どちらにとってもデメリットをもたらす可能性もあるわけで。チェックリスト的なのをやったら自分に当てはまって「しっくりきた」「安心した」という主観的な体験はよく聞かれるし、それ自体はその人本人の足場としては良いんだろうなと思うけど、「自分もHSPだ」と思う人がたくさん出てくるというのは、それだけ概念として「粗い」ということなのかもしれないし。
専門家の取材やレビューと、HSP自認の当事者の体験を行き来しながら、この少し危うさのある概念との適度な付き合い方を見出していくような企画を、えーと、あれです、いま書いてる本が一段落したら考えようかな。
色々あった上で血液型診断的なレベルに収まってほどよく冷めていくのか、それとも他の精神疾患と比較してちゃんと整理されてもう少し限定的な新規カテゴリとして確立されていくのか、どうなるんだろうね。
寒い日も、雨の日も、あなたを「ようこそ!」と歓待したい
僕は雨の日は、けっこう好きなんだけど、しかし昨日今日の寒さは堪えたね。みなさんお元気ですか。いや元気じゃなくてもいいんです。ご自愛ください。
雨の日や寒い日はただでさえ外出が億劫になるもので、なおかつ、着込んだり傘開いたり閉じたり、いつもと違う動作、違う空間づかいを要求されるので、個々人の行動の変化が総体として、街全体の緩慢さ、どんよりさ、窮屈さなどなどを醸し出す。
(そういえば同僚がこんなことをつぶやいていた笑)
寒い日とか雨の日のときの、ダメージが大きい人、というのも実はけっこういる。
病気や障害がある人は、身体が思うように動かなくなったり抑うつ症状が出やすくなったり、駅が混むことで車いす等での移動がより困難になったりと、外出のハードルが更にグンと高くなる。
それから、病気や障害とまでいかなくとも、「低気圧で頭痛が起こりやすい」という人は、かなーりいるんじゃないだろうか。
イベントや勉強会を企画・主催する機会が多い人、飲食店などを経営する人、福祉サービスに従事する人などは、経験としても統計としても、「雨の日は来る人数が減る」ということは知っている。
(そしてもちろん、赤字ばっかりじゃ続けられないので、主催者側は、天候も織り込んで参加者数の見込みを立てたり修正したり、全体で吸収したり、事前決済にしたり、あれやこれや工夫はする)。
まぁ、中には「雨降ったしめんどくさいからいいや」と思ってドタキャンする人もいるんだろうし、連絡ない人とかもいるので、そういうのはやめてほしいなー…と、思いつつ、究極のところ、その日に来る/来ない(あるいは来られない)理由はわからないわけです。
行きたいんだけど、どうしても身体が動かなくて行けない、という人も中にはいるわけで。
「すっごく楽しみにしてたのに、身体の調子が悪くて…」と、当日申し訳無さそうに連絡をくださったり、申し込み時点で「ぜひ行きたいんですけど、体調の波が大きくて…」と事前に相談をしてくださる方とやり取りするにつけ、あぁこの人たちは、これまでも歯がゆい思いをしてきたんだろうな、と想像します。
結局のところお天道様にはかなわないし、私たち一人ひとりの「からだ」だって、思ったときに思う通りに動いてくれるとは限らない。
「場」を開く側としてできることは限られていますが…オンライン参加や資料のデータ共有など、会場に来られなくても参加できる代替手段を可能な用意しつつ、会場にたどり着いた人には、「ようこそ!よく来てくれたね!」と、とにかく全力で歓待したい。
いつもそう思います。
最後にひとつお知らせを…
来週、こんなイベントをやります。
11/27(水) LITALICO研究所OPEN LAB#5: 「からだ」はどこまで拡がるか - 未来のコミュニケーションを創造する
「LITALICO研究所 OPEN LAB」は、社会的マイノリティに関する「知」の共有と深化を目的とした、未来構想プログラムです。
7月から毎月1回、シリーズ講義でやっており、今回が5回目、テクノロジーによる身体の拡張がテーマです。
障害や病気のある当事者の方、経済的に困難な方や遠方におられる方も含め、あらゆる人にオープンな知のコミュニティとなるよう、以下のような情報保障や合理的配慮を、すべての講義において実施しています。
・講演会場での合理的配慮(ライブ文字起こしや休憩スペースの確保)
・経済的に困難な方へのスカラーシップ制度(各回公募・選抜)
・オンライン受講制度(通年受講チケットにて提供)
・レポート記事・レポート動画の無料公開(順次制作・公開)
・レポート記事の英文翻訳(順次制作・公開)
水曜日の天気がどうなるかわかりませんが、会場参加・オンライン受講ともに可能です。
クラウドファンディングでの先行予約・サポーター枠と別に、各回
Peatixでの一般チケット販売もしており、そちらはまだ少し空きがあるので、よかったらお越しくださいませ。会場でもオンラインでも、あなたのご参加嬉しいです。
心の病は、「からだ」が覚えている
ここ2週間ほど、調子があまりよろしくなかった。
仕事中や人と会っているときに、ちょっと変な汗が出たり、動悸がしたりして、「おーっと、これは」と自覚した。
少し前から、定期的にジム通いするようになり、運動できるぐらいに回復してきていい感じだねーと主治医と話していたところだったのだが、ふむ。
上がったと思ったらまた下がる。まだまだままならないことがある。
とはいえ、要因のアタリは容易についた。
・原稿仕事の進捗がイマイチなことによる疲れと焦り
・複数プロジェクトが同じタイミングでちょっとバタバタしてきたこと
・原稿が書けないことに付随して、ドミノ倒しのように他の仕事も滞り、ボールが貯まり、と負のスパイラルに陥りかけたこと
・あわせて、身体にも疲れが貯まっていったこと
溜め込んだ状態で馬力でなんとかしようとしてもうまくはいかないので、食事・睡眠など生活リズムを整えることを優先して、ちょっと戻ってきたなというのが今週後半。
それから、動悸が出ているときに無理にそのまま作業を進めようと思ってもうまくいかないので、そういうときは潔くパソコンを閉じて、ジムに走りに行くことにした(そういうときは強度は低めで、ゆるーいジョギング程度にする)。1時間ほど走っていると頭もスッキリするし、動悸も収まるという結果を得たので、良い対処法を見つけたな、と思う。
寝る前の抗うつ薬の服薬と、月に一度の通院を続けている。適応障害と診断を受けてから、もうすぐ1年半ほどが経つ。
今日が通院日だったので、主治医と以下のような会話をした。
「いやー、やっぱりちょっと負荷がかかるとすぐ症状に出るもんですね。だいぶ回復してきたなと思ったし、実際回復はしていっているのだろうけど、やっぱりこう、根本的には"病前"の自分とは別の身体になったんだなぁという感慨があります」
「そうだね、一度崩れたときのことを、やっぱりからだが覚えているからね。反応は出やすくなるんだよ。でもそれは、実は病気になる前も負荷がかかっているのに気づいていなかっただけかもしれないし、症状が出やすくなったというのは、からだが早めにシグナルを出してくれるようになったということでもあるよ」
「そうですね、からだの声を聞きやすくなったというか。症状が出たら、それをトリガーにして対処を打てば良いというのは、ある意味わかりやすいですよね」
「心の病」といいつつ、それは身体症状としても表出するわけだから、心のさざなみとうまく付き合っていくうえで、耳を傾けるべきは「からだ」の声なのだろう。
自分で人体実験をしているようだ、といえば言葉が物騒だが、病気になってよかったなと思うのは、以前より自分のからだの声に敏感になることができたということだ。
こういう時に自分はストレスがかかりやすいな。弱ったときにはこういう反応が出るな。その反応が出たときにはこういう対処をすれば収まるな。などなど。サバイバルスキルを溜めていっている感じ。
吃ることがいいことだなんて思えなかった。「隠れ吃音」の僕が自分の体と仲良くなるまで
「君はちゃんと吃ることができるからいい」
そう言われたのはもう8年前のこと。当時は「はぁ…」と頷くしか返事ができなかったが、今でも折に触れて思い出す。
この言葉を僕に言ったのは、西きょうじさん。軽井沢に住んで、東京に通って予備校講師をしている、ちょっと変わった人だ。実際に授業を受けたことはないけれど、ひょんなことから紹介してもらい、以来ちょくちょくお酒を飲む仲になった。
西さんに言われたことは、「実感の伴わない知識まで、さも自分の考えかのように流暢に喋るよりは、下手くそでゆっくりでも、自分の実感から言葉を絞り出そうとできることの方がよっぽどいい」と、そういうニュアンスだったと思う。
だけど当時の僕は、むしろ「そのようにしか話せない」自分にひどく悩んでいた。流暢に、明瞭に話せる人になりたかった。スムーズに対人コミュニケーションを成立させられる人が羨ましかった。
頭の中と胸の内ではたくさんの思考と気持ちが渦巻くけど、それをうまく言葉に出来ないから吃る。結果、他人には伝わらない。「何が言いたいのか、お前の話はわかりにくい」と周りからよく言われていた。幼少期から青年期にかけて、そうしたコミュニケーション不全を多く経験してきたが、西さんとこの話をしたときは、それがより顕在化していた時期だった。
2011年。東日本大震災が起こった年であり、僕が大学を卒業して、大学院に行かずに石巻に移る選択をした年だ。
海と大地が大きく揺れた。それだけでなく、社会全体も、人の心も揺れていた。
地震と津波によってあっさりと崩され、飲み込まれていく街。圧倒的な自然の猛威は、大地の表面にしがみついて暮らす人間の無力さ、小ささを知らしめた。「安全神話」と地方への搾取構造によって成り立っていた電力供給。原発事故は、僕たちが生きる社会が虚構の上に成り立っていたという現実を突きつけた。
「前提」が揺さぶられ、未来が見えなくなったとき、自分はどうあるべきなのか。
それぞれに思うところはあっただろうが、大学同級生のほとんどは、就職や進学など、すでに決まっていた進路にそのまま進み、新しい生活をスタートした。3月11日から4月1日ー震災が起きてから卒業し、新年度が始まるまでわずか20日間という日数は、立ち止まって考えるにも、他の道を検討・選択するにも短すぎる時間だった。
僕はというと、彼らのように就職・進学するでもなく、休学・留年するでもない、「はざま」の時間を過ごしていた(別稿で書いた通り、当時海外大学院に合格していたが、渡航までに半年ほどの時間があった。結局、留学は延期し、ほどなくして石巻に移り住むことになる)。
行動するにしても、立ち止まるにしても、道を変えるにしても、何かを「選ぶ」ことは、他の可能性を一度断ち切るということだ。100点満点、望みが全て叶う選択などきっとないのだろう。だから、少なくとも選んだ道に後悔しないために、自分にとっての「正解」にするために日々を一生懸命生きるのだ。それはわかる、理屈としてはわかる。わかるんだけど、本当にそれだけなんだろうか…。
何かを選んだら、それを正解にするというシナリオしかないのだろうか。選びながらもためらう、前に進みながらも迷う、そういうあり方は、許されないのだろうか。
震災や原発事故をめぐる社会の言説、3.11以後にもどうあれ続いていく東京の日常。マクロからミクロ、そのどこにもフィットする感覚を持てなかった僕は、もともとの口下手の域を越えて、より一層吃るようになった。
うまく話せないならどうするか。書くしかない。発する言葉にしっくり来ていないから書く。伝えられていない感触が残るから書く。ブログに、Twitterに、とにかくそこにインターネットがあったから書いた。今ではそれが仕事になっているのだから皮肉だが、当時は誰かのためではなく、ただただ自分の生存のためだった。東京に残っていた頃も、石巻に移り住んでからも、日々誰かと関わりはし、しかしそこでは相変わらず口下手で、そんな日常の合間にほそぼそと、そしてぼそぼそと書いた。書くことが自分にとって楽しいわけではなかったし、それが何に繋がるのかもわからない。だから、吃ることが「いいことだ」なんて言ってもらっても、なかなか素直には喜べなかった。
*
西さんが言ってくれた言葉が腑に落ちて納得できたのは、それから1年ほど経った後、『自分の仕事をつくる』『かかわり方のまなび方』などの著者である西村佳哲さんによる3日間のワークショップに参加させてもらったときのことだ。西村さんは、さまざまな生き方、働き方をしている人たちへのインタビューをされてきた方だ。ワークショップは、インタビューの細かな手法や技術を学ぶのではなく、一人ひとりの「きくこと」に対する解像度を上げていこう、という試みだった。
そこで教わったことは3つ。「先回りしない」「相手についていく」「沈黙を恐れない」
その人が黙っていたり、言いあぐねているときは、待たなきゃいけない。言葉以前の「気持ち」が言葉になるまでの時間だから。お腹のなかに手を入れて、自分の気持ちにしっくりくる言葉を、「これかな?」「いいや、これかな?」と探り当てている時間だから。言葉が花開く瞬間を、聞き手が先回りして奪わないこと。そんな風なことを西村さんはおっしゃっていた。
この考え方を教わったとき、気持ちがずいぶんと楽になったのを覚えている。吃ることは、自分が自分らしい言葉を紡ぎ出すために”必要”な時間なんだということ。僕にとって書くことは、自分の中の気持ちを確かめる作業だったのだということ。その場その場ではうまく話せなくても、決して伝えることを諦めていたわけではなかったということ。
自分の中で、「話す」と「聞く」と「書く」が交差した瞬間だった。今、曲がりなりにも僕が仕事としてインタビューや執筆をできているのは、そうした経験があったからこそなのかもしれない。自分も、相手も、それぞれのペースで言葉を探している。上手に、早く話す必要はないのだ。
*
そこから更に数年。アメリカに渡り、日本に帰ってきて、26歳で今の会社に入り、いろんな仕事を経験する。クライアントとのミーティング、研修講師、会社説明会、チームマネジメントetc.人前で話すことも増え、自分でもそれを意識することもないまま、いつの間にかどもりは消えていた。
悩みながら、居場所を転々としながら、20代後半にしてようやく就職した分、凸凹な自分をうまく活かせる場所に、ようやく出会えたなという感覚がある。かかわる一人ひとりの多様性、困難に向き合う上での一人ひとりの痛みや悩みを大事にしてくれる組織だと思う。
とはいえ、スピード感はある。ビジョンを持って、明快に言うべきことを言う。その場その場で意思決定をして物事を前に進める。ためらいよりも決断が、思索よりも行動がどうしても大きな比重を占めやすくなる。
それでも仕事にやりがいはあるし、テーマも自分の関心と重なっている。忙しいけれど自分は適応できるだろう、適応できている。そう思っていたら、昨年にガタが来た。適応障害という診断。「適応できている」と思っていたら、身体は悲鳴をあげている。動機や息切れ、憂うつ感。やるべきこと、できること、やりたいことのバランス不全。やりたいことと外れているわけではないけれど、そのスピードや表現型は合っているのか。
そしてこのタイミングで、また「吃り」が出るようになった。上司や妻との会話で、うまく話せない。どもってしまう。違和感に気づいていながら考えないようにしてきたツケが利息付きでまとめて返ってきた。そんな夏だった。
身体を休める、薬を飲む、業務調整をする、そういうまっとうなケアの積み重ねで、適応障害の心身症状は次第に収まっていった。心や身体にのしかかっていたストレッサーを一つ一つ取り除いたり緩和したりして、回復していくための余白をつくる。そうすれば次第にエネルギーが戻ってくる。けれど、同じタイミングで再び現れた吃りについては、どうもそれらの症状とは性質が違うような気がした。休めば治るというものではなく、僕が他者と話し、関わることの根底に関わっているような感覚が拭えないでいた。
この吃りという現象をどう捉えて、自分はどう付き合っていくのか。そのヒントを得たのは、ちょうどこの時期に知り合った、『どもる体』著者の伊藤亜紗さんとの対談だ。意気投合したのは、”立て板に水”のように上手に話せているときのほうが違和感がある、ということだ。
“「私、大学の講義も3年で内容を全部変えているんですよ。”立て板に水”みたいに話せるようになってきちゃうと、学生に対して申し訳ない気持ちになるし、苦しい。新しいものにしてたどたどしくしゃべらないと伝わってない気がするんです。」
「仕事に慣れてくるとしゃべりが上手になってきますよね。同じことを繰り返し言っているようで…。単純に労力対効果でいったら効率良くなっているからいいことなはずなのに、逆に『このままでいいんだろうか』って思っちゃいます(笑)。」
「自分の輪郭を更新したくなるような感じですね。形成されてきたパターンや枠…ある種、自分の枷にもなっているものがずれたときが楽しいし、生きてる感がある。」
https://h-navi.jp/column/article/35027019 ”
生きてる感。
そうか、僕はどもっている自分が、たぶんちょっと、好きなのだな。生きてる感じがするから。
「君はちゃんと吃ることができるからいい」という西さんの言葉を思い出す。「言いあぐねているときは、”気持ち”が言葉になるまでの時間だから、待たなきゃいけない」という。西村さんのワークショップを思い出す。
しっくり来る言葉がうまく見つからず、吃ったり、たどたどしく話したりしている時間は、身体的には決して楽ではない。手近な仮置きの言葉に置き換えたほうが楽な場面もある。だけどそこでちょっとだけ踏ん張って、吃る体に自分を委ねてみる。もぞもぞと脱皮をするような感覚で言葉を探す。吃りながら訥々と言葉を発している時間は、自分が誠実でいられている感覚がする。
適応障害を発症したときに吃りも再発したのは、単なるストレス反応というより、「納得しきっていないことを話すことはできないぞ」という、身体からのメッセージだったのかもしれない。
吃りが多く出るときは、立ち止まって自分のあり方を見つめ直すチャンスである。ちょっと面倒で生きづらいかもしれないけれど、思考停止せず、誠実に生きてくためのシグナルとして、吃りはかけがえのない隣人なのだ。
*
それから1年。これを書いている今では体調もずいぶん回復し、吃りも日常的にはあまり出ない。
だけど時折、「隠れ吃音」と言っていいぐらいのささやかな吃りが表出することがある。いや、正確にはそういうときはむしろ積極的に吃りにいっているかもしれない。安心して吃れる相手と、そうでない人、あるいは場所・話題がある気がする。
流暢に話したほうが良い場面もある。それが悪いわけではないけれど、そればっかりだと息苦しくなる。吃りは「そろそろ息をしたいぞー」という体からのリクエストなのかもしれない。どもっているときのほうが身体的には息苦しいはずなのに、それが「息をする」ってことなのは、変な感じがするけれど。
鎧を着るときと脱ぐとき、鎧を脱いだ上で、さらにもぞもぞとぎこちなく脱皮するプロセスすらも見せられるとき。お互いにとって大事なテーマを、すぐに答えが出なくてもいいから、ゆっくりじっくり探りたいとき。そういうときは、吃るぐらいがきっとちょうど良い。
話すことは、共鳴することなのかもしれないな。
身の回りに何人かいる「隠れ吃音仲間」のかすかなシグナルは、周りの人はほとんど気づかない、僕たちだけのちょっとした秘密だ。
““どもりはあともどりではない。前進だ。”
武満徹『音、沈黙と測りあえるほどに』, 1971年, 新潮社”
僕たちは偶然に、「弱者」になる。そしてまた偶然に、「助ける人」になる
街中や電車で「ヘルプマーク」を着けている人を見かけることが増えた。外見からは見えにくい困難さのある方が、周囲からの認知・援助を得やすくするための意思表示のサインとしてつくられたヘルプマーク。東京都で2012年から作成・配布がはじまり、現在ではほとんどの都道府県で配布されている。仕事柄、比較的早くから知っていたのだが、目に見えて一般に普及してきたなと感じたのはここ1-2年(2018-2019年)のことだ。
東京で暮らしていると、一日1回は目にするぐらいになった。それどころか、乗り合わせた車両内にヘルプマークをつけている人が2,3人いる、という状況に出くわすこともまったく珍しくはなくなった。ヘルプマークを使用している人は、義足や人工関節等を使用している人、内部障害や難病などがある人、発達障害、精神障害や知的障害がある人、または妊娠初期の人など、多岐にわたる。入手するために障害者手帳や医師の診断は必要ない。ヘルプマークを必要とする人なら誰でも、市区町村の窓口や駅などで簡単に入手することができる。
ヘルプマークの普及によって可視化されたのは、世の中にこれほど多くの「見えない困難」がある人がいる、という事実である。ヘルプマークのことを知らなかったり使いたくなかったりで身につけていない人や、思うように外出ができない人がその背後にいると思えば、実態としては目に入る以上の割合だろう。個別の疾患や障害当事者の人数なら、少し調べればさまざまな統計・調査から、数字として知ることができる。だけど、日常生活を送る私たちの肌感覚に迫る形で、「こんなにもいる」ことを示すマークは、これまでなかったのではないだろうか。
しかし、と、ここまで書いて考える。
この車両全体を見渡したとき、「見えない困難」は、実はもっとたくさん隠れているのではないか。
お腹が痛くて必死に下痢を我慢している人、足をくじいてしまって立つのもやっとな人、連日のハードワークでくたびれきっている人、想い人に振られて今にも泣き出しそうだけど必死にこらえている人。マタニティマークもヘルプマークもつけていない。杖もついていないし車椅子にも乗っていない。声をかけたとして、誰かが助けられる類の困りごととは限らない。だけど、なんらかのマークで表象されていないけれど、すぐ目の前のこの人が、今にも助けを求めたいぐらいにいっぱいいっぱいである、という可能性は、決してゼロではない。
もちろん、ヘルプマークをつけている人たちも、今がどういう状態か見ただけではわからない、という点では同じである。内部疾患などがあり、身体が他の人以上に疲れやすい人、発達障害や精神障害があり、何かのトリガーでパニックや癇癪が起きる可能性が他の人より高いという人、などなど、他の人たちと比べて、困りごとが起きる「リスク(確率)」が高い、でもそれが表面上では区別がつかない、という人たちがヘルプマークをつけている。リスクが高い、というだけで、比較的元気なときもあるだろう。
車椅子に乗っている人はどうか。電車の乗り降りの際に駅員さんがスロープを設置しているように、移動においてニーズがあるということは一見してわかる。だけど、実は同じ人がトイレ介助のニーズも持っているかもしれなくて、たまたま介助者が同行しておらず、誰かに頼みたいけど、赤の他人にはなかなか頼めない…という「見えない困難」を抱えている、かもしれない。
健常者という言葉があるが、「常に健康な者」なんているのだろうか、と思う。同様に、「障害者」とカテゴライズされる人が、いつ何時も同じ「障害」があるわけではない、とも言うことができる。個々人のコンディションの波と、その時の状況で、私たちの「ニーズ」は微妙に揺れ動く。
「ヘルプマーク」の意味がない、と言いたいわけではない。「みんな困ってるからみんな我慢しようよ」と言いたいわけでもない。他の多くの人と比較して、常時、または持続的な困難がある人を「見える化」するための社会共通のシグナルをつくり、それを持つ人を「優先座席」というセーフティネットで受け止めやすくする。それ自体は必要なことだと思う。ヘルプマークも、まだまだ普及の途上だから、多くの人に知ってもらえると嬉しいな、とも思う。
しかし同時に、いまこの瞬間、車両にいる誰かが、より見えにくい困難を抱えているかもしれないということを、どう考えれば良いのだろう、と逡巡する。問うても答えがないことはわかっているのだけれど、私たちは、いつ誰が相対的な「弱者」となるかわからない、という不確実さの中を生きているのは事実なのだ。
こうした話をするときにいつも思い出すのは、ブロガーのfinalventさんによる「誰が弱者か?」というタイトルの記事だ。優先座席啓発のポスターを揶揄するネット上のネタを題材にしながら、政治・経済といった構造上の問題に言及しつつも、今この瞬間に誰がどのポジションにあるか、つまり「弱者」というのは偶然だろうと彼は言った。それだけを聞くとお先真っ暗な感じもするが、その偶然を不可避なものとして、その人固有の人生を送ることで、弱者も不幸も意味を失うのだ、とも続けている。これを読んだのが当時、寒空の下、たったひとりで貧乏留学をしていたニューヨーク時代(おまけに彼女に振られたあと)だったので、淡々とした彼の語り口と、自分の置かれた状況を照らし合わせて、だいぶと救われた気持ちになったのを覚えている。
しかしいま改めて読み返して、それでもやっぱり、偶然が偶然で終わらない(と、少なくとも思える)社会であれば、と願う。偶然のめぐり合わせとして、自分が突発的に「弱者」になった場合、あるいはそういう人を見かけた場合に、少しでも助けが得られやすい社会になっていってほしいし、していきたいと、僕はまだ思っている。
こと東京に関して言えば、さらに電車の中でのめぐり合わせと優先座席と助け合いの問題に絞って言えば、そもそもこの街には人が多すぎて、とてもじゃないが電車移動の際に他人を気遣う余裕など持てない状況に押し込まれている。それ自体は個人の倫理ではなく、マクロな政策として解決していくべき問題なのだろう。
とはいえ、この街の人たちが、他者を助ける力を潜在的にも持っていないかというと、そうではない、と僕は言いたい。
良くも悪くも雑で開けたニューヨークから対照的な東京の街に帰って来て、毎朝・毎晩中央線に揺られて自宅と職場を行き来する生活を初めて間もないころ、今でも覚えている出来事がある。
*
「ゴッ」
帰りの電車がちょうど中野駅に着く頃、車内で突然音がして振り返る。音のした座席近くを乗客数人が弧を作って取り囲んでおり、何か重い物が落ちたかと思って見たら、人が倒れていた。
中年の女性が、荷物を手に握ったまま、言葉もなく目をつぶっている。友人なのか母なのか、5,60代の連れの女性が地べたに座らせて背中をさする。中野駅に着き、扉が開いて停車しているが、自分では立って歩けそうにない。ひとりが座席をゆずり、ほか数名で抱きかかえてひとまず座席へ座らせた。
「そこのボタン押してください」
近くの女性が呼び出しボタン横の男性に声をかける。それを受けた男性はボタンを押して駅員を呼び、すぐに駅員から返事があった。
「どうされました?」「お客さんが倒れました」「すぐ向かいます。そちら4号車でよろしいですか?」「えーと、はいそうです」
ほどなくして駅員が階段を上ってきた。扉近くに立っていた乗客2名がスマートフォンを掲げて手を振り、「こちらですー」と駅員をいざなう。乗客が道を空けて駅員を倒れた女性のもとへ通す。
「大丈夫ですか?どうされました?」「貧血みたいです」連れの女性が答え、駅員と共に彼女を抱きかかえて外へ運んで行った。
3人が出て行くと、人々はまたすぐにスマートフォンを取り出して同じ姿勢で画面に顔を向け出した。乗務員の車内アナウンスが続く。
「先ほど、中野駅にて、具合の悪くなったお客様がおられたため、現在4分ほど遅れて運行しております」
電車が運行を再開するまでわずか4分。何事もなかったかのような、いつもの東京の車内。だけど確かに、さっきの一瞬、ここは「開いて」いた。偶然居合わせた人たちが、偶然に倒れた人のために、誰が言い出すともなく手を差し伸べた。言葉が、指が、腕が、ボールを運び、状況を動かした。ヘルプマークもマタニティマークもつけていない。その人が倒れることに、なんの予兆も予告もなかった。突然の、偶然の出来事である。それでもそこにいる僕たちは、動いた。
「お急ぎのところご迷惑をおかけして、申し訳ございません」
アナウンスは続いたが、とりたてて文句を言う人も見られない。僕も、それから2駅して阿佐ヶ谷に着いたので何事もなく電車を降りた。
「”ご迷惑”の対価としては悪くない時間じゃないか」
乗客がスマートフォンの画面に顔を戻す前、わずかに見せた安堵の色を思い出しながら家路につく。
時間は夜の11時前。退勤ラッシュと終電前ラッシュの間の、短いながらも比較的空いた時間帯だった。もっと混雑した時間帯だったら、人々の反応は違ったかもしれない。中には、イライラをあらわにする人も出てくるかもしれない。僕自身も、どうだろう。その時は近くに立っていて、わずかながらも「助ける側」の人間だった。だけど、その人が倒れた場所がもっと遠かったら?僕自身がくたびれ果てて、座席で目をつぶって眠りかけていたら?動くのがワンテンポ遅れたかもしれないし、先に動き出した人に任せてしまったかもしれない。
「弱者」が偶然であると同様に、「助ける人」もまた偶然のめぐり合わせであるのだろう。
それでも。きっと「助ける人」はいるのだろう。それが僕になるかどうかはわからない。機敏に反応して「最初の1人」になれるかどうかもわからない。だけど少なくとも、その偶然が「ゼロ」にだけはならないように、予備軍としての備えは持っておきたいものだ。ときにくたびれ、ときに酔っ払って帰りながらも、そう思う。
参考記事
「自分の傷なんて大したことない」と、あらゆる"当事者"に遠慮していた
1995年に地元・神戸で起こった阪神淡路大震災。当時、小学1年生だった僕は、寝室兼子ども部屋に布団を敷いて寝ており、勉強机の椅子が倒れてきて目を覚ました(と言っても、パイプのかるーい椅子だったので無傷である)。つまり僕も、当時の震災を経験した当事者である、と言えるのだが、阪神淡路の「被災経験」について、僕は語るほどのものをほとんど持たない。
Read moreどうしても仕事を休めない人向け、メンタルいわしたときの「いのちだいじに」初動対応
私も昨年経験したので、近い世代の働きマンたちやそのパートナーからちょくちょく相談受けるのですが、メンタルいわしたときって初動対応がすごく大事で、そこでやれる限りの対応をがっとやれると、それだけ予後がよくなると思うので、参考にしてもらえればと思ってつらつらと書く。
僕は医師ではないので、あくまで経験者は語る的な位置づけでほどよく参考にしてもらえれば嬉しいです。
まず大前提として…
がっつり休職出来る人は休んだ方がぜっっったいに回復早いから、休めるなら休んでくれよな!頼むから!
ということを声を大にして伝えておきます。
ここでは、それでも、さまざまな、実にさまざまな事情があって、「そうは言っても仕事やすめねーんだよ今」って人を対象に(いや休んでほしいんだけども)、働きながらでもどうにかこうにか死なないためのアドバイス的な位置づけになります。
考え方: 作戦名「いのちだいじに」への切り替えを、自分と他人両方に、なるべく早く周知徹底する
ドラクエの作戦あるじゃないですか、「ガンガンいこうぜ」とか「じゅもんつかうな」とか。あれです。一刻もはやく「いのちだいじに」に切り替えてくれ。それを自分だけでなく周囲にも認知徹底してくれ。
多忙な働きマンがメンタルいわしたとき、自分も周囲も従来の「ガンガンいこうぜ」感覚のままでいると、絶対にギアが合わないのです。
だって!エネルギーの総量が!超下がってるから!瀕死だから!
切り替えるための方法はいくつかあるので、実行可能なやつは全部やるって感じで低温運用に切り替えてください。
“・通院する
・可能な範囲で周囲に自己開示・相談
・急ぎでない予定は全キャンセル
・新規の予定入れない
・渡せるタスク渡す
・それでも残るタスクだけに絞ってやる
・食事・睡眠絶対死守(運動は元気になってから)”
①まずは通院してくれ、話はそれからだ
会社や自宅からアクセス良い、最寄りの心療内科を今すぐ予約するんだ。最近は、仕事帰りの勤め人のために、夜やってるクリニックもあるぞ。僕も初診は夜遅くまで働いてクタクタになったその足で向かったぞ。
なんせ、メンタルいわしてるときって認知のゆがみんが現れて、正常な自己判断できない状態なってますんで、「まだ大丈夫」とか思ってるのだいたい大丈夫じゃないですから。はやめに医師に診てもらって、お薬出してもらうなり、会社に見せる用の診断書書いてもらうなりしてください。
そして定期通院のリズムをつくってください。相談相手が外部にいる、それだけで少し心が楽になります。
②可能な範囲で症状の自己開示と周囲への相談を
直接の上長、家族やパートナー、同僚や後輩など、日常生活や仕事でかかわる人たちに対して、可能な範囲で自己開示と、対処方針の相談をする。無理に一人で抱え込むよりは、"具体的"に開示・相談した時方が全体最適になりやすいと思います。
「今こういう状態で、こういうことはできるけど、こういうことはしんどいんだ」と、仕事や家庭運営上、"必要な範囲での弱さの共有"をする、ぐらいの感覚で良いと思います。
③世界は意外と回るので、急ぎでない予定は全キャンセル
上長などと相談してもらえればと思いますが、自分が抱えていた仕事のうち、どうしても今日・明日とか今週中とかでやらなきゃいけないことは、ほんとにマクロかつドライにみると案外少なかったりします。
「出来ないより出来るに越したことないけど、まぁしばらくペンディングしててもどうとでもなるな」みたいなプロジェクトとかタスクとか、割とあるんで、そのへんは上長と相談しながら、これを機に思い切って業務整理・優先順位判断してみてはどうでしょうか。
④新規の予定入れない
これはもう読んで字のごとくです。コントロール可能な範囲では、少なくとも短期的に急ぎの「新規案件」を入れる必然性ないのでバッサリ切りましょう。
それ以外でも、メンタル病む人に限って「業務外の業務」的な、諸方面からのふわっとした相談とかランチMTGとか入れられがちだったりします。そういうのぜんぶバッサーっとブロックしてくださいね。
⑤渡せるタスクはじゃんじゃか渡す
これを機に後輩たちに責任&役割を移譲しましょう。不安なら、判断軸だけしっかり抑えたりすり合わせの時間をつくった方が良いですが、仕事を任せて部下が育つってことは往々にしてあるので、良い機会だと思ってください。
⑥それでも残るタスクだけに絞って一撃必殺で仕事乗り切ろう
もうね、あとは、それでも渡せない、休めないなって案件だけに専念してください。大事な商談とかプレゼンとか。ほかの仕事ゼロにするぐらいの勢いで渡して、それでも休めないなって仕事だけ手元に残しましょう。
⑦食事・睡眠絶対死守(運動はもうちょい元気になってからじわじわと)
当たり前のことですが、食事・睡眠時間絶対死守です。しっかり寝るんだーーーー!
---------------------------------------------------------------------------
なんだか取り留めもなく書きましたが、とにかくですね、みなさん「いのちだいじに」どうにか生き延びてほしいわけです。
幸あれ
「弱さ」をめぐる旅のはじまり
「適応障害ですかね。」
「そう思います。」
平日の夜、職場から徒歩5分のクリニックで、最近知り合った医師の先生とそう話したのは、今の会社で働きだして5年目の夏のことだった。
「仕事も人も、好きなんですよね。嫌な理由ないんですけど。でもしんどいんですよね。」
風邪をひいているわけでもないのにやたらと咳が出る。オフィスに向かうだけでドッと疲れる。ミーティング前には動悸がする。言葉以上に身体は正直だ。
適応障害というのは、特定のストレス要因に反応して心身の症状が起こる疾患である。受診の場に至ってなお「別に仕事が嫌なわけじゃなくて」と防衛線を張る僕に対して、「あなた、そろそろ限界ですよー」と身体が言っているのだ。
「俺もついにビョーキになったか」という、不思議な安堵と納得。「明日はどういう報告と相談をしようか」という、極めて実務的な対応方針の思案。そういう色々が混ぜこぜに頭を巡りつつも、先生に診断書を出してもらい、処方された抗うつ薬を帰り道の薬局で受け取った。
診断を受けた翌朝、通常通り出社し、パソコンを開いて、上長と人事部長にメールで報告した。直近で入っていた会議はキャンセルし、その他、急ぎでないもの、自分の手元でしばらく寝かせても当座支障がないものなど、いくつかの観点で業務を取捨選択し、緊急避難として減らせる限りの業務負荷とストレッサー回避をした。自分が診断を受けたこと、仕事についてはこんな対応をしていること、直近エネルギーが落ち込んでいて心配をかけるかもしれないが、自分を守りながら回復に向けてやれることをやっていこうと思っていること、などを妻に話した。それから翌週またクリニックに足を運び、職場との相談・対応状況を相談しつつ、業務調整をしながら療養を続けましょうという方針について話した。
家に帰る前にオフィス近くのベンチでパソコンを開き、その場でテキストを打つ。自分が現在「弱っている」ということ、一応のお墨付きとして、医師の診断を受けたこと、会社にも妻にも共有しつつ、業務調整をしながらもひとまずは仕事を続けてもいること、弱った自分のことを自分自身がどう捉えているか、等々を、なるべく淡々と、ジャッジを交えずに、かつ率直に現在地点の記録として書き残した。そしてその記事をSNSに放流した。
ほどなくして、SNSのコメント欄やメッセージボックスにたくさんの声が届いた。僕の心身の状況を気遣い、また支えようとしてくれるようなメッセージももちろん嬉しかったが、少し驚いたのは、それ以上に前のめりな様子で、さまざまな自己開示が寄せられてきたことだ。
「久しぶり。実は俺もいま同じような状態で」
「今、わたしのパートナーが心配なんだけど、どうしたらいいかわからなくて」
「数年前にまったく同じような状態だった。でも当時、そんなふうに職場や周囲に話すなんてできなかった。勇気あるよ」
などなど。
卒業して以来7,8年と会っていない、大学の同級生。
誰からも信頼されていていつも輝いていた先輩。
共通の友人の集まりで1,2度会って、SNSでゆるくつながっていたぐらいの知人。
採用の仕事で一度会ったぐらいの、当時学生だった子。
少し前に会社を辞めた元同僚。
それは「相談」というものではなかった。きっと「ただ、知らせたかった」のだと思う。そして僕に連絡をくれた。僕も、彼らのこえを受け取った。
お互いに何か即効性のある良い解決策を出せるはずもないし、「支え合う」というには滑稽なぐらい、お互いへろへろに弱っている同士のやり取りだ。だけど不思議と、気持ちが楽になった。具体的に何かをしてもらったわけではないが、診断を受けた直後に、自分と同じような経験をしてきた友人たちが幾人いる、という事実が、僕の心の引き出しの中にアーカイブされた。
「弱さ」を開示すると、似たような「弱さ」が引き寄せられて集まってくる。
巷のメンタルヘルスや生き辛さをめぐる言説では、「共依存」はよくないと、SNSは傷の舐め合いになりやすいと、そういうことがよく言われてきた。
ところが今回は不思議と、共倒れにはならなかった。むしろ、「弱さ」を開示しながら、一定の距離を保ち、弱いままでもつながっている、生きているという事実に、かすかに、しかし確かに支えられながら、それぞれがそれぞれに回復の道を歩んでいく。そんな感覚だったように思う。これはいったい、どういうことだろうか。
「強くある」ためのノウハウは見聞きするに事欠かない。企業研修で、ビジネス書で、ネットの記事で、「強くあれ」というメッセージが繰り返し発信されている。だけど、「弱った」状態でどう生きていくか、弱いままでも生きていける知恵については、教わったことがなかったように思う。
「弱さ」を開くことの可能性。人間関係の網の目の中で与え合うということ。自分の生を肯定する物語が開かれること。「弱さ」を携えて生きていく人たちと著者の対話を通して探求していきたい。
----
「弱さ」を巡る旅をしながら綴る一冊の書籍ができあがるまで、晶文社の安藤聡さんとの二人三脚で、また読者や友人たちとの対話のなかで、執筆プロセスを公開しながら進めていきます。
最初から構成を決めて埋めていくというより、旅をして、断片を書き連ねて、何を書くべきかがだんたんと見えてくる、そんな書籍になりそうです。
世代の宿題、そしてわたしの宿題 ぶっちゃけキッツイなーと思うこともあるんですけども
世代の宿題、というのがあるよな。たくさんあるんだけど、その中で、自分の宿題、というのがあるよな。そう考えながら仕事をしている。
ほんの数年前までは自分が生きるのに必死だったけど、いや今も必死なんだけど、歳を取るにつれ、この宿題は自分たちが受け止めてどうにかせんといかんよなという感覚が強まってくる。
全体的にカネも時間もなくてみんな必死のヘロヘロだよというムードの中で、真綿で首を絞められるような構造の中で、1)もう一度、私たちが拠って立つ倫理を共有すること、2) 魂を売らずに自律・持続可能なメディア環境をつくること、3)個人の心身がボロボロにならないようなクッションを敷くこと、そういうことを考えている。
まとまってはいない。仕事帰りに疲れた脳みそで書く。すまん。
宿題その① もう一度、私たちが拠って立つ倫理を共有すること
相模原、の後の、登戸と、元次官の息子殺傷。最近、頭の片隅にずっとあって、自分の思考と行動と言葉に影響している。日に日にその残響は実感を増す。
僕の同世代は、だいたい大学卒業前後というタイミングで東日本大震災を目の当たりにした。個人もNPOもボランティア団体も企業派遣も、みんなそれぞれの関わり方で、現地に飛び込んだり後方支援したり…僕もその中にいた。もちろん課題はまだ全部片付いてはいないが、損得ではない何かに、多かれ少なかれ「突き動かされて」いたのだと思う。
その少し前から、SNSが勃興したり、greenz.jpとかソトコトとかオルタナとか、そういう「ソーシャル系」の先駆けとも言えるメディアが立ち上がったりして、まだまだマスには遠かったかもしれないけど、社会的なイシューにコミットすることを、一定カジュアルにしたり、かっこよくしたり、そういうことをちょっと上の先輩たちがやってきた。
障害者差別解消法が施行されたり、法定雇用率がアップしたり、あとはなんだ、働き方改革とか、ダイバーシティ&インクルージョンとか、SDGsとか、レインボーとか、心のバリアフリーとか、オリ・パラとか、とにかく少なくともお題目としては、色々、掲げられてきたはずだ。
そういう「前進してる感」が、まがりなりにもちょっとずつ積み重なってきたはずの機運が、1つ、2つ、3つと、片手で収まる数の事件で、オオカミの一息で吹き飛ばされた子豚の藁小屋よろしく、あっけなく崩れてしまった。そんな感覚に陥る。
やってる方はそれはそれで真剣に企画してきたはずなんだけど、それでも、ソーシャルなあれやこれやをオシャレにしていくあれやこれやが茶番みたいに思えてくる。くそう。
ちゃんと「怒る」、ちゃんと「それはダメだ」と言うことの必要性を感じる。一方で、敵を想定した短期的なキャンペーンでは、根本解決に至らないことも知っている。
彼らをして、その行動に至らしめた構造こそを問わねばならないことはわかっている。しかし、それにしても、余裕がない。社会に、私に。
障害のある人に限らず、誰もが「役に立たなければいけない」というプレッシャーにさいなまれているように見える。無意識に、しかし水が染み渡るかのように、優生主義や能力主義の亡霊が私たちの思考と行動に影響しているように思える。
彼らの行動選択自体にNOをちゃんと言わねばならないということと、社会全体の「余裕の無さ」を前にして、どう伝えれば届くのかということ。後者はより難しい宿題だ。
倫理を打ち立てなければならない。方法はまだ見えない。だけどそれが必要なのは確かだ。
誰かを悪者にして溜飲を下げるのではない、歴史と構造と倫理へのまなざしを持った、愛と知性が必要だ。
宿題その② 魂を売らずに自律・持続可能なメディア環境をつくること
先立つものはお金である。それも、紐付きでないお金だ。あるいは十分に分散されたポートフォリオだ。
今日こんな記事を読んだ。
書いていることはいちいち正論である。僕もこんないい子ぶったツイートをした。
しかし一方で、ぐぬぬ、である。
ここに書かれている「昔話」にあるような、「正直さ」と「めんどくささ」をもって、メディアと編集部が堂々とクライアントや広告部と渡り合える余裕をもった媒体が、今、日本のどこにあるのか。
高級ブランドと一流のクリエイターと、信頼関係を築くに至る、編集者の深い教養とセンスと、ネットワークと。それらを貯める余裕がほとんどの媒体の編集者には、いまない。
それで良いとも、余裕がないからしょうがないとも思っていないからこそ、歯がゆい。
「ウェブ以後」の、どんどんコンテンツが無料化されていく流れのなかで、人材育成のための時間と潤沢な制作費・育成費をどうやってつくるのか。魂を売らずに自律・継続可能なメディア環境をどうつくるのか。
「タイアップ記事なんて、なくなればいい」とまで勇ましいことを言い切れない現状に歯ぎしりしながら、次のメディア環境と経済圏をどうやってつくればいいねんって試行を、同世代の友人たちと、一緒に、あるいはそれぞれに、けっこう必死こいてやってる。だいぶ無理ゲーやなと思いつつ、活路を探している。
宿題その③ 個人の心身がボロボロにならないようなクッションを敷くこと
それでいて、自分も周囲の人も倒れないで済むように、ということ。
人口ボーナスに支えられた高度経済成長は今は昔。働けば働くほど豊かになる保障もなく、しかしぼんやりしていると食っていけない。いやーキッツい。しかしそれでも、いやだからこそ、心身の健康を守るということを大事にしないと、とても続けてられない。
昨年、体調を崩した。まだ治りきっちゃいない。それでもどうにか、こうにか、やっている。
5年ぶり、10年ぶりに、知人友人から連絡がくる。「実は僕も」「実はパートナーが」まじかお前もか。よく生きててくれた。しかし大変だよなお互い。と、戦地で同胞に会ったかのような気分である。病院やカウンセリングを紹介する。たまに飯でも食おうやと声をかける。あとは、祈る。そんな感じ。
心身をボロボロにするまで走ることはない。そんな無理を重ねて自己疎外をしていては宿題1も2も到底ムリなので。
疲れたら休む。困ったら助けを求める。自分がちょっと余裕があるときは、しんどくなっている人を支える。そういう循環をどうにかこうにか回していく。
粗にして多な、孤立しない繋がりを、クッションを、そこここに敷いていく。ひとつで全部を救おうとしない。非力さを認める。同時に、非力な支え合いの持つ力を、信じる。
そんなことを考えている。
すまん、俺も寝る。みんなも、休んでくれよな。
「こころの病」とのなが〜いお付き合い、あるいはサステナブルメンヘラのすすめ - 適応障害・抑うつを経験した私の場合
昨年の7月に適応障害と抑うつ症状との診断を受けた。もうすぐ1年が経つのか。
診断を受ける前は、オフィスに着くと動悸や咳や汗が出て、不安や焦燥感に襲われた。そういった「急性症状」は今は全くない。
適応障害は、原因となるストレスから距離をあけ、適切な休息・療養をすれば、通常半年ぐらいで回復すると言われている。
実際、良くなったと思う。
少し状況が変わって身軽になり、過度なプレッシャーやストレスを感じないで済むような働き方・就労環境をつくることができた。自分で時間・場所・内容の裁量をより効かせられるようになったのが大きく、本業・副業問わず、色々工夫しながらうまいこと続けられているとは思う。
だから今が「適応障害」かというと、その字面から受ける印象と、身体感覚にはややギャップがある。
しかしながら、今が「寛解」の絶好調かというと、そうとも言えない。
まず、体力は明確に落ちた。
以前より疲れやすくなっている。
平日、仕事に支障の出ないパフォーマンスを出せてはいるが、土日にはもう体力が残っていない。家事・育児の合間はほとんどボヘーっと寝ている。
ちょっと気が重たい案件があると、堪える。
常時ストレスにさらされているわけではないので、ちょっとヘビーな交渉だったり、人のケアに関することだったりが局所的に発生しても十分に対応可能なレベルなのだが、終わったあとの数日は、反動でどよーんとなる。
ストレスに対する「感度が上がった」、とみなすのか。
無理をして働いて麻痺していた感覚が「正常に戻った」、とみなすのか。
もともとのパーソナリティから来る社会適応上のストレスに対して、心と身体が「より素直に反応するようになった」、とみなすのか。
いずれが適切な表現なのか(あるいはこの全てか)わからないが、とにかくそんな感じであるので、「絶好調!」って感覚はしばらく来ていない。長時間ワークはもう無理で、瞬間最大風速でなんとかやっている感じ。
引き続き、寝る前に一錠の抗うつ薬と、月に一回の通院は継続している。
「お薬、いつ頃まで必要でしょうかね」という話を先生ともする。
「ゆうへいくん自身はどう思う?」と先生。
「うーん、体調とか、疲れやすさとか考えると、まだ回復しきったとは言えないな、もうちょい必要かなって感覚です」と僕。
「うん、そうだろうね」と先生。
自己認識は出来ているし、順調な方だよとも言われるし、そう思う。
(僕の場合は休職しないという選択肢をとったので、もっと早く回復したかもなというifはあるが、それも含めて自分で選んだし、その中でうまくやった方だと思う)
それでも、時おり考えてはちょっと、どよーんとする。
これはいつまで続くんだろう。
「寛解」とはいったい、なんだろう。と。
どよーん。
…と、書いてみるなどするが、とはいえ7-8割はもう「分かって」いて。
「すっかり元通りに元気に」なることをゴールとすると、きっとうまくいかない。
発症以後の、ちょっと疲れやすく繊細になった我が心身と、なが〜い目線でお付き合いしていくということなんだろうな、と思う。
*
自分もこんな体たらくだが、いや、だからこそなのか、20代の、自分より少し若い子たちの相談に乗ることが多い。「メンタルヘルス相談」と「キャリア相談」と「家族・パートナーシップ相談」とが、人によってそれぞれの成分でブレンドされたよもやま人生相談である。
セルフケアの力が弱かったり、それを高める経験が不足していたり、経験を積んでいくための伴走者とつながっていなかったり、という子が多いのが気になっている。
それまでの生育歴も関係して、本人の自己肯定感の低さ、見捨てられ不安などから、無理に「がんばろう」としてしまう。相談ができずに、溜め込んでしまう。
結果、ストレッサーから距離を開けるのが遅くなったり、受診に至るまで足踏みしたりする。
僕に話してくれた段階で、「いや、それは早く病院いこ?」って状態にある場合は、僕の主治医を含めた信頼できる&相談しやすいところを紹介して受診を促すなどしている。
急性期はとにかく医療とつながっての治療・休養が第一だと思うが、もう一つ気になるのは、休職明け等のセルフケアや生活・業務リズムづくりが難しく、頑張りすぎてまたダウンしてしまう、というケースが少なくないことだ。
私も人のこと言えないのだが、急性期を経たあとは、いかにセルフケアを丁寧にやっていくかが大事だとひしひし感じる。
ただ、メンタルいわしたあとは、心も身体も体力の上限値が減退しているので、ひとりでなんとかしようとするとだいたいうまくいかない。サステイナブルな生活リズムとセルフケア方法を確立するために、急性期を経た「その後」も相談できる相手と繋がり続けることが大切だ。
定期的な通院はもちろんだが、職場においても、上司や同僚との面談をこまめに入れて、相談しやすい時間や関係、あるいは周囲に気づいてもらいやすい機会を意図して組み込んでいくことが必要だと思う(休職前の感覚でタスク詰め込むと絶対詰むので…)。
結局のところ、
・十分な休息と睡眠
・バランスの取れた食事
・適度な運動
・家族や趣味の時間など、リラックスできる時間の確保
などなど…健康になるための「当たり前の要素」を、ないがしろにせず一個一個丁寧に満たしていくのが一番の安定の道なのだと思う。
31歳、そもそも体力が落ち始める年齢に差し掛かっていたという要素もあるだろうが、僕はもう、以前のように朝早くから夜遅くまで働き続けることはできない身体になった。
夜や土日に、はみ出たタスクを無理やり終わらせるという芸当ができなくなったわけだから、「アディショナルタイムは無い」という前提で仕事を組むしかないのである。
逆に、睡眠や食事、運動など、健康維持のために必要な時間は何があろうと最優先でブロックする、という前提で生活設計しないといけない(まだ完璧にはできていないけど)
「総量」が少なくなった稼働時間でどう稼いでいくか、ということが今後の職業生活で必須条件になってしまったようだけど、今の自分なら案外とやれそうな気もしているし、それはそれで試行錯誤を楽しんでいこうかな、と思う。
「その後の不自由」を生きるとは、きっとそういうことなのだろうし、「回復とは、回復し続けること」だと先輩たちも言っている。