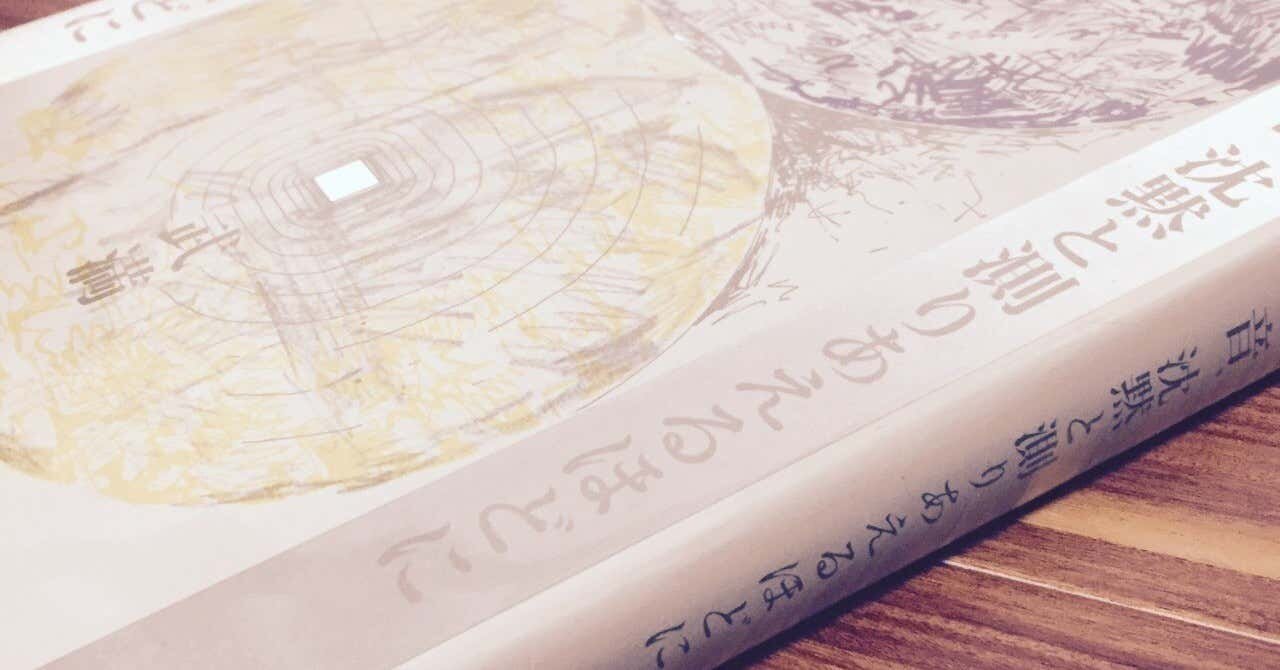2023年10月27日・28日に韓国・ソウルにて参加した「障害学国際セミナー2023」の発表ポスターのPDFとテキストを掲載します。
Read moreArchiving Narratives by people living with illness in public libraries in accessible and useful ways for citizens; a case study of Tobyoki Bunko" in Japan.
I participated in East Asia Disability Studies Forum 2023 from 27 and 28 October 2023 at Seoul, Korea. Here I upload my poster presentation PDF file, and texts of it below.
Read more絶望を分かち合うという希望 - 熊谷晋一郎さんインタビュー
「わたし」には、無限の可能性があるわけではない。身体も歴史も有限である。
では、病気や障害による症状、望んでもいなかった出来事や経験……さまざまな「痛み」すらも、自分の人生の有限性として、我慢して生きていくしかないのだろうのか。それとも別の道があるのだろうか。
「わたし」と「回復」をめぐる、熊谷晋一郎さんの物語を辿る。
Read more自分の痛みに名前をつける。浦河べてるの家の当事者研究に教わったこと
咳が出ない。曇天の下、ただひたすらに続く国道235号線を走る道中でふと気づいた。オフィスから物理的に離れるだけでこんなにわかりやすく収まるのかよと笑ってしまう。そしてようやく、ああ自分はやはり相当に無理をしていたのだなという事実を受け止める。
Read moreわたしと発達障害 - 「名付け」のない診断域外をさまよいながら
約1年前から、コンサータ(薬名:メチルフェニデート)を処方されて毎朝飲んでいる。発達障害の一つとされる、ADHD(注意欠如・多動性障害)の症状に対して処方される薬で、脳内の神経伝達物質の働きを良くして、集中しやすくするというもの。
日々、ただ生きているだけで色んなものに注意を持っていかれて、脳みそが常に忙しい。幸か不幸か、瞬発力と処理速度はあるので、来たものをどんどん打ち返していく形で、色んなプロジェクトを同時並行で進めることは出来るのだけど、それぞれで発生する重たい案件(主に原稿とか原稿とか原稿とか)は、いつも〆切ギリギリの過集中で乗り切って、終わったらドッと疲れる、みたいなことになる。いや、〆切ギリギリというのは半分ウソで、周囲のみなさんの本当に本当に寛大な便宜によって、それぞれに〆切を延ばしてもらったり待ってもらったりしながらどうにかこうにか、懺悔と謝罪を重ねて、生きている。
薬が効いてちょっとでも楽になるならそりゃあありがたい、ということで、適応障害がきっかけで診てもらっている主治医に相談して、途中からコンサータも処方してもらった。最初は18mgで、なかなか効果の実感がないので途中から36mgに増やした。飲むと、気持ちシャキンとするかな、という感じ。目立った副作用は今のところ出ていないので服薬を続けているけれど、とはいえ色んなものに追われる毎日なのは変わらない。難儀だ。
通院についても服薬についても、自身の特性の凸凹についても、特段隠してはいない。かといって自分からアピールすることもない。日常のコミュニケーションの中で話題になれば話しはする。自分にとってはその程度の要素でしかない。ただ、こんな風に聞かれたときは、言葉の座りの悪さに、もにょもにょしてしまう。
「お薬が出てるってことは、悠平さんも発達障害なんですか?」
「うーん、まぁ、そうねぇ、そういうことになるのかもねぇ」
なぜもにょもにょするのか。それはひとえに、「発達障害」という概念が示すもの、その言葉の用法、「診断」=名付けに込める期待、当事者性・当事者意識といったものが、あまりにも多様だからだ。そして、実際に自分の困り感が、「発達”障害”」とか「ADHD(注意欠如多動性”障害”」とか「ASD(自閉症スペクトラム”障害”)」といった、”障害”と表現することが妥当なのかというと、けっこう微妙なレベル感だからだ。なので、「われ発達障害当事者ぞ」と声高に言うのもなんかこうしっくりこないなぁというか、ちょっと遠慮しちゃうなぁ、という感じなのである。
*
そもそも「発達障害」とは何か…という話を厳密に突き詰めていくと手に負えなくなるので、ひとまずの現時点で概ね社会的な合意の取りやすいラインでの記述に留めさせてほしい。
発達障害は、先天的な脳機能の発達のアンバランスさ・凸凹≒「特性」と、周囲の「環境」とのミスマッチによって、日常生活や社会生活に支障や困難が生まれる障害であると言われている。
日本では「発達障害」というカテゴリーは、その中に大きく「ADHD(注意欠如・多動性障害」、「ASD(自閉症スペクトラム障害)」、「LD(学習障害)」の3つのグループを含んだものという想定で用いられることが多い。ただこれは、海外ではあまり見られない日本特有の整理・用法であり、更には行政上の定義・分類と、医師が診断する際の定義・分類も完全には重ならず、なかなか扱いが難しいことも留意しておきたい。
ともあれひとまずは、先天的な凸凹と環境の相互作用によって生きづらさや障害を感じる人たちがいて、その人たちの特徴や困難さを捉え、名付け、医療や行政で支援するために、あるいは当事者・保護者たちが仲間とつながるために、「発達障害」というカテゴリーが、現在の日本社会で広く共有され、使用されているということは事実だと言っていいだろう(話すと長くなるので詳しく知りたい人はこちらの記事でも入り口にしていただいて各自どうぞ)
自分が、あるいは家族や身近な人が「発達障害かも?」と思ったときにはどうするか。書籍やインターネット上のコンテンツを参考に理解を深めたり、必要そうな対策をとってみて、それで楽になるということも勿論ある。しかし、困り感が強い場合は、自己診断で留めず、医療機関にかかって検査や診断を受けることが推奨される。医師をはじめとする専門家の目を通すことで、自分自身を適切に理解する助けになったり、他の病気や障害の可能性を見極めることができたりするからだ(必ずしも医師の目が100%ということではない)。
じゃあ医師は何を基準に私たちが発達障害かどうかを診るかというと、さまざまな研究をもとに作成される「診断基準」というものがあって、それを拠り所にして診る。発達障害に関しては、『DSM(精神障害の診断・統計マニュアル)』または『ICD(国際疾病分類)』というものが使われていて、それぞれ版を重ねるごとに診断カテゴリや診断基準も変わっていく。
たとえばADHD(注意欠如・多動性障害)の、『DSM-5(精神障害の診断・統計マニュアル第5版)』における診断基準は概ね以下の通りだ。
①不注意および/または多動性―衝動性の症状によって、生活に支障が出たり、発達が妨げられたりしている
②12歳までに、不注意または、多動性―衝動性の症状が見られた
③家庭や学校、職場などの2つ以上の環境で、不注意または、多動性―衝動性の症状が見られる
④症状が社会的、学業的、もしくは職業的機能を損ねている明らかな証拠がある
⑤統合失調症や他の精神障害の経過で生じたのではなく、それらで説明することもできない
https://h-navi.jp/column/article/126 より。
さらに詳しい記述はDSM-5そのものをあたってほしい
ここでポイントなのは、代表的な症状に当てはまることと、社会生活に支障をきたすほどの不適応・困難さがあること、その両方が必要だということ。
つまり、ADHDなりASDなり、その特徴として挙げられる典型的な症状やエピソードが見られるだけでは診断基準に満たず、それが「障害」といえるほどの困難さがあってはじめて、診断がくだされることになるのだ。
そもそもの特性の凸凹は誰しもあるのだが、その中でも凸凹の度合いが大きい人たちというのが、先天的に一定割合生まれてくる。僕もその一人だろう。ただ、それが即、障害ー困難や生きづらさに繋がるかというと、そうとは限らない。環境の影響もかなり大きいのだ。
同じような凸凹の強さ・傾向であっても、環境によってはそれが目立たなかったり、逆に強みになることもあったりして、障害を感じないケースは多くある。逆に、凸凹の度合いはそれほどではないとしても、環境とのミスマッチが大きければ不適応を起こすことも十分にある。また、先天的な凸凹が強かったとしても、後天的なスキル獲得や道具の活用によって、生きづらさを軽減することはできる。それゆえ、同じような特性がある人でも、それが発見され、診断や支援を受けられたかどうかや、どんな環境で過ごしたかによって、個々人の予後は大きく異なってくるのだ。
また、バイオマーカー(生理学的指標)がないため、上記の同じ診断基準を参照していても、医師ごとに判断の仕方はどうしても異なってくる。属人性を排除しにくいのも発達障害診断の特徴だ。
これらが、自分が「発達障害なの?」と問われたときに、迷いなくYESと答えることを難しくしている要因だろう。特性の凸凹や、それによる困り感は間違いなくあるんだけど、どうにかこうにか、自分が生きやすい環境や働き方を見出して、社会適応出来ていると言えば出来ている。「障害」の診断基準にハマるかというと、微妙なラインだ。自分の調子が悪いときに受診するか、比較的広めに判断する医師にかかったら、診断書が出ることもある、というぐらいの立ち位置だと思う。
*
実際に、「発達障害の診断を取ろう」という目的を持って受診したことが、これまで2回ある。
1度目は、今から4年前のことだ。
子ども〜成人まで、発達障害特性のある色んな人たちと関わる仕事をする会社に入って数年。仕事を通して発達障害のことを知り、学び、理解を深めていくたびに、どんどん「これ、俺やん」という感覚が強まっていく。27,8年生きてきて、色んな失敗、つまづき、しくじりを重ねながらも、どうにかこうにか働いて暮らしているけど、どうにも世界とうまくフィットしていない感覚がある。なんだかずーっと、生きることが「ぎこちない」。自分のこの主観的な経験は、誰しも経験する程度問題なのか、それとも、発達障害というもので説明ができるものなのか。診断が出るかどうかはわからないけれど、少なくともその確認がしたい。自分のことを理解したい。そんな欲求が日増しに強くなった。
仲良くなった同僚の一人が診断を受けたという病院を紹介してもらって、そこに行くことにした。
職場から片道2時間弱。電車に揺られて鎌倉へ。ひょうひょうとしたおじいちゃん先生が院長の、小さなクリニックだった。
院長との診察が1回。訥々と、自分が感じていること、これまでのこと、現在のことを話す。後日、心理士によるWAIS(ウェクスラー式知能検査)を実施。2時間程度、色んな課題をやって帰る。また別の日に、WAISの検査結果と心理士の所見を受け取る。一番高い項目と一番低い項目の差が30ほど開いていた。所見に書かれた状態像、困難例、支援例は、いずれも、まぁそうだよな、という内容だった。終わってからまた院長先生との診察へ。また訥々と、近況を話す。
「どうかな、自分のことが少しわかってきたかな」
「そうですね、まぁだいたい」
そのまま診察は終わった。WAISの検査結果とは別に、この人はADHDですよとかASDですよとか、「診断書」が出るのかとおもったら、特に何も出されなかった。質問して、お願いすればなにか違った展開になったのかもしれないけど、凸凹はわかったし、なにか福祉制度を利用したいわけでもないし、まぁこんなものなのか、と思って通院を終了した。
通院を終えてから1,2ヶ月ぐらいの間、同僚や友人、監修の先生などに、雑談がてら、受診したことを話したりWAISの検査結果を見せたりした時期がある。日頃の僕の様子を知っている人たちなので、「まぁ、そうだろうねぇ笑」とか「言語性たっか!笑」とか「知覚統合が低めなのね。言語理解とこれだけ差があったらしんどいよね」とか、まぁそんな感じでライトに楽しみながらフィードバックをくれた。
「たとえるなら右腕の筋力だけめっちゃ発達してて、そのちからで色々乗り切ってきたんだけど、反動でずっと背中が痛い、みたいな感じだろうなと思って見てたよ」
友人の一人のこの表現がとてもしっくりきて、「ああ、そうそう、そんな感じ!」と、自分のしんどさを説明してもらえて気持ちが楽になったのを覚えている。
そこからしばらくは、「診断がほしい」という気持ちはなくなった。相変わらず色んな場面で困り感は発生するんだけど、色々経験を積んで自分で対処できるようになったり、チームで働くことで補完し合える環境になったり、結婚して日常生活の安心が得られたりと、人生全体が少しずつ進捗するにつれて「自分が発達障害かどうか」ということが重大トピックではなくなっていった、というのが適切だろうか。
傾向があるかないかと言われれば、明らかにあるし、親しい友人間でお互いの凸凹エピソードをネタに笑い合うことはあるけれど、わざわざその一面を強調するほどでもない。まぁまぁ社会適応できるようになった「発達凸凹さん」という認識でそこから数年を過ごした。
「やっぱり、発達障害の診断も取ろうかな」
そう思って再び専門医にかかったのは、今から1年半ほど前。
その少し前に、仕事での無理がたたり、心身の調子を崩して「適応障害」の診断を受けたのがきっかけで、再び「そのこと」を考えるようになった。
うつ病、適応障害、パニック障害etc.などの精神疾患になった成人が、受診・休養をきっかけに、基底にある先天的な発達障害特性に気づき、診断を受けたというパターンはけっこう多い。精神疾患がいわゆる「二次障害」として、自分にシグナルを与えてくれた、というプロセスだ。
身の回りの知人・友人にも、仕事を通して出会い、インタビューをした人にも、そのルートを辿った人は少なくなかった。自分が体調を崩した当時は「あ、これ自分も同じパターンだわ」と、苦笑いしたものである。
企業で働いて、管理職にもなって、色々工夫しながらどうにかこうにか適応できていたはずだったのだけど、やっぱりしんどさはなくならない。「診断」がどうしてもほしいってことじゃないけど、スッキリした方がなんとなく楽な気がする。診断が出たからといって、その結果に振り回されることもないだろうし、自分の中で疑問や不安があるわけではないけれど、答え合わせぐらいのつもりで発達障害の診断ももらっとくか。そんなふうに考えた。
適応障害がきっかけで受診し、今も毎月通っているクリニックの主治医に相談をした。
「先生のお知り合いで、発達障害の専門医がいる精神科、紹介してもらえませんか」
「うん、いいけど、悠平くんぐらい自己理解してて対処も出来ているレベルだったら、診てもらってもあまり変わらないと思うよ?」
「まぁ、そうですよねー、たぶんそうなんですけど、なんというか、色々あったし、もう一度受けてみたいなぁって」
「わかった。じゃあ連絡しとくから、〇〇クリニックの△△先生で予約して行ってみて」
予約をして、都内某所のクリニックへ。
適応障害になってからの通院歴、これまでの経緯、自覚症状や困りごとをバーっとWordに書き出して印刷し、数年前に受けたWAISの結果と一緒に持参。「うおー俺は今回こそ診断取るぞー!適応障害とADHDとASDのトリプルホルダーじゃーい!」みたいなテンションでツマにチャットを送り、電車に乗りこむ。いま振り返れば妙にやる気満々すぎる患者である。めんどくせえなこいつ。
以前、同僚に教えてもらって行った鎌倉のクリニックよりずっと大規模な場所だった。ロビーで少し待ち、名前を呼ばれて部屋に入る。
「今日はどうされました?」
ガタイも良く、眼光鋭い先生だった。先ほどの強気はどこへやら、ちょっと緊張しながら資料一式をお渡しし、自分が書いた文章に指差しながら、しどろもどろに説明した。
「まぁその…こうこうこういう仕事をしていて、以前も傾向あるかなと思ってWAISも受けた結果がこれなんですけど、最近適応障害になって治療中なんですが、やっぱりベースに発達障害もあるんじゃないかと思って、改めて診ていただきたいというか…いやあの、こうやって自分でエピソード書き出すとバイアスかかって診断基準に寄せちゃうってのはわかってるんですけどね、なので先生には割り引いて聞いていただきつつですけど、でもやっぱり…」あーだこーだあーだこーだ。
振り返るとやっぱり、我ながらめんどくさい患者である。書いていて変な汗が出てきた。
その先生は、主治医の申し送り書やWAISの結果も見ながら、僕の話を黙って聞いていたが、しばらくして口を開いた。
「なるほど、はい、はい、おっしゃることはわかりました。じゃあちょっと改めて質問しますね」
先生は診察用紙にやや大きな字で「ADHD」「ASD」と並べて書き、それぞれマルで囲んだ。
「あなたは自分で、ADHDとASDどっちが強いと思ってますか?」
「ADHDですね。どっちもあると思いますけど、強いのはADHDでしょう」
「そうですか…。僕の見立てはね、明らかにこっち(ASD)」
そう言いながら先生は ADHD < ASD と大きく不等号を書き足した。
「表出する困りごとの背景として、大きく衝動性と常同性どっちが効いてるかといったら、あなたの場合は圧倒的に常同性の方」
えー、マジすか。いや、混合型だろうなぁと思ってはいたけど、そっち(ASD)の方が強いとは思ってなかった…(という話を、帰ってきてツマや同僚、友人に話したら「え、そりゃ絶対そうでしょw」「ADHDもあると思うけどさ、ASD性もめっちゃあるw」「むしろASDの方が強いって自覚なかったのかw」と爆笑された。あ、はい)。
「それから、これもやってごらん」
続けて先生は、A3裏表1枚のチェックリストを差し出した。10セクターに分かれた質問が全部で80問ほどある。該当するものに○をつけていき、集計する。それは、パーソナリティ障害のスクリーニングを行うための簡易質問シートだった。
「どう?」
「はい、集計できました。うわぁ…」
ほとんどのセクターでは0個か1個しか○がつかなかったのだが、演技性パーソナリティ障害、自己愛性パーソナリティ障害に該当するセクターの質問だけたくさん○がついた。
「なにか生きていく上での不適応や生きづらさを感じるとき、そこにはストレス、身体特性、精神疾患、発達障害、と色んな要因があるんだけど、一番見落とされがちなのがパーソナリティ。最近はみなさん発達障害かも?って思って来られることが多いんですけどね。理想も高くて、色々周囲に気を遣って、でもギャップが感じてしんどいんでしょう」
演技性…自己愛性…うん、まぁ確かに言われてみれば、そう、そういう傾向は、ある…。パーソナリティ障害、かぁ…それは盲点だった。
自分でつけた○の数と集計結果を眺めながら、頭の中がぐるぐる回転していた。
「ただあなたはね、話していても好印象ですし、ここまで色々工夫して知性で補正されてこられたんでしょう。発達障害にせよパーソナリティ障害にせよ、その傾向はあっても、決して『障害』ってほどの状態ではないと思いますよ」
「はぁ…」
障害ってほどではない。うん、うん、まぁ、そうだろう。発達障害の診断基準は知っているし、今やったばかりのパーソナリティ障害チェックリストも、単なるスクリーニング用の簡易テストだ。「障害」と医学的に診断されるほどの不適応は来たしていないと言われれば、確かにまぁ、その程度なのかもしれない。
もともと「答え合わせ」ぐらいのつもりで来た。診断が出ようと出まいと、自分の傾向と対策は特に変わらない。それはわかっていたはずなんだけど、なんだか足場を踏み外したような感覚がする。ADHDとASDの強弱の見立てが外れていたからなのか、「パーソナリティ障害」カテゴリからの不意打ちを食らったからなのか、理由はよくわからない。
「ここに来るってことは、苦労はされてきたんでしょう。困ってるからここに来たんだと思いますよ。でもね、あなたはすでに自分の知性で十分に補正されてますから、『障害』って思わなくても良いんじゃないですかね」
「そうですかぁ。なるほど…。それでえっと、僕の診断名はどうなるんでしょうか。診断書に書かれる名前というか」
「診断書って、あなた、障害者手帳がほしいとか、休職したいとか、職場でこんな配慮がほしいとか、目的があればそれに応じて書きますけど、何に使います?」
「いや、なにか別に支援を受けたいとかそういうわけじゃないんですけど、発達障害ってグレーゾーンだの確定診断だの巷ではややこしいので、なんというか、自己紹介的に…」
「みなさんね、発達障害の確定診断がほしいって来られるんですけど、あなたもご存知の通りスペクトラムですから、確定診断なんてものはないんですよ。支援が必要なら書きますけど、必要あります?」
「いやー、そうですね、ないっすね…。たしかにスペクトラム、そうですよねぇ。いや、はい、大丈夫です。ええとまぁでも、パーソナリティの傾向とか、新しい発見があって面白かったです。ありがとうございました」
それこそ知性で補正しながら、ポジティブな収穫の確認と、感謝の意を言葉にして部屋を出た。
2回目の「発達障害診断チャレンジ」も、そんな感じで、わかりやすい「名付け」はもらえないまま終了した。
後日、いつものクリニックの通院日に、苦笑いしながら事の顛末を主治医の先生に報告した。
「うん、まぁ事前に言った通りの結果だったね(笑)」
「いやー、自分も仕事柄スペクトラムだっていつも言ってましたしね、そりゃそうだって感じなんですけど。自分のこととなると、名付けがほしいって思うことがあるんですよね。専門医の先生に言ってもらって諦めがついた感じがします。色んな凸凹があるけどどれもグレーゾーン、みたいな曖昧な立ち位置で自分はこれからも生きていくんだろうなって。まさかパーソナリティ傾向もあるとは思ってませんでしたよ(笑)」
「まぁまた自分の新しい一面が見えたのはよかったんじゃない。あと、僕もコンサータ出す資格は持ってるから、不注意・衝動性が自分で気になるなら、試しに少量から出すことできるけど?」
「え、先生も出せるんすか!」
…という感じで現在に至る。
自分の心身の不調や凸凹については、これまで別の記事でも色々と書いてきたが、改めて列挙してみるとこんな感じだ。
適応障害: 診断書が出たのち、療養・回復し、現在は診断域外、レクサプロ(SSRI)服薬継続
ADHD: 傾向あり、診断域外、コンサータ(メチルフェニデート)服薬継続
ASD: 傾向あり、診断域外
パーソナリティ障害: 演技性・自己愛性パーソナリティの傾向あり、診断域外
その他: 隠れ吃音(普段は目立たないが、たまに出る)
薬は飲んでいる。障害者手帳は持っていない。一般枠の雇用で就労していたが、現在は自営業で曖昧に食っている。
「障害」というほどではないにせよ、上記の凸凹もあって心身の波はやや大きく、「疲れやすい」身体と共に生きている。
「医療」のメガネでも「福祉」のメガネでも、どの障害にも当たらない。「診断基準」の少し外側、ふわふわした名前のない場所が僕の立ち位置になるのだろう。
「ここに来るってことは、苦労はされてきたんでしょう。困ってるからここに来たんだと思いますよ」
精神科の先生に言われた言葉をしばしば思い出す。
名付けがあろうとなかろうと、自分の凸凹自体は変わらない。取れる対策も大きくは変わらない。
じゃあどうして、2度も受診をしたのか。
それはやっぱり、「名前がない」ことの生きづらさがあったんだろう。
*
医師による診断が出るかどうか。障害者手帳(精神保健福祉手帳)を取得するどうか。障害者雇用枠での就職をするかどうか。
発達障害の「名付け」に付随する、医療・行政・労働市場におけるそれぞれの選択肢。もちろんこれらは必ずしも全て選ばなくても良い。また、診断と手帳に関しては望んだからといって取れるとは限らない。当然、発達障害の「当事者」一人ひとりがどんな「名前」を社会的に付与されているかはさまざまであるし、名付けに対する思い入れも人それぞれ違う。同じ人間でも、年月を重ねる中で距離感が変わっていく。
「大人になってから診断を受けて、ようやくバラバラのパーツがつながりはじめた。そんな感覚」
「やっぱり診断が、『名前』がほしい。スペクトラムだとかグレーゾーンだとか、そんなこと職場の人にはとても理解してもらえない」
「診断を受けてからしばらくは、なんでも特性に紐付けて自分を説明しようとしてたけど、今はもう、飽きちゃった。自分の一部でしかないなって」
「最初は障害者雇用枠で入ったんですけど、手帳の更新忘れちゃって(笑)そのまま一般枠になりましたが、職場はもうわかってくれてるんで」
「実はこないだ、手帳返納したんですよ。そのまま使ってても良いんだろうけど、なんとなく、自分の区切りとして」
身の回りの知人・友人たちの、「発達障害とわたし」にまつわる、色々なエピソードを聞かせてもらってきた。それぞれがそれぞれに苦労してきて、どうにかこうにか生き延びている。彼らと出会い、部分的に経験を共有し、ときに「あるあるネタ」で笑いながら、ときに愚痴を言いながら、同じ時代を生きていることを有り難く思う。と同時に、あいかわらず「名付け」が定まらない自分のふわふわした立ち位置をめんどくさく思う。
別にめちゃくちゃこだわってるわけでも、困ってるわけでもないんだけど、さ。
医師の診断も出て「当事者として」の語りを出来る友人がうらやましいという気持ちと
「自分はまぁ、診断なくて困ってるほどでもないからなぁ」と、周囲の理解が得られなくて悩んでいるグレーゾーン当事者への妙な遠慮と
(あまり好きな言葉ではないが)「支援者」側に片足突っ込んでいるゆえの、職業倫理的な自己抑制と
医師や行政の名付けがない中で「適当」に自己診断で名乗ることに抵抗する、自分のASD的特性と(これは皮肉)
そういういろんな立場や思考がないまぜになって、ずっと「足場がない」感じでふわふわと生きている。
…ここまで書いてきたが、特にスッキリする結論は出そうにない。ただ、この文章を書き始めるまでの4,5年で、またこの文章を逡巡しながらちょびちょびと書き進める中で、少しずつ、少しずつ、「まぁそんなもんだよな、仕方ないよな」という諦念が分厚くなってきていて、それはきっと悪いことではないのだろう。
そもそもがスペクトラムで、環境によって凸凹は強みとも弱みともなるのだから、結局、当事者も医師も、誰も「名乗る」ことへの許可・お墨付きを与えることなんてできないのが、「発達障害」というものだ。診断名や、典型例では説明できない多面的な自分の姿がたくさんあることに目を向けてからがむしろ本番で、「名付け」はスタート地点でしかない。
名前を見つけて、説明できる要素が増えていくこと。
説明しきれない部分が残るのを許容できるようになること。
原因がどうであれ、対策を取って楽になる場面が増えていくこと。
凸凹をならして平らにしようとするのではなく、凸凹のままでも生きていく方法や環境を見つけていくこと。
そういうことをこの4,5年の間に、いや、「発達障害」という概念に出合う前も含めたこの32年間の人生で、色々と身につけて頑張ってきたのが今の自分だ。どうにかこうにか生き延びてきた。そのことだけは、自分で肯定してやりたいと思う。
アラサーになって、これから段々と老いていく。それもまた、悪いことではない。
体力も落ちるから、無理せず過ごせる、自分に合った居場所だけが自ずと残っていくだろう。
「年取ったら定型発達も発達障害も一緒くたに、みんなポンコツになっていくから、発達凸凹なんか目立たなくなるよ!」と笑いながら励ましてくれた先輩もいた。
ここ数年は特にしんどかったが、振り返ってみればそもそも、「健康」であるという感覚を持てていた記憶がほとんどない。
しかし、歳を重ねるごとに、しんどいながらもしぶとく生き延びていくゾンビ的なレジリエンスは高まっているように思う。
きっとこれからも、名前のつかないマイルドな生きづらさはずっと抱えて生きていくのだろうけれど、これだけ予行演習を重ねたならば、さして恐れることでもないのかもしれない。
概念としてのHSPの危うさと、それが「求められている」ということと
HSP(とHSC)、数年前ぐらいからじわじわ話題になり、目に見える範囲でもHSPを自認する個人の語りが増えてきたように思うが、話題になったり収まったりまた話題になったりの小さなサイクルの中で、その都度、医学の観点からの危うさを指摘する声も出ているし、色々とうーんという概念ではあるのだが、とはいえHSPが一定の人たちに「求められている」という現象も踏まえて整理が必要だなぁと思う。
HSPは、まだ医学的な疾患概念として十分に精査・吟味されておらず、その状態で雑に流布することが、他の疾患の見落としや、それによって適切な治療や支援に繋がらなくリスクも踏まえると、僕もどちらかというと「診断」や「普及」に対しては批判的に見ている方だ。
一方で、HSPの「名付け」がしっくり来る、安心するという個人の主観的体験と語りが増えていることにも重要な意味があるのだろうし、その実態をうまく解きほぐしたり、橋渡ししたりできればなぁとも思う。
他の疾患カテゴリとの類似点・相違点など、現時点で分かっていること・分からないこと整理しつつ、HSPと自認する多様な個人の感覚と、名付けの「その後」の物語を並べていくと見えてくるものがありそうだ。概念として粗さがあるものの、一人ひとりの生活単位で見れば、HSPという「名付け」を取っ掛かりに、結果として別の疾患カテゴリにちゃんと接続して収まる人もいるだろうし、医学的診断はどうあれ、HSP自認のもと、しんどくならないように色々と生活の工夫をしていく余地もあるだろう。
概念整理はちゃんと丁寧にせなあかんよと思う人なので、雑なブームになっていくことにモヤる一方で、医師が専門家クラスタに籠もって内輪で批判してる間に、一般レベルでどんどん広がっていくことが、将来的に当事者・医療どちらにとってもデメリットをもたらす可能性もあるわけで。チェックリスト的なのをやったら自分に当てはまって「しっくりきた」「安心した」という主観的な体験はよく聞かれるし、それ自体はその人本人の足場としては良いんだろうなと思うけど、「自分もHSPだ」と思う人がたくさん出てくるというのは、それだけ概念として「粗い」ということなのかもしれないし。
専門家の取材やレビューと、HSP自認の当事者の体験を行き来しながら、この少し危うさのある概念との適度な付き合い方を見出していくような企画を、えーと、あれです、いま書いてる本が一段落したら考えようかな。
色々あった上で血液型診断的なレベルに収まってほどよく冷めていくのか、それとも他の精神疾患と比較してちゃんと整理されてもう少し限定的な新規カテゴリとして確立されていくのか、どうなるんだろうね。
寒い日も、雨の日も、あなたを「ようこそ!」と歓待したい
僕は雨の日は、けっこう好きなんだけど、しかし昨日今日の寒さは堪えたね。みなさんお元気ですか。いや元気じゃなくてもいいんです。ご自愛ください。
雨の日や寒い日はただでさえ外出が億劫になるもので、なおかつ、着込んだり傘開いたり閉じたり、いつもと違う動作、違う空間づかいを要求されるので、個々人の行動の変化が総体として、街全体の緩慢さ、どんよりさ、窮屈さなどなどを醸し出す。
(そういえば同僚がこんなことをつぶやいていた笑)
寒い日とか雨の日のときの、ダメージが大きい人、というのも実はけっこういる。
病気や障害がある人は、身体が思うように動かなくなったり抑うつ症状が出やすくなったり、駅が混むことで車いす等での移動がより困難になったりと、外出のハードルが更にグンと高くなる。
それから、病気や障害とまでいかなくとも、「低気圧で頭痛が起こりやすい」という人は、かなーりいるんじゃないだろうか。
イベントや勉強会を企画・主催する機会が多い人、飲食店などを経営する人、福祉サービスに従事する人などは、経験としても統計としても、「雨の日は来る人数が減る」ということは知っている。
(そしてもちろん、赤字ばっかりじゃ続けられないので、主催者側は、天候も織り込んで参加者数の見込みを立てたり修正したり、全体で吸収したり、事前決済にしたり、あれやこれや工夫はする)。
まぁ、中には「雨降ったしめんどくさいからいいや」と思ってドタキャンする人もいるんだろうし、連絡ない人とかもいるので、そういうのはやめてほしいなー…と、思いつつ、究極のところ、その日に来る/来ない(あるいは来られない)理由はわからないわけです。
行きたいんだけど、どうしても身体が動かなくて行けない、という人も中にはいるわけで。
「すっごく楽しみにしてたのに、身体の調子が悪くて…」と、当日申し訳無さそうに連絡をくださったり、申し込み時点で「ぜひ行きたいんですけど、体調の波が大きくて…」と事前に相談をしてくださる方とやり取りするにつけ、あぁこの人たちは、これまでも歯がゆい思いをしてきたんだろうな、と想像します。
結局のところお天道様にはかなわないし、私たち一人ひとりの「からだ」だって、思ったときに思う通りに動いてくれるとは限らない。
「場」を開く側としてできることは限られていますが…オンライン参加や資料のデータ共有など、会場に来られなくても参加できる代替手段を可能な用意しつつ、会場にたどり着いた人には、「ようこそ!よく来てくれたね!」と、とにかく全力で歓待したい。
いつもそう思います。
最後にひとつお知らせを…
来週、こんなイベントをやります。
11/27(水) LITALICO研究所OPEN LAB#5: 「からだ」はどこまで拡がるか - 未来のコミュニケーションを創造する
「LITALICO研究所 OPEN LAB」は、社会的マイノリティに関する「知」の共有と深化を目的とした、未来構想プログラムです。
7月から毎月1回、シリーズ講義でやっており、今回が5回目、テクノロジーによる身体の拡張がテーマです。
障害や病気のある当事者の方、経済的に困難な方や遠方におられる方も含め、あらゆる人にオープンな知のコミュニティとなるよう、以下のような情報保障や合理的配慮を、すべての講義において実施しています。
・講演会場での合理的配慮(ライブ文字起こしや休憩スペースの確保)
・経済的に困難な方へのスカラーシップ制度(各回公募・選抜)
・オンライン受講制度(通年受講チケットにて提供)
・レポート記事・レポート動画の無料公開(順次制作・公開)
・レポート記事の英文翻訳(順次制作・公開)
水曜日の天気がどうなるかわかりませんが、会場参加・オンライン受講ともに可能です。
クラウドファンディングでの先行予約・サポーター枠と別に、各回
Peatixでの一般チケット販売もしており、そちらはまだ少し空きがあるので、よかったらお越しくださいませ。会場でもオンラインでも、あなたのご参加嬉しいです。
吃ることがいいことだなんて思えなかった。「隠れ吃音」の僕が自分の体と仲良くなるまで
「君はちゃんと吃ることができるからいい」
そう言われたのはもう8年前のこと。当時は「はぁ…」と頷くしか返事ができなかったが、今でも折に触れて思い出す。
この言葉を僕に言ったのは、西きょうじさん。軽井沢に住んで、東京に通って予備校講師をしている、ちょっと変わった人だ。実際に授業を受けたことはないけれど、ひょんなことから紹介してもらい、以来ちょくちょくお酒を飲む仲になった。
西さんに言われたことは、「実感の伴わない知識まで、さも自分の考えかのように流暢に喋るよりは、下手くそでゆっくりでも、自分の実感から言葉を絞り出そうとできることの方がよっぽどいい」と、そういうニュアンスだったと思う。
だけど当時の僕は、むしろ「そのようにしか話せない」自分にひどく悩んでいた。流暢に、明瞭に話せる人になりたかった。スムーズに対人コミュニケーションを成立させられる人が羨ましかった。
頭の中と胸の内ではたくさんの思考と気持ちが渦巻くけど、それをうまく言葉に出来ないから吃る。結果、他人には伝わらない。「何が言いたいのか、お前の話はわかりにくい」と周りからよく言われていた。幼少期から青年期にかけて、そうしたコミュニケーション不全を多く経験してきたが、西さんとこの話をしたときは、それがより顕在化していた時期だった。
2011年。東日本大震災が起こった年であり、僕が大学を卒業して、大学院に行かずに石巻に移る選択をした年だ。
海と大地が大きく揺れた。それだけでなく、社会全体も、人の心も揺れていた。
地震と津波によってあっさりと崩され、飲み込まれていく街。圧倒的な自然の猛威は、大地の表面にしがみついて暮らす人間の無力さ、小ささを知らしめた。「安全神話」と地方への搾取構造によって成り立っていた電力供給。原発事故は、僕たちが生きる社会が虚構の上に成り立っていたという現実を突きつけた。
「前提」が揺さぶられ、未来が見えなくなったとき、自分はどうあるべきなのか。
それぞれに思うところはあっただろうが、大学同級生のほとんどは、就職や進学など、すでに決まっていた進路にそのまま進み、新しい生活をスタートした。3月11日から4月1日ー震災が起きてから卒業し、新年度が始まるまでわずか20日間という日数は、立ち止まって考えるにも、他の道を検討・選択するにも短すぎる時間だった。
僕はというと、彼らのように就職・進学するでもなく、休学・留年するでもない、「はざま」の時間を過ごしていた(別稿で書いた通り、当時海外大学院に合格していたが、渡航までに半年ほどの時間があった。結局、留学は延期し、ほどなくして石巻に移り住むことになる)。
行動するにしても、立ち止まるにしても、道を変えるにしても、何かを「選ぶ」ことは、他の可能性を一度断ち切るということだ。100点満点、望みが全て叶う選択などきっとないのだろう。だから、少なくとも選んだ道に後悔しないために、自分にとっての「正解」にするために日々を一生懸命生きるのだ。それはわかる、理屈としてはわかる。わかるんだけど、本当にそれだけなんだろうか…。
何かを選んだら、それを正解にするというシナリオしかないのだろうか。選びながらもためらう、前に進みながらも迷う、そういうあり方は、許されないのだろうか。
震災や原発事故をめぐる社会の言説、3.11以後にもどうあれ続いていく東京の日常。マクロからミクロ、そのどこにもフィットする感覚を持てなかった僕は、もともとの口下手の域を越えて、より一層吃るようになった。
うまく話せないならどうするか。書くしかない。発する言葉にしっくり来ていないから書く。伝えられていない感触が残るから書く。ブログに、Twitterに、とにかくそこにインターネットがあったから書いた。今ではそれが仕事になっているのだから皮肉だが、当時は誰かのためではなく、ただただ自分の生存のためだった。東京に残っていた頃も、石巻に移り住んでからも、日々誰かと関わりはし、しかしそこでは相変わらず口下手で、そんな日常の合間にほそぼそと、そしてぼそぼそと書いた。書くことが自分にとって楽しいわけではなかったし、それが何に繋がるのかもわからない。だから、吃ることが「いいことだ」なんて言ってもらっても、なかなか素直には喜べなかった。
*
西さんが言ってくれた言葉が腑に落ちて納得できたのは、それから1年ほど経った後、『自分の仕事をつくる』『かかわり方のまなび方』などの著者である西村佳哲さんによる3日間のワークショップに参加させてもらったときのことだ。西村さんは、さまざまな生き方、働き方をしている人たちへのインタビューをされてきた方だ。ワークショップは、インタビューの細かな手法や技術を学ぶのではなく、一人ひとりの「きくこと」に対する解像度を上げていこう、という試みだった。
そこで教わったことは3つ。「先回りしない」「相手についていく」「沈黙を恐れない」
その人が黙っていたり、言いあぐねているときは、待たなきゃいけない。言葉以前の「気持ち」が言葉になるまでの時間だから。お腹のなかに手を入れて、自分の気持ちにしっくりくる言葉を、「これかな?」「いいや、これかな?」と探り当てている時間だから。言葉が花開く瞬間を、聞き手が先回りして奪わないこと。そんな風なことを西村さんはおっしゃっていた。
この考え方を教わったとき、気持ちがずいぶんと楽になったのを覚えている。吃ることは、自分が自分らしい言葉を紡ぎ出すために”必要”な時間なんだということ。僕にとって書くことは、自分の中の気持ちを確かめる作業だったのだということ。その場その場ではうまく話せなくても、決して伝えることを諦めていたわけではなかったということ。
自分の中で、「話す」と「聞く」と「書く」が交差した瞬間だった。今、曲がりなりにも僕が仕事としてインタビューや執筆をできているのは、そうした経験があったからこそなのかもしれない。自分も、相手も、それぞれのペースで言葉を探している。上手に、早く話す必要はないのだ。
*
そこから更に数年。アメリカに渡り、日本に帰ってきて、26歳で今の会社に入り、いろんな仕事を経験する。クライアントとのミーティング、研修講師、会社説明会、チームマネジメントetc.人前で話すことも増え、自分でもそれを意識することもないまま、いつの間にかどもりは消えていた。
悩みながら、居場所を転々としながら、20代後半にしてようやく就職した分、凸凹な自分をうまく活かせる場所に、ようやく出会えたなという感覚がある。かかわる一人ひとりの多様性、困難に向き合う上での一人ひとりの痛みや悩みを大事にしてくれる組織だと思う。
とはいえ、スピード感はある。ビジョンを持って、明快に言うべきことを言う。その場その場で意思決定をして物事を前に進める。ためらいよりも決断が、思索よりも行動がどうしても大きな比重を占めやすくなる。
それでも仕事にやりがいはあるし、テーマも自分の関心と重なっている。忙しいけれど自分は適応できるだろう、適応できている。そう思っていたら、昨年にガタが来た。適応障害という診断。「適応できている」と思っていたら、身体は悲鳴をあげている。動機や息切れ、憂うつ感。やるべきこと、できること、やりたいことのバランス不全。やりたいことと外れているわけではないけれど、そのスピードや表現型は合っているのか。
そしてこのタイミングで、また「吃り」が出るようになった。上司や妻との会話で、うまく話せない。どもってしまう。違和感に気づいていながら考えないようにしてきたツケが利息付きでまとめて返ってきた。そんな夏だった。
身体を休める、薬を飲む、業務調整をする、そういうまっとうなケアの積み重ねで、適応障害の心身症状は次第に収まっていった。心や身体にのしかかっていたストレッサーを一つ一つ取り除いたり緩和したりして、回復していくための余白をつくる。そうすれば次第にエネルギーが戻ってくる。けれど、同じタイミングで再び現れた吃りについては、どうもそれらの症状とは性質が違うような気がした。休めば治るというものではなく、僕が他者と話し、関わることの根底に関わっているような感覚が拭えないでいた。
この吃りという現象をどう捉えて、自分はどう付き合っていくのか。そのヒントを得たのは、ちょうどこの時期に知り合った、『どもる体』著者の伊藤亜紗さんとの対談だ。意気投合したのは、”立て板に水”のように上手に話せているときのほうが違和感がある、ということだ。
“「私、大学の講義も3年で内容を全部変えているんですよ。”立て板に水”みたいに話せるようになってきちゃうと、学生に対して申し訳ない気持ちになるし、苦しい。新しいものにしてたどたどしくしゃべらないと伝わってない気がするんです。」
「仕事に慣れてくるとしゃべりが上手になってきますよね。同じことを繰り返し言っているようで…。単純に労力対効果でいったら効率良くなっているからいいことなはずなのに、逆に『このままでいいんだろうか』って思っちゃいます(笑)。」
「自分の輪郭を更新したくなるような感じですね。形成されてきたパターンや枠…ある種、自分の枷にもなっているものがずれたときが楽しいし、生きてる感がある。」
https://h-navi.jp/column/article/35027019 ”
生きてる感。
そうか、僕はどもっている自分が、たぶんちょっと、好きなのだな。生きてる感じがするから。
「君はちゃんと吃ることができるからいい」という西さんの言葉を思い出す。「言いあぐねているときは、”気持ち”が言葉になるまでの時間だから、待たなきゃいけない」という。西村さんのワークショップを思い出す。
しっくり来る言葉がうまく見つからず、吃ったり、たどたどしく話したりしている時間は、身体的には決して楽ではない。手近な仮置きの言葉に置き換えたほうが楽な場面もある。だけどそこでちょっとだけ踏ん張って、吃る体に自分を委ねてみる。もぞもぞと脱皮をするような感覚で言葉を探す。吃りながら訥々と言葉を発している時間は、自分が誠実でいられている感覚がする。
適応障害を発症したときに吃りも再発したのは、単なるストレス反応というより、「納得しきっていないことを話すことはできないぞ」という、身体からのメッセージだったのかもしれない。
吃りが多く出るときは、立ち止まって自分のあり方を見つめ直すチャンスである。ちょっと面倒で生きづらいかもしれないけれど、思考停止せず、誠実に生きてくためのシグナルとして、吃りはかけがえのない隣人なのだ。
*
それから1年。これを書いている今では体調もずいぶん回復し、吃りも日常的にはあまり出ない。
だけど時折、「隠れ吃音」と言っていいぐらいのささやかな吃りが表出することがある。いや、正確にはそういうときはむしろ積極的に吃りにいっているかもしれない。安心して吃れる相手と、そうでない人、あるいは場所・話題がある気がする。
流暢に話したほうが良い場面もある。それが悪いわけではないけれど、そればっかりだと息苦しくなる。吃りは「そろそろ息をしたいぞー」という体からのリクエストなのかもしれない。どもっているときのほうが身体的には息苦しいはずなのに、それが「息をする」ってことなのは、変な感じがするけれど。
鎧を着るときと脱ぐとき、鎧を脱いだ上で、さらにもぞもぞとぎこちなく脱皮するプロセスすらも見せられるとき。お互いにとって大事なテーマを、すぐに答えが出なくてもいいから、ゆっくりじっくり探りたいとき。そういうときは、吃るぐらいがきっとちょうど良い。
話すことは、共鳴することなのかもしれないな。
身の回りに何人かいる「隠れ吃音仲間」のかすかなシグナルは、周りの人はほとんど気づかない、僕たちだけのちょっとした秘密だ。
““どもりはあともどりではない。前進だ。”
武満徹『音、沈黙と測りあえるほどに』, 1971年, 新潮社”
「情の時代」を生きる私たちの痛みと祈り - あいちトリエンナーレ「表現の不自由展・その後」の再開と鑑賞を経て
台風が来る前にどうにか一度、と、予定をやりくりして行ってきた。
「あいちトリエンナーレ2019 情の時代 Taming Y/Our Passion」
10月11日(金)の朝に出て、15時過ぎには東京に戻る新幹線へ。滞在時間はわずか5時間弱、駆け足で回れたのは「表現の不自由展・その後」を含む愛知芸術文化センター(A会場)のみ。粗削りなのは承知の上で、鑑賞した作品群と、不自由展を中心としたトリエンナーレの周辺環境・事象について、来場者の一人として以下に書き残す。
目次
1. 再開した「表現の不自由展・その後」の様子
2. 「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」の中間報告について
3. 「情の時代」におけるキュレーションに求められるもの
4. 二分法を超える方法はないのか。「遠近を抱えて Part Ⅱ」に感じたこと
5. 断片情報で引き裂かれた感情。それを超えるのも「情」の力
1. 再開した「表現の不自由展・その後」の様子
10月8日に「表現の不自由展・その後」が再開、伴って展示を中止していた他のアーティストの作品も全て展示再開となり、あいちトリエンナーレ全体が全面再開となった。
不自由展をはじめ、一時中止を経て再開した作品には、「展示再開 NOW OPEN AGAIN」の札。
不自由展入り口には、中止時と再開時に際しての作家たちのステートメントが両方とも掲示されていた。また、展示中止中に会場を塞いでいた「壁」と、そこに貼られたメッセージ付きの付箋という新たな「作品」も場所を少し移動して、不自由展の会場外で自由に鑑賞できるようになっている。
再開した不自由展は、時間帯ごとに人数制限を設けて抽選を行う形での鑑賞受付の形を取っている。以下のような流れだった。
各時間帯に先立って抽選受付
↓
抽選結果発表(会場&WEB掲示)
↓
鑑賞開始の約30分前に集合
↓
同意書の記入・提出と手荷物の預け入れ
↓
会場前のスペースに追加掲示された「表現の自由」に関する基礎知識解説資料、および「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」の中間報告の中心的な部分を抜粋した紙資料を読みながらの待機時間
↓
スタッフによるアナウンス(映像作品以外は撮影可・SNS当シェアは禁止、映像作品は撮影不可といった、同意書記載事項の口頭再確認)
↓
警備品による身体チェックののち、入場
↓
会場内の掲示作品を自由に鑑賞
↓
最後の20分で、「遠近を抱えて・Part Ⅱ」を鑑賞
(座布団を敷いてみんなで一緒に観るかたち)
参加した回は10月11日(金)の11時台の枠。鑑賞プロセスは非常に落ち着いた雰囲気で進み、トラブルは一切発生しなかった。
参加者は、少し緊張しているような真剣な面持ちで待機時間を過ごしていた。会場に入ったあとは、限られた時間の中で作品を見つめ、触れ、また写真を撮る。
少女像の隣に座ってスタッフに写真を撮ってもらう人も多くいた。肩を抱く人、頬を見つめる人、もたれかかる人。
私は、少女像と同じ前方を直視しながら、左手を少女像の手に添えて撮影した。
2. 「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」の中間報告について
会場で不自由展の鑑賞前に中心部分の抜粋版が印刷配布された、「あいちトリエンナーレのあり方検証委員会」の中間報告はこちらのサイトからも確認することができる。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/bunka/triennale-interimreport.html
以下に簡単に、私が重要だと感じた論点を要約紹介したい。
■展示の一時中止は「安全上の理由」
8月1日〜3日は展示室内は概ね冷静だったが、見ていない人がSNS上の断片画像を見て抗議を越えた脅迫等の犯罪行為や組織的な電凸行為に及び、以下のような被害が発生した。
・電話、FAX、メール、合計10,379件による業務妨害、精神的苦痛
・学校や福祉視閲の脅迫まであり、逮捕者も2名
■芸術祭全体のテーマ「情の時代」への評価、不自由展も企画自体は妥当という評価
・9月22日時点、入場者数は約43万人と、前回を約2割上回る勢い
・「情の時代」というテーマの妥当性と先進性、アートとジャーナリズムの融合に対する各方面からの高い評価
・不自由展も、企画それ自体は趣旨に沿ったものであり、妥当だったという評価
■不自由展まわりで問題とされたのは、趣旨を適切に伝えるためのキュレーションの欠陥
上述の通り、企画それ自体に問題はなく、特に批判の的となった3つの作品(キム・ソギョン/キム・ウンソン「平和の少女像」、大浦信行「遠近を抱えてPartII」、中垣克久「時代の肖像ー絶滅危惧種idiot JAPONICA 円墳ー」)も作者の制作意図に照らすと展示すること自体に問題はない作品だったという結論。
しかしながら、鑑賞者にたいしてその趣旨を適切に伝えキュレーションが出来ていたとは言い難いという評価。
・作品選定に際し、過去に美術館等で展示を拒まれたもの以外に新作も混じり、「表現の不自由展」というコンセプトからのズレ
・政治性を強く帯びた作品が多かったので、「政治プロパガンダ」という印象を与えた
・作品数に対してそもそも会場が狭い、入り口に映像作品「遠近を抱えてPartII」を配置、資料コーナーが奥になる、など空間配置上の問題
・断片がネット上に拡散されることへのリスク対応が不十分(徹底して禁止するという仕組みが講じられなかった)
・予算と時間の不足から、エデュケーションプログラムやガイドツアー等を実施できなかった
(憲法や民主主義の原則 基礎知識を必要とする。「禁止されたことのある作品」を一般来場者がただ観る、だけでは理解しにくい)
・芸術監督とキュレーションチームのチームワーク、出展作家である「表現の不自由展 実行委員会」とのコミュニケーションなど、組織ガバナンス上の問題
■作品は憲法上の表現の自由を超えるものではなく、法令違反でもない、という立場は堅持
批判の的となった3つの作品を含め、「表現の不自由展・その後」は法令違反ではなく、憲法で明示された表現の自由の下で最大限尊重されるべき、という立場は堅持されていた。
政治的な色彩が強い作品であっても、アートの専門家の自律的判断を尊重すべきであり、公金を支出することは認められるという結論。また公金支出をもって、自治体がその作品の政治的メッセージを支持したということにはならない。
憲法第21条第1項は表現の自由を保障し、第2項は検閲を禁止している。表現の自由は憲法の保障する基本的人権の中でも重要なものであり、最大限尊重されるべきものである。
表現の自由も絶対的なものではなく、「公共の福祉」に反する場合には制限できることが13条で定められている。しかし、重要な権利であるゆえに、曖昧な理由での制限はしてはならない。
一定範囲の人々が不快に感じたとか、単に漠然と公共の福祉に反すると「思う」ということでは制限できない。表現の自由が制限される際には、マイノリティに向けたヘイトスピーチの規制など、別途「法令上の根拠」が必要。そして、今回の展示で言えば、昭和天皇の写真を焼いてはならないという法令はない。
昭和天皇は故人であり、また公人中の公人であるため表現の対象となることは当然ありうる。さらに、「遠近を抱えてPartII」の作者である大浦信行氏の制作・展示の趣旨からしても侮辱には当たらないとの結論(従軍した日本人の少女の中にある「内なる天皇」を燃やすことで「昇華」させていく、「祈り」といっても良い行為と大浦氏は説明)。
よって、「表現の不自由展・その後」全体も、「遠近を抱えてPartII」をはじめとする個々の作品も、違法にはあたらず、公共の福祉には反しない。同展示の「表現の自由」は尊重されるべきという結論。
——
以上が、中間報告から私が重要と考える、また本記事を通してインターネット上の読者・鑑賞者にシェアすべきと考えた論点である。
・展示中止は安全上の理由であり、作品自体の問題ではない
・不自由展および収録作品の表現の自由は、いずれも守られるべきである
・一方、安全上の脅威をもたらすほど人々の感情がかき乱され、作品への賛否で人々が分断される事態になったキュレーション上の欠陥が指摘される
この3つをそれぞれに分けて考えることが重要だと思う。
3. 「情の時代」におけるキュレーションに求められるもの
「表現の不自由展・その後」は、上述の3作品に対して、主に右派、保守とされる人々からの反発があったと理解している。日韓の従軍慰安婦を巡る日韓関係と、「遠近を抱えてPartII」は昭和天皇の肖像との結びつきから、反発的感情を招くだけのインパクトがあった作品だと思う。
しかしながら、「表現の不自由展・その後」に展示された作品全てが、右派、保守とされる人々にとって気に入らない表現だったかというと、私はそうは思わない。
たとえば、横尾忠則「暗黒舞踏派ガルメラ商会」は、朝日のモチーフが旧日本軍の旭日旗を思わせる軍国主義的なものであるということで、在米韓国系市民団体「日本戦犯旗退出市民の会」からの抗議を受けた作品だ。
※ 横尾忠則 表現の不自由展・その後 リンク切れ ※
これは、右派・保守と呼ばれる人たちが怒るべき出来事で、「表現の不自由展・その後」において展示されたことは喜ばしいことではないかと思うのだが、そうしたことはほとんど話題に上がらない。
(モチーフはさておき、作品自体の政治的メッセージは薄いこと、一枚のポスター作品であり、銅像や映像よりネット空間における「拡散映え」しにくいという要素はあると思うが)
「表現の不自由展・その後」内の個別の作品に対する評価・言及量のギャップが事例となったように、インターネットでは人々の強い感情を喚起しやすい一部のコンテンツだけが拡散されやすく、一連の企画やプログラム全体の趣旨が適切に伝わらないことがままある。まさに「情の時代」と言えるだろう。
インターネットは、私たち一人ひとりが発信の担い手となれる、情報流通の「民主化」をもたらした。私自身もその恩恵に大きく預かっている一人だ。
しかし、今回の不自由展をめぐるインターネット上の言説と人々の分断を見るに、オープン・フリー・フラットなインターネット的コミュニケーションがもたらす負の側面とも改めて向き合わなければならないように思う。
コンテクスト(文脈)がちぎられ、伝えるべき情報”群”のうち一部だけが先鋭化して拡散する。そのことが分断の連鎖を生む。
断片であっても「情報は多ければ多いほどいい」、そんな思想が果たして本当に良いのだろうか、と考えさせられる。
今回の不自由展再開にあたっては、先の章で紹介した通り、鑑賞方法の改善や情報流通の制限など、相当な注意を払ってのキュレーションの再設計がなされていた。
今日ではアートの分野に限らず(ビジネス・メディア・カルチャーなど)、イベントにおいて撮影・拡散を自由にしていく傾向は強くなっている。
しかし、扱うテーマによっては、いたずらに分断を促進しないための、セミクローズドな情報流通設計は、オプションとして検討する必要があるだろう。
(もちろん、それが行き過ぎると、今回の不自由展が投げかけた「検閲」の問題に繋がっていくことには注意しなければならない…)
・適切な鑑賞をしやすい空間・時間デザイン
- 人数・時間を限定し、落ち着いて観られるようにする
- 作品の理解・思考が深まりやすい導線設計
・事前事後のエデュケーション機会とセットにする
- 鑑賞前の資料閲覧やプログラム受講
- 鑑賞後の対話的なワークショップ
・二次的情報流通の量・性質をコントロールする
- SNS等のシェアを禁止ないし一部制限する
- 投稿・流通フォーマットの指定など、趣旨の伝達を担保した上で多様な言論が生まれるような「ナッジ」の工夫
などなど… 「情の時代」においては、作品を直接鑑賞する人たちへの情報提供だけでなく、二次的な鑑賞者への情報の流通や影響についても視野に入れたキュレーションが求められるのではないだろうか。
(もちろん、私のような素人が言うまでもなく、すでに多くのプロが意識・工夫されているところだとは思う。ただ今回の不自由展への反応のように、政治的な色彩を帯びる作品については、今まで以上に大きくリスクを見積もって対応せねばならない時代になってきているのだろう)
4. 二分法を超える方法はないのか。「遠近を抱えて Part Ⅱ」に感じたこと
しかし、と、ここでまた考える。この問題の根底にあるものはなんだろうか。
キュレーションの工夫で「減災」はできるだろうが、それでも炎上リスクは「ゼロ」にはならない。
そもそもアートは、グレーでモザイクなこの世界に存在するありとあらゆるものを取り上げようとする運動だ。
世界に、人に「問い」を投げかけるアート作品は、時に人の感情を刺激し、私たちが何気なく立つ日常を揺さぶってくる。
反発も問題も起こらない、きれいな「シロ」の作品ばかりでは決してない。
また作品は、「対話」の媒体でもある。作り手やキュレーター側が想像もしていなかった多様な解釈と発見が、鑑賞者によって掘り起こされることがある。
作り手側が想定する”適切な”鑑賞方法はあったとしても、作品からどんなメッセージをどう受け取るかについて、たったひとつの”正解”があるわけではない。
不自由展においても、時計の針を巻き戻して様々な対策を講じ、現在のような炎上や分断を防ぐことができたとして、それでもやはり、個々人の心理的体験としては、反感や反発を覚える人たちは出てくるだろう。
一人ひとりの思想や感情の多様さを前提に、作品に対する反発も覚悟の上で、橋をどうかけるか。
今回、不自由展に抗議をした人たちが、断片だけでなく「作品」と落ち着いて対話をするきっかけ、文脈、環境、関係性をどうやってつくるのか。
右派と左派に分かれるのではなく、「わたし」と「あなた」の関係において、作品鑑賞後の意見・感情の相違をどう分かち合うのか。
こちらの方がよっぽど難しい問題だ。
もちろん安全上の脅威、脅迫行為や犯罪行為に対しては断固として戦わなければならない。多様な言論も表現の自由が最大限尊重された上でこそだ。
今回のあいちトリエンナーレを見るに、実際問題、ものすごく難易度が高い。仮に私がキュレーターになったとしたら、うまくやれる自信はない。
だけど、鑑賞者の一人として、情報発信を生業とする者として、市民の一人として、敵・味方の二分法を超える方法を考えたい。それがあいちトリエンナーレから受け取った自分の宿題だと思う。
ここから先は、いち鑑賞者の、願望混じりの感想に過ぎない。
だが、騒動の象徴となった作品のひとつ、「遠近を抱えてPartII」にこそ、実は分断を超えるポテンシャルが秘められていたように思えてならない。
昭和天皇の肖像を燃やすというところだけがフィーチャーされたが、映像のもととなったコラージュ作品「遠近を抱えて」には、天皇制批判や昭和天皇侮辱の意図は一切ない。むしろ大浦は、そのコラージュを「自分自身の肖像画」と述べている。外へ外へ拡散していく自分自身のイマジネーションと、内へ内へと修練していく天皇のイマジネーション、そのせめぎ合いを表現したという。
「遠近を抱えてPartII」に反発を覚えた右派・保守と呼ばれる人たちも、作者の大浦信行も、作中に出てくる従軍看護婦の少女も、鑑賞者である私も、共通して「天皇」を内側に抱えている。日本人として、日本に生きることで私たちは、「天皇」という引力に多かれ少なかれ影響を受けている。一方で、一人ひとりの「わたし」は「日本人」として簡単にひとくくりにできない多様性を持っており、さまざまな個性が外側に広がっていく。
「遠近を抱えてPartII」の映像中には、コラージュを燃やす場面だけでなく、先の大戦で戦死した軍人たちを弔うアナウンスや、従軍看護婦としてインパールに向かう前、母に別れを告げる少女の手紙の朗読(彼女は「靖国でお待ちしています」と言う)といったシーンが含まれている。
ノスタルジックに信奉しようと、距離を開けようと、私たちの中にある消しようのない「日本人性」。それを否定するでも肯定するでもなく、葛藤のままに「昇華」する。ある種の祈りとして、写真を燃やす行為があった。私はそう受け取った。
私は、政治的には比較的にリベラルな立ち位置の人間だと思う。ものすごく信心深い方でもない。「日本すごい」幻想に浸ってもいない。だけど同時に、この土地に生まれ育った日本人としての歴史とアイデンティティも、私の中のかけがえのない一部であると思う。
昭和天皇の肖像を焼くという行為に反応して表現の不自由展に怒った人たちに対して、それは断片的理解に過ぎないとか、表現の自由を理解してないと批判することはたやすい。だけど、仮に断片的な受け取り方であったとしても、本人が感じた「感情」ー怒りや痛みは、尊重すべきだと思う。
そしてその痛みは、僕の中にもあるかもしれないのだ。
台風も来ている。会期ももう終わる。今回はその機会がないけれど、彼らと共に、その共通の「痛み」を出発点に対話ができたなら、と願う。
そのための方法を、別の機会で、場面で、探していきたいと思う。
5. 断片情報で引き裂かれた感情。それを超えるのも「情」の力
最後に、愛知芸術文化センター(A会場)で鑑賞したその他の作品も一部紹介しながら、今回のあいちトリエンナーレのテーマ「情の時代」について述べて結びとしたい。
今人類が直面している問題の原因は「情」(不安な感情やそれを煽る情報)にあるが、それを打ち破ることができるのもまた「情」(なさけ、思いやり)である。「アート」の語源にはラテン語の「アルス」やギリシア語の「テクネー」がある。この言葉は、かつて「古典に基づいた教養や作法を駆使する技芸」一般を指していたのだ。われわれは、「情」によって「情」を飼いならす「技」を身に付けなければならない。それこそが本来の「アート」ではないのか。
芸術監督の津田大介氏のステートメントに応えるように、あいちトリエンナーレには、「情」によって「情」を飼いならす「技」を示す数々の作品が集まっていた。
■タニア・ブルゲラ「43126」
展示室に入る前にスタンプで押される5桁の数字。2019年に国外へ無事に脱出した難民の数と、国外脱出が果たせずに亡くなった難民の数の合計人数。
部屋の中の壁にも同様の数字が刻印されており、室内ではメンソールが充満している。
地球規模の問題に関する数字を見せられても感情を揺さぶられない人々を、無理やり泣かせるために設計された、このメンソール部屋。
乱暴と言えば乱暴だが、人は感情を揺さぶられて泣くだけでなく、泣いたことそれ自体で感情が揺さぶられもする、不思議な生き物なのだ。きっかけはメンソールでも、涙を流しながらその数字を再び見てみると、受け取り方が変わるかもしれない。
「なさけ」を喚起する技術が、人の想像力を拡張する可能性を示している。
■ ジェームズ・ブライドル「継ぎ目のない移行」
ジェームズ・ブライドル(A18c) | あいちトリエンナーレ2019
英国の入国審査、収容、国外退去の3つの管轄区域について、計画書や衛星写真などを手に入れ、中に足を踏み入れた人へのインタビューを通じて再現した3Dアニメーション映像。この建物を通過する人々は強制的に国外へ移送され、送還のために使用している拘置施設、法廷、飛行機を撮影することは違法となっている。
これだけインターネットが世界中を覆い尽くしていても、一部の人以外は決して訪れることがない、「不可視」の領域がこの地球上には存在する。そしてそこで非人道的な捜査が行われている…。
「見えない」ものを見ようとすること。ジャーナリストによる粘り強い調査と3Dアニメーションという情報技術が、見えるものだけに捉えられた私たちの想像力を拡張させてくれる。
■ヘザー・デューイ=ハグボーグ「Stranger Visions」「Invisible」
ヘザー・デューイ=ハグボーグ(A13) | あいちトリエンナーレ2019
■村山悟郎「Decoy-walking」
作家がニューヨーク市の街頭で収集したDNAサンプルに基づいて3Dプリントされた肖像のシリーズ「Stranger Visions」。公共の場所にあるDNAを消去し、またノイズで覆い隠す2つのスプレー製品からなる「Invisible」。近い将来オンラインで個人情報を収集するのと同じくらい、遺伝子情報を収集することが一般的になるだろうという。技術的にますます「監視社会」が容易になっていくなかで、政府が主体となる狭義の「検閲」がなかったとしても、人々は自己表現を萎縮するかもしれない。そんな未来における表現の自由とはなんだろうか。
この問いに応答するかのような試みが、村山悟郎の作品だ。
表情と手を駆使したさまざまな”変顔”が、コンピュータによって「顔認識」されるかどうか。パターンから逸脱するさまざまな歩き方が「歩容認証」技術によって捉えられるかどうか。
パターンを認識するためのテクノロジーと、これらに対峙し、駆け引きをする人間の存在を示したこれらのインスタレーションは、折しも「マスク禁止令」に対して、髪の毛で顔を隠したり、ジョーカーのメイクを施したり、プロジェクションマッピングで他人の顔を映し出したりという抵抗を繰り広げている香港の市民たちのクリエイティビティとリンクする。
情報技術を時に利用し、時に欺きながら、私たちは機械と「共存」し、表現をする。
■dividual inc.「ラストワーズ/タイプトレース」
dividual inc.(A14) | あいちトリエンナーレ2019
整然と並んだ24枚のモニターに、インターネットを通じて集まってきた「10分遺言」が次々と表示される。入力の際に次の言葉を入れるまでの時間に応じて文字のサイズが変化するソフト「TypeTrace」によって、逡巡や勢いといった書き手の「息遣い」が生々しく表出される。
ある人は恋人に、ある人は家族に、ある人はSNSのフォロワーに、ある人はペットに、ある人はパソコンに。
反省を、後悔を、言付けを、思い思いに綴っていく。
その内容もプロセスもさまざまだが、遺言の後半には多くの人たちが「感謝」を述べる傾向があったと、作者のドミニク・チェン氏から別の機会で聞いたことがある。
誰しもが逃れられない「死」に向かって生きているという点で、人は平等だ。
遺言を書くという経験。平等な「死」を想うこと。
思想や文化、社会的立場の相違を越えた「祈り」の環をつなぐ鍵がここにあるのかもしれない。
わたしが「男性」であるという、逃れられない事実に対して
「男性」であることと「女性」であること。それに伴って生まれる差異を、比較的意識しないで済む生き方や所属をしてきたと思う。お互いが平等で対等な個人としてかかわることを前提とする、比較的「リベラル」な文化・環境に身を置いてきた。
そんな自分も、やはり男性であり、そしてそれが社会的には「マジョリティ」である。そのことを強烈に意識させられた本が、『82年生まれ、キム・ジヨン』(著: チョ・ナムジュ, 訳: 斎藤真理子, 筑摩書房)だ。
1982年生まれの33歳、夫と1歳の娘の3人で暮らす女性、キム・ジヨンが、ある日突然母親や同級生が憑依したかのような奇妙な言動を取るようになったことをきっかけに精神科を受診。男性の精神科医による症例報告というフォーマットで、彼女が生まれてから2016年現在に至るまでの人生が語られる。韓国で「社会現象」と呼ばれるまでの大ベストセラーとなったのち、日本でも2018年に翻訳版が発売された。
家や学校での男の子との扱いの差、就職先・給与・仕事の配属等々の男女の待遇差、飲み会でのセクハラ、そしてストーカーや盗撮といった性暴力。キム・ジヨンという一人の女性の人生を通して淡々と描かれるのは、現代社会を生きる女性が直面するさまざまな性差別である。
キム・ジヨン氏の母〜祖母の世代における伝統的な男尊女卑的価値観とその残滓、男性のみに課せられる徴兵制度、IMF危機など、小説の舞台となる韓国特有の文化的・政治的・経済的背景もある。だけど、それらを差し引いてもなお、これを読んだ女性たちが国を超えて「私たちの物語」として受け取り、何かを語りたくなるだけの強さを持った本だと思う。
とある読書会でこの本を題材に語ることになった。参加者の年齢に幅はあったけれど、概ねキム・ジヨン氏(小説内で33歳)のプラスマイナス5歳ぐらいには収まっていたと思う。女性メンバーたちの最初の反応として、『キム・ジヨン』で描かれているようなことは、まぁ多かれ少なかれ「あるある」だよねというトーンで共通していた。
多様だったのは、その「あるある」に対する個々人の感じ方、対処の仕方だ。
明に暗に、女性差別的な対応をされたとき、それをどれだけ鋭敏に感じ取るか。その上で、真っ直ぐ怒るのか、サラリと受け流すのか、静かに距離を空けるのか。学校や就職先、所属コミュニティの文化によって、「女性であること」がどの程度不利になったのか。その上で生存戦略として、自分自身の身の置き方をどのように決めたのか。
自身の経験の語り方、語るときの声のトーンや表情。そこに彼女たちが、僕の経験していない「痛み」をどう受け止めて処理してきたのか(あるいは処理しきれなかったのか)があらわれているように感じた。
その日の読書会は、選書もあってか女性参加者の方がはるかに多かったが、僕も含めて男性参加者もいた。話しやすい雰囲気と関係性が非常によく担保された場なのだが、それでもこのときは、自分から何かを語ることが、とても難しく感じた。
それは、自分が「男性である」ことの潜在的な加害者性を意識せざるを得なかったからだと思う。
本を読んでいてもっとも苦しかったのは、高校時代のキム・ジヨン氏が、予備校からの帰りのバスで味わった恐怖の場面だ。後ろの席の男子生徒が、「いつもニコニコしてプリントを渡してきた」というだけで自分に気があると勘違いし、キム・ジヨン氏の帰り道をずっとつけてきて、ついには降りた停留所で立ちはだかったという場面だ。危うく襲われそうなところで、同じバスに乗っていた女性が駆けつけてきたため、男子生徒は逃げていったが、その一件がきっかけでキム・ジヨン氏は予備校をやめ、しばらく笑えなくなり、身の回りの男性がみんな怖くなった。
読んだとき、普段は意識せずに過ごすことができていた自分のマジョリティ性を突きつけられたようで、しばし頭がクラクラした。
この男子生徒と自分は同じカテゴリーに属している。1対1になったとき、女性を恐怖に陥れ、あまつさえ押さえつけることのできる身体や力の大きさを持った「男」なのだ。
ひどいやつだと思う。同じ男性として許せないとも思う。実際に、全ての男性がそんなことをしているわけではない(”Not all men”)。そりゃ当たり前だ。しかし、いくら言い聞かせたとしても、自分が潜在的に「そうできる」力を持っているという事実は変わらない。
検査や指導と称して、不必要に女子生徒の身体に触れる高校教師。会食の場でキム・ジヨンを隣に座らせ、セクハラ発言を繰り返して下品に笑う取引先の部長。作中では他にも、キム・ジヨン氏や彼女の友人たちが受けてきたさまざまな性差別・セクハラ事案が描かれる。フィクションではない現実で、同じような経験をしてきている女性がたくさんいることも知っている。身近な友人たちから直接に聞いたこともある。読めば読むほど、自分が同じ「男」であることに、暗澹たる気持ちになる。
しかし…我が身を振り返って、これまで自分が一切の性差別や抑圧に加担していなかったと言えるだろうか。多かれ少なかれ自分の中にもある「男の子」性が、無邪気に誰かを傷つけたことはなかったと言えるのか。小学校での隣の席の女子へのいたずら、思春期の男子たちの集まりで語られる「誰がいい」「あいつは無いわ」といった品定め。「悪気はなかった」「ちょっと口が滑っただけ」「幼かった。今はそんなことしない」と言い訳するのはたやすいが、そうした小さな鈍感さの積み重ねが、誰かを傷つけていなかったと言えるだろうか。
「ひどいこと」をする男性たちへの嫌悪感。彼らと同じカテゴリーに属する自分の、潜在的な加害性への恐れ。そして実際に人を傷つけてきたに違いないという現実。
「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい」
女性差別の問題に対して、自分が「どの口で」何を語ることができるのか。生まれ持った自分の身体が偶然に男性であるゆえに、逃れ得ない「マジョリティ」性を前に、口ごもるしかなかった。
*
「だけど、私たちも石を投げてきたかもしれない」
参加者の女性のひとりがそう発言した。
「被害者」としての経験を語る一方で 自分自分が女性差別や男性差別をしている可能性はないのか。マイノリティの立場であるからこそ、そのことに対する意識や想像が難しい部分もあるという。
「男性」と「女性」というマクロな切り分け方をしたときに、確かに性別格差・性差別は存在する。しかし、同じ「男性」「女性」集団の中にも世代・教育レベル・経済レベル・地域性などによって支配的な価値観や選択傾向を持ったさまざまなクラスター(小集団)が存在し、当然、個人レベルで言えばもっと多様な価値観と選択パターンが存在する。そして、自分が属するクラスターにおいてマイノリティとなるような選択をした人は、周囲からのプレッシャーを受けたり、自分自身の選択に自信を持ちづらかったりするのだ。
たとえば「男性」会社員が長期の育休を取る、または専業主夫になるという選択は、男女の機会均等を求めるリベラルなクラスターの中では称賛・受容されやすいかもしれないが、社会全体で見れば少数派となる。大半の日本企業では、まだまだ「男性はよく働き、会社で活躍し、出世し、稼いでいく」という暗黙の前提があり、育休を取ることが出世レース上で不利に働いたり、専業主夫になる男性が下に見られるといったことはあるだろう。「女性」の中でも、高学歴でキャリア志向の強い女性が多いクラスターの中では、出産を機に仕事を辞める「寿退社」を選ぶことに躊躇いや劣等感が生じやすいかもしれない。
僕が参加した読書会も男女共に高学歴の参加者が比較的多かったが、出産を機に仕事を辞めたという人が何人かいた。本当は両立したかったが泣く泣く諦めたという人もいれば、もともとそう望んでいたと語る人もいる。産休・育休は可能な限りギリギリまで短くし、すぐに仕事に復帰したという人、もともと仕事も楽しかったけれど、いざ生まれてみると育児が楽しくて、少し考えたけどあまり迷わずに退職を選んだという人、それほど急いではいないけれど、いずれは、また働きたいなぁとは思っている、という人。グラデーションの中には他にもさまざまな選択肢が散らばっている。
男女の機会均等、とりわけ女性の就業機会拡大が、その実態やスピードに課題はあれど、大きな傾向としては進展していく。経済的な理由も相まって「夫婦共働き」がスタンダードになっていく。そうした中でも、個人レベルでは当然、専業主夫/主婦になりたい、あるいはそれを選ぶ人たちはいるはずだ。しかし、高学歴・キャリア志向が強いクラスターであればあるほど、その選択はマイノリティとなり、暗にヒエラルキーの「下」として見られる傾向が強くなる。
参加していたとある女性が「私はもともと専業主婦になりたいと思ってそれを選択しただけなのに、どうしてそれを”降りる”とか”ドロップアウト”だとか言われなければいけないのか」と憤りを表明していたのが印象的だった。
本来なら個々人が自由に、フラットに社会的な役割を選択し、また行き来して良いはずだ。しかし男性である、女性であるという生物学的な差異と、歴史的に形成され、また変化していく「男女」にまつわる支配的な価値観や選択の傾向が、一回きりの人生である「わたし」の人生に否応なしに影響を及ぼしてくる。特に結婚・出産・育児というライフステージの節目においては、そもそも別種類であるはずの「あなたとわたし」の問題と「男女」の問題が同一視されやすい。
生まれた性別と時代に紐づく、逃れ得ないマジョリティ性・マイノリティ性に対して、一人ひとりの「わたし」はどう向き合えば良いのだろう。
*
読書会のあと、思い出したことがある。
自分より世代が上で、もっと女性差別が強かった時代に自分の力でキャリアを切り開いてきた、そんな「強い女性」たちに、人生のいくつかのタイミングで、出会い、かかわり、教えを受けるなどした。ほとんどの方とは今はもう会っていないし、連絡を取ることもない。記憶も少しずつ薄れ、混ざり、変容もしているだろう。ぼんやりと、ただぼんやりと、いくつかの表情と言葉を帰り道に思い出した。
「ノーブレス・オブリージュ(高貴なる義務)」ということをよく言われた。恵まれた立場にあるものは、その能力やリソースを、恵まれない立場にあるものも含めた社会全体に奉仕するために使うべきだという考えだ。当時の僕は、「ノーブレス」という形容詞への違和感や、それを語る人たちの「お説教」的物言いへの嫌悪感や、モラトリアム真っ只中で自分が生きるのに必死なのにそんな義務を勝手に課されたくないよという逃避から、その言葉を受け取ることを拒んでいた。
少しは大人になって、自分より若い世代と仕事等で関わることが増えた今も、僕はこの発想には与しない。その考え方が生まれた背景や社会構造に一定の理解はするものの、複雑で多様な人間を、能力や立場の強弱二分することの限界、「強い」側からの視点だけで社会を捉え、変革しようとすることの欺瞞を感じるからだ。
けれども、個人的な主義主張・好き嫌いを脇に置いて、その言葉を僕が受け入れにくかった理由は別のところにあったのだろう。
つまるところそれは、「男性」と「女性」の問題である。この社会で男性として生きること、女性として生きることで背負う構造の問題である。年齢・経験・キャリアの差、そして「教える」「教わる」という師弟関係において、彼女たちの方が僕より「強い」立場にあったからこそ、「男女」の問題が一層際立った。表立ってそこに触れることはほとんどなかったと思う。あくまで「わたし」と「あなた」の会話をしていたはずだ。だけど当時の僕は、無意識下にプレッシャーを感じていた。
女性が働く上で直面するさまざまな見えない障壁の喩えとして「ガラスの天井」という言葉がある。就活や職業選択、業務上のやり取り、配属や昇進等のさまざまな場面において、時に露骨に、時にやんわりと示される「女性であること」による差別。統計的には、従業員や、役員構成や、育休取得率の男女間ギャップといったもので可視化される。現在でもまだまだ残っていると言えるだろう。
僕が思い起こす女性たちはいずれも、ガラスの天井が今よりもっと分厚かった時代に戦ってきた人たちだ。大学入学時も就職時も、まわりはほとんど男性だったと、折に触れてエピソードも聞いた。男性社会で勝ち抜いていくことは事実大変だったと思うし、彼女たちのような先達一人ひとりの戦いが少しずつ女性を取り巻く環境を変えてきた、その歴史と痛みを思うと頭が下がる。
「ノーブレス・オブリージュ」とはきっと、そんな時代を生き抜いてきた彼女たちの矜持を表す言葉だったのだろう。自分たちが身を持ってその過酷さを体験してきたからこそ、下の世代に伝えたいこと、期待することが山程ある。
そんな彼女たちからすると当時の僕は、見ていてイライラする存在だったかもしれない。「あなたは、(男性としても若い世代としても能力としても)恵まれたものを持っているのに、どうしてそんなになよなよしているのか」と。事実、所属コミュニティの中で僕はダントツにこじらせてなよなよしていたし、みんなが着々と就職や進学先を決めていくなか行き当たりばったりでフラフラしていたし、女性メンバーの方がよっぽど優秀でしっかりしていたと思う。
とはいえ当時の僕は僕なりに、フラフラしながらもそれはそれで必死に悩んでいたものから、彼女たちの期待に応えて「力強く」生きていくことはどっちにしろできなかった。若かった、未熟だと言えばそれまでだけれど、別れはある種の必然だったのだろう。
先に言った通り、どれも1対1の、「わたし」と「あなた」の話なのだ。生きる上での価値観とタイミングが合わなかっただけに過ぎない。彼女たちも僕も、同級生たちも、誰も男性全体、女性全体を代表することなどできないはずだ。
それなのにどうして今になって思い出すのか。そこにはやっぱり、時代と世代のギャップによって重み付けされた、女性性・男性性のぶつかりが、「わたし」と「あなた」の関係の”中”に、無視できない重さで内包されていたからだと思う。
時計の針を巻き戻すことはできない。巻き戻したところで、当時の僕が話せたことはないかもしれない。
そうだとしても、無視できない男性性・女性性を自覚した上での「わたし」自身の問題として、彼女たちとの別れをもう一度受け止め直したとしたら、僕はこれからどうあるべきだろう。読書会の帰り道にそんなことを考えた。
「選べない」ことも含めて、自分なりの方法で運命を引き受ける。結局はそれしかないと思う。
自分が「男性」であることそれ自体について回る、潜在的な加害性を自覚すること。不当な差別や性搾取に対しては断固としてNOと言うこと。男性たちの内なるミソジニーを意識し、それが表出する場面に同調しないこと。
また一方で、「あなたは男だから」「男なのに」という逆向きの偏見に対しては、臆することも遠慮することもなく「僕”は”それを選ばない」と表明すること。
性別に伴うさまざまな痛み・苦しみを生み出している「社会構造」。自分がその一部であること、いつでも加害者になりうることからは目を背けない
その上で「今、この場で、わたしとあなたはこれを選ぶ」ということにお互いが納得できるまで向き合うこと。
「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい」
そんなことを言えば、罪を犯したことのない、一切手が汚れていない「ノーブレス」な人間なんていないのかもしれない。
「男女」の問題はそれぐらいにこじれやすくて、一筋縄ではいかなくて、しんどい。
でもそのしんどさからは逃げない。ここに留まって生きていくことはできる。
ノーブレスではないかもしれないけれど、少なくともオーネストでありたいと思う。
僕たちは偶然に、「弱者」になる。そしてまた偶然に、「助ける人」になる
街中や電車で「ヘルプマーク」を着けている人を見かけることが増えた。外見からは見えにくい困難さのある方が、周囲からの認知・援助を得やすくするための意思表示のサインとしてつくられたヘルプマーク。東京都で2012年から作成・配布がはじまり、現在ではほとんどの都道府県で配布されている。仕事柄、比較的早くから知っていたのだが、目に見えて一般に普及してきたなと感じたのはここ1-2年(2018-2019年)のことだ。
東京で暮らしていると、一日1回は目にするぐらいになった。それどころか、乗り合わせた車両内にヘルプマークをつけている人が2,3人いる、という状況に出くわすこともまったく珍しくはなくなった。ヘルプマークを使用している人は、義足や人工関節等を使用している人、内部障害や難病などがある人、発達障害、精神障害や知的障害がある人、または妊娠初期の人など、多岐にわたる。入手するために障害者手帳や医師の診断は必要ない。ヘルプマークを必要とする人なら誰でも、市区町村の窓口や駅などで簡単に入手することができる。
ヘルプマークの普及によって可視化されたのは、世の中にこれほど多くの「見えない困難」がある人がいる、という事実である。ヘルプマークのことを知らなかったり使いたくなかったりで身につけていない人や、思うように外出ができない人がその背後にいると思えば、実態としては目に入る以上の割合だろう。個別の疾患や障害当事者の人数なら、少し調べればさまざまな統計・調査から、数字として知ることができる。だけど、日常生活を送る私たちの肌感覚に迫る形で、「こんなにもいる」ことを示すマークは、これまでなかったのではないだろうか。
しかし、と、ここまで書いて考える。
この車両全体を見渡したとき、「見えない困難」は、実はもっとたくさん隠れているのではないか。
お腹が痛くて必死に下痢を我慢している人、足をくじいてしまって立つのもやっとな人、連日のハードワークでくたびれきっている人、想い人に振られて今にも泣き出しそうだけど必死にこらえている人。マタニティマークもヘルプマークもつけていない。杖もついていないし車椅子にも乗っていない。声をかけたとして、誰かが助けられる類の困りごととは限らない。だけど、なんらかのマークで表象されていないけれど、すぐ目の前のこの人が、今にも助けを求めたいぐらいにいっぱいいっぱいである、という可能性は、決してゼロではない。
もちろん、ヘルプマークをつけている人たちも、今がどういう状態か見ただけではわからない、という点では同じである。内部疾患などがあり、身体が他の人以上に疲れやすい人、発達障害や精神障害があり、何かのトリガーでパニックや癇癪が起きる可能性が他の人より高いという人、などなど、他の人たちと比べて、困りごとが起きる「リスク(確率)」が高い、でもそれが表面上では区別がつかない、という人たちがヘルプマークをつけている。リスクが高い、というだけで、比較的元気なときもあるだろう。
車椅子に乗っている人はどうか。電車の乗り降りの際に駅員さんがスロープを設置しているように、移動においてニーズがあるということは一見してわかる。だけど、実は同じ人がトイレ介助のニーズも持っているかもしれなくて、たまたま介助者が同行しておらず、誰かに頼みたいけど、赤の他人にはなかなか頼めない…という「見えない困難」を抱えている、かもしれない。
健常者という言葉があるが、「常に健康な者」なんているのだろうか、と思う。同様に、「障害者」とカテゴライズされる人が、いつ何時も同じ「障害」があるわけではない、とも言うことができる。個々人のコンディションの波と、その時の状況で、私たちの「ニーズ」は微妙に揺れ動く。
「ヘルプマーク」の意味がない、と言いたいわけではない。「みんな困ってるからみんな我慢しようよ」と言いたいわけでもない。他の多くの人と比較して、常時、または持続的な困難がある人を「見える化」するための社会共通のシグナルをつくり、それを持つ人を「優先座席」というセーフティネットで受け止めやすくする。それ自体は必要なことだと思う。ヘルプマークも、まだまだ普及の途上だから、多くの人に知ってもらえると嬉しいな、とも思う。
しかし同時に、いまこの瞬間、車両にいる誰かが、より見えにくい困難を抱えているかもしれないということを、どう考えれば良いのだろう、と逡巡する。問うても答えがないことはわかっているのだけれど、私たちは、いつ誰が相対的な「弱者」となるかわからない、という不確実さの中を生きているのは事実なのだ。
こうした話をするときにいつも思い出すのは、ブロガーのfinalventさんによる「誰が弱者か?」というタイトルの記事だ。優先座席啓発のポスターを揶揄するネット上のネタを題材にしながら、政治・経済といった構造上の問題に言及しつつも、今この瞬間に誰がどのポジションにあるか、つまり「弱者」というのは偶然だろうと彼は言った。それだけを聞くとお先真っ暗な感じもするが、その偶然を不可避なものとして、その人固有の人生を送ることで、弱者も不幸も意味を失うのだ、とも続けている。これを読んだのが当時、寒空の下、たったひとりで貧乏留学をしていたニューヨーク時代(おまけに彼女に振られたあと)だったので、淡々とした彼の語り口と、自分の置かれた状況を照らし合わせて、だいぶと救われた気持ちになったのを覚えている。
しかしいま改めて読み返して、それでもやっぱり、偶然が偶然で終わらない(と、少なくとも思える)社会であれば、と願う。偶然のめぐり合わせとして、自分が突発的に「弱者」になった場合、あるいはそういう人を見かけた場合に、少しでも助けが得られやすい社会になっていってほしいし、していきたいと、僕はまだ思っている。
こと東京に関して言えば、さらに電車の中でのめぐり合わせと優先座席と助け合いの問題に絞って言えば、そもそもこの街には人が多すぎて、とてもじゃないが電車移動の際に他人を気遣う余裕など持てない状況に押し込まれている。それ自体は個人の倫理ではなく、マクロな政策として解決していくべき問題なのだろう。
とはいえ、この街の人たちが、他者を助ける力を潜在的にも持っていないかというと、そうではない、と僕は言いたい。
良くも悪くも雑で開けたニューヨークから対照的な東京の街に帰って来て、毎朝・毎晩中央線に揺られて自宅と職場を行き来する生活を初めて間もないころ、今でも覚えている出来事がある。
*
「ゴッ」
帰りの電車がちょうど中野駅に着く頃、車内で突然音がして振り返る。音のした座席近くを乗客数人が弧を作って取り囲んでおり、何か重い物が落ちたかと思って見たら、人が倒れていた。
中年の女性が、荷物を手に握ったまま、言葉もなく目をつぶっている。友人なのか母なのか、5,60代の連れの女性が地べたに座らせて背中をさする。中野駅に着き、扉が開いて停車しているが、自分では立って歩けそうにない。ひとりが座席をゆずり、ほか数名で抱きかかえてひとまず座席へ座らせた。
「そこのボタン押してください」
近くの女性が呼び出しボタン横の男性に声をかける。それを受けた男性はボタンを押して駅員を呼び、すぐに駅員から返事があった。
「どうされました?」「お客さんが倒れました」「すぐ向かいます。そちら4号車でよろしいですか?」「えーと、はいそうです」
ほどなくして駅員が階段を上ってきた。扉近くに立っていた乗客2名がスマートフォンを掲げて手を振り、「こちらですー」と駅員をいざなう。乗客が道を空けて駅員を倒れた女性のもとへ通す。
「大丈夫ですか?どうされました?」「貧血みたいです」連れの女性が答え、駅員と共に彼女を抱きかかえて外へ運んで行った。
3人が出て行くと、人々はまたすぐにスマートフォンを取り出して同じ姿勢で画面に顔を向け出した。乗務員の車内アナウンスが続く。
「先ほど、中野駅にて、具合の悪くなったお客様がおられたため、現在4分ほど遅れて運行しております」
電車が運行を再開するまでわずか4分。何事もなかったかのような、いつもの東京の車内。だけど確かに、さっきの一瞬、ここは「開いて」いた。偶然居合わせた人たちが、偶然に倒れた人のために、誰が言い出すともなく手を差し伸べた。言葉が、指が、腕が、ボールを運び、状況を動かした。ヘルプマークもマタニティマークもつけていない。その人が倒れることに、なんの予兆も予告もなかった。突然の、偶然の出来事である。それでもそこにいる僕たちは、動いた。
「お急ぎのところご迷惑をおかけして、申し訳ございません」
アナウンスは続いたが、とりたてて文句を言う人も見られない。僕も、それから2駅して阿佐ヶ谷に着いたので何事もなく電車を降りた。
「”ご迷惑”の対価としては悪くない時間じゃないか」
乗客がスマートフォンの画面に顔を戻す前、わずかに見せた安堵の色を思い出しながら家路につく。
時間は夜の11時前。退勤ラッシュと終電前ラッシュの間の、短いながらも比較的空いた時間帯だった。もっと混雑した時間帯だったら、人々の反応は違ったかもしれない。中には、イライラをあらわにする人も出てくるかもしれない。僕自身も、どうだろう。その時は近くに立っていて、わずかながらも「助ける側」の人間だった。だけど、その人が倒れた場所がもっと遠かったら?僕自身がくたびれ果てて、座席で目をつぶって眠りかけていたら?動くのがワンテンポ遅れたかもしれないし、先に動き出した人に任せてしまったかもしれない。
「弱者」が偶然であると同様に、「助ける人」もまた偶然のめぐり合わせであるのだろう。
それでも。きっと「助ける人」はいるのだろう。それが僕になるかどうかはわからない。機敏に反応して「最初の1人」になれるかどうかもわからない。だけど少なくとも、その偶然が「ゼロ」にだけはならないように、予備軍としての備えは持っておきたいものだ。ときにくたびれ、ときに酔っ払って帰りながらも、そう思う。
参考記事
「自分の傷なんて大したことない」と、あらゆる"当事者"に遠慮していた
1995年に地元・神戸で起こった阪神淡路大震災。当時、小学1年生だった僕は、寝室兼子ども部屋に布団を敷いて寝ており、勉強机の椅子が倒れてきて目を覚ました(と言っても、パイプのかるーい椅子だったので無傷である)。つまり僕も、当時の震災を経験した当事者である、と言えるのだが、阪神淡路の「被災経験」について、僕は語るほどのものをほとんど持たない。
Read more「弱さ」をめぐる旅のはじまり
「適応障害ですかね。」
「そう思います。」
平日の夜、職場から徒歩5分のクリニックで、最近知り合った医師の先生とそう話したのは、今の会社で働きだして5年目の夏のことだった。
「仕事も人も、好きなんですよね。嫌な理由ないんですけど。でもしんどいんですよね。」
風邪をひいているわけでもないのにやたらと咳が出る。オフィスに向かうだけでドッと疲れる。ミーティング前には動悸がする。言葉以上に身体は正直だ。
適応障害というのは、特定のストレス要因に反応して心身の症状が起こる疾患である。受診の場に至ってなお「別に仕事が嫌なわけじゃなくて」と防衛線を張る僕に対して、「あなた、そろそろ限界ですよー」と身体が言っているのだ。
「俺もついにビョーキになったか」という、不思議な安堵と納得。「明日はどういう報告と相談をしようか」という、極めて実務的な対応方針の思案。そういう色々が混ぜこぜに頭を巡りつつも、先生に診断書を出してもらい、処方された抗うつ薬を帰り道の薬局で受け取った。
診断を受けた翌朝、通常通り出社し、パソコンを開いて、上長と人事部長にメールで報告した。直近で入っていた会議はキャンセルし、その他、急ぎでないもの、自分の手元でしばらく寝かせても当座支障がないものなど、いくつかの観点で業務を取捨選択し、緊急避難として減らせる限りの業務負荷とストレッサー回避をした。自分が診断を受けたこと、仕事についてはこんな対応をしていること、直近エネルギーが落ち込んでいて心配をかけるかもしれないが、自分を守りながら回復に向けてやれることをやっていこうと思っていること、などを妻に話した。それから翌週またクリニックに足を運び、職場との相談・対応状況を相談しつつ、業務調整をしながら療養を続けましょうという方針について話した。
家に帰る前にオフィス近くのベンチでパソコンを開き、その場でテキストを打つ。自分が現在「弱っている」ということ、一応のお墨付きとして、医師の診断を受けたこと、会社にも妻にも共有しつつ、業務調整をしながらもひとまずは仕事を続けてもいること、弱った自分のことを自分自身がどう捉えているか、等々を、なるべく淡々と、ジャッジを交えずに、かつ率直に現在地点の記録として書き残した。そしてその記事をSNSに放流した。
ほどなくして、SNSのコメント欄やメッセージボックスにたくさんの声が届いた。僕の心身の状況を気遣い、また支えようとしてくれるようなメッセージももちろん嬉しかったが、少し驚いたのは、それ以上に前のめりな様子で、さまざまな自己開示が寄せられてきたことだ。
「久しぶり。実は俺もいま同じような状態で」
「今、わたしのパートナーが心配なんだけど、どうしたらいいかわからなくて」
「数年前にまったく同じような状態だった。でも当時、そんなふうに職場や周囲に話すなんてできなかった。勇気あるよ」
などなど。
卒業して以来7,8年と会っていない、大学の同級生。
誰からも信頼されていていつも輝いていた先輩。
共通の友人の集まりで1,2度会って、SNSでゆるくつながっていたぐらいの知人。
採用の仕事で一度会ったぐらいの、当時学生だった子。
少し前に会社を辞めた元同僚。
それは「相談」というものではなかった。きっと「ただ、知らせたかった」のだと思う。そして僕に連絡をくれた。僕も、彼らのこえを受け取った。
お互いに何か即効性のある良い解決策を出せるはずもないし、「支え合う」というには滑稽なぐらい、お互いへろへろに弱っている同士のやり取りだ。だけど不思議と、気持ちが楽になった。具体的に何かをしてもらったわけではないが、診断を受けた直後に、自分と同じような経験をしてきた友人たちが幾人いる、という事実が、僕の心の引き出しの中にアーカイブされた。
「弱さ」を開示すると、似たような「弱さ」が引き寄せられて集まってくる。
巷のメンタルヘルスや生き辛さをめぐる言説では、「共依存」はよくないと、SNSは傷の舐め合いになりやすいと、そういうことがよく言われてきた。
ところが今回は不思議と、共倒れにはならなかった。むしろ、「弱さ」を開示しながら、一定の距離を保ち、弱いままでもつながっている、生きているという事実に、かすかに、しかし確かに支えられながら、それぞれがそれぞれに回復の道を歩んでいく。そんな感覚だったように思う。これはいったい、どういうことだろうか。
「強くある」ためのノウハウは見聞きするに事欠かない。企業研修で、ビジネス書で、ネットの記事で、「強くあれ」というメッセージが繰り返し発信されている。だけど、「弱った」状態でどう生きていくか、弱いままでも生きていける知恵については、教わったことがなかったように思う。
「弱さ」を開くことの可能性。人間関係の網の目の中で与え合うということ。自分の生を肯定する物語が開かれること。「弱さ」を携えて生きていく人たちと著者の対話を通して探求していきたい。
----
「弱さ」を巡る旅をしながら綴る一冊の書籍ができあがるまで、晶文社の安藤聡さんとの二人三脚で、また読者や友人たちとの対話のなかで、執筆プロセスを公開しながら進めていきます。
最初から構成を決めて埋めていくというより、旅をして、断片を書き連ねて、何を書くべきかがだんたんと見えてくる、そんな書籍になりそうです。
世代の宿題、そしてわたしの宿題 ぶっちゃけキッツイなーと思うこともあるんですけども
世代の宿題、というのがあるよな。たくさんあるんだけど、その中で、自分の宿題、というのがあるよな。そう考えながら仕事をしている。
ほんの数年前までは自分が生きるのに必死だったけど、いや今も必死なんだけど、歳を取るにつれ、この宿題は自分たちが受け止めてどうにかせんといかんよなという感覚が強まってくる。
全体的にカネも時間もなくてみんな必死のヘロヘロだよというムードの中で、真綿で首を絞められるような構造の中で、1)もう一度、私たちが拠って立つ倫理を共有すること、2) 魂を売らずに自律・持続可能なメディア環境をつくること、3)個人の心身がボロボロにならないようなクッションを敷くこと、そういうことを考えている。
まとまってはいない。仕事帰りに疲れた脳みそで書く。すまん。
宿題その① もう一度、私たちが拠って立つ倫理を共有すること
相模原、の後の、登戸と、元次官の息子殺傷。最近、頭の片隅にずっとあって、自分の思考と行動と言葉に影響している。日に日にその残響は実感を増す。
僕の同世代は、だいたい大学卒業前後というタイミングで東日本大震災を目の当たりにした。個人もNPOもボランティア団体も企業派遣も、みんなそれぞれの関わり方で、現地に飛び込んだり後方支援したり…僕もその中にいた。もちろん課題はまだ全部片付いてはいないが、損得ではない何かに、多かれ少なかれ「突き動かされて」いたのだと思う。
その少し前から、SNSが勃興したり、greenz.jpとかソトコトとかオルタナとか、そういう「ソーシャル系」の先駆けとも言えるメディアが立ち上がったりして、まだまだマスには遠かったかもしれないけど、社会的なイシューにコミットすることを、一定カジュアルにしたり、かっこよくしたり、そういうことをちょっと上の先輩たちがやってきた。
障害者差別解消法が施行されたり、法定雇用率がアップしたり、あとはなんだ、働き方改革とか、ダイバーシティ&インクルージョンとか、SDGsとか、レインボーとか、心のバリアフリーとか、オリ・パラとか、とにかく少なくともお題目としては、色々、掲げられてきたはずだ。
そういう「前進してる感」が、まがりなりにもちょっとずつ積み重なってきたはずの機運が、1つ、2つ、3つと、片手で収まる数の事件で、オオカミの一息で吹き飛ばされた子豚の藁小屋よろしく、あっけなく崩れてしまった。そんな感覚に陥る。
やってる方はそれはそれで真剣に企画してきたはずなんだけど、それでも、ソーシャルなあれやこれやをオシャレにしていくあれやこれやが茶番みたいに思えてくる。くそう。
ちゃんと「怒る」、ちゃんと「それはダメだ」と言うことの必要性を感じる。一方で、敵を想定した短期的なキャンペーンでは、根本解決に至らないことも知っている。
彼らをして、その行動に至らしめた構造こそを問わねばならないことはわかっている。しかし、それにしても、余裕がない。社会に、私に。
障害のある人に限らず、誰もが「役に立たなければいけない」というプレッシャーにさいなまれているように見える。無意識に、しかし水が染み渡るかのように、優生主義や能力主義の亡霊が私たちの思考と行動に影響しているように思える。
彼らの行動選択自体にNOをちゃんと言わねばならないということと、社会全体の「余裕の無さ」を前にして、どう伝えれば届くのかということ。後者はより難しい宿題だ。
倫理を打ち立てなければならない。方法はまだ見えない。だけどそれが必要なのは確かだ。
誰かを悪者にして溜飲を下げるのではない、歴史と構造と倫理へのまなざしを持った、愛と知性が必要だ。
宿題その② 魂を売らずに自律・持続可能なメディア環境をつくること
先立つものはお金である。それも、紐付きでないお金だ。あるいは十分に分散されたポートフォリオだ。
今日こんな記事を読んだ。
書いていることはいちいち正論である。僕もこんないい子ぶったツイートをした。
しかし一方で、ぐぬぬ、である。
ここに書かれている「昔話」にあるような、「正直さ」と「めんどくささ」をもって、メディアと編集部が堂々とクライアントや広告部と渡り合える余裕をもった媒体が、今、日本のどこにあるのか。
高級ブランドと一流のクリエイターと、信頼関係を築くに至る、編集者の深い教養とセンスと、ネットワークと。それらを貯める余裕がほとんどの媒体の編集者には、いまない。
それで良いとも、余裕がないからしょうがないとも思っていないからこそ、歯がゆい。
「ウェブ以後」の、どんどんコンテンツが無料化されていく流れのなかで、人材育成のための時間と潤沢な制作費・育成費をどうやってつくるのか。魂を売らずに自律・継続可能なメディア環境をどうつくるのか。
「タイアップ記事なんて、なくなればいい」とまで勇ましいことを言い切れない現状に歯ぎしりしながら、次のメディア環境と経済圏をどうやってつくればいいねんって試行を、同世代の友人たちと、一緒に、あるいはそれぞれに、けっこう必死こいてやってる。だいぶ無理ゲーやなと思いつつ、活路を探している。
宿題その③ 個人の心身がボロボロにならないようなクッションを敷くこと
それでいて、自分も周囲の人も倒れないで済むように、ということ。
人口ボーナスに支えられた高度経済成長は今は昔。働けば働くほど豊かになる保障もなく、しかしぼんやりしていると食っていけない。いやーキッツい。しかしそれでも、いやだからこそ、心身の健康を守るということを大事にしないと、とても続けてられない。
昨年、体調を崩した。まだ治りきっちゃいない。それでもどうにか、こうにか、やっている。
5年ぶり、10年ぶりに、知人友人から連絡がくる。「実は僕も」「実はパートナーが」まじかお前もか。よく生きててくれた。しかし大変だよなお互い。と、戦地で同胞に会ったかのような気分である。病院やカウンセリングを紹介する。たまに飯でも食おうやと声をかける。あとは、祈る。そんな感じ。
心身をボロボロにするまで走ることはない。そんな無理を重ねて自己疎外をしていては宿題1も2も到底ムリなので。
疲れたら休む。困ったら助けを求める。自分がちょっと余裕があるときは、しんどくなっている人を支える。そういう循環をどうにかこうにか回していく。
粗にして多な、孤立しない繋がりを、クッションを、そこここに敷いていく。ひとつで全部を救おうとしない。非力さを認める。同時に、非力な支え合いの持つ力を、信じる。
そんなことを考えている。
すまん、俺も寝る。みんなも、休んでくれよな。
これは「生まれてしまった」私たちのための、祝福と再生の歌だ ZOC「family name」
「すごい社会包摂アイドル出てきた」
友人が教えてくれたリンクを何気なくクリックしたらガツンとやられた。
うわ、ちょっとこれ、すごいわ。
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IytBgF3UhP0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
ZOCは、藍染カレン、戦慄かなの、香椎かてぃ、西井万理那、兎凪さやか、そして「共犯者」大森靖子の6名からなるアイドルグループだ。
family name 同じ呪いで
だからって光を諦めないよ
彼女たちにとって、family name、つまり親の姓は、選ぶことができずに課せられた「呪い」である。
生まれる-be bornと受動態で表現されるように、子は生まれてくる家や親を選べない。
そして、生まれたばかりの子どもやまだ自活できない若者にとって、親は庇護者であると同時に権力者である。
「呪い」とまでは言わなくとも、生まれた家や親に対してアンビバレントな感情を抱えている、少なくとも抱えた経験のある人は少なくないだろう。
選ぶことのできない呪い、それでもわたしはわたしの人生に光あることを諦めない。「family name」は、”生まれてしまった”運命に悩み翻弄されるすべての人たちに向けた、祝福と再生の歌だ。
ZOCの公式サイト上ではメンバーそれぞれのプロフィール写真とともに、2-3行の簡潔な紹介文が添えられている。
「毎夜ぼっちで踊ってた熊本のワンルーム・ロンリーダンサー」「少年院帰り」「孤高の横須賀バカヤンキー」「完全セルフプロデュースアイドル」「女子百八のコンプレックス」…そんな言葉が並ぶ。
僕は彼女たちの詳しい生い立ちを知らないが、family nameを「呪い」と言い切ることに説得力を持たせる程度には、「何かあったんだろう」と部外者が想像するに難くない、(曲中でも自ら歌っているが)「治安悪い」顔ぶれである。
彼女たちが生きてきたこれまでの歴史それ自体が、きっとZOCというユニット、そして彼女たちが歌う「family name」に力強さをもたらしていることは間違いないと思う。
だけど、それ以上に僕がZOCに惹かれるのは、彼女たちが「かわいそうなマイノリティ」枠に決して回収されない、気高さと疾さと、危うさとしたたかさを携えた存在だからだ。
かわいそう抜きでもかわいいし
私をぎゅってしないなんておかしい
という歌詞は、上記のようなプロフィールを開示したアイドルに対して、今後当然に想定されるような有象無象のマウンティングーやたらと不幸な過去ばっかり聞きだして強調したがるインタビューとか、君たち大変だったんね守ってあげようと寄ってくるオッサンたちとかに対する牽制にもなっている。
かわいそうかどうかなんてどうだっていいから、今この場で歌って踊っている私たちを見ろ、そして祝福しろ。
そんな、「アイドル(偶像)」として立つことへの矜持が感じられる。
そして僕が一番好きなのはここ。
いらない感情しか売らないから
消費されたって消えはしない
最初に聴いたとき、これはものすごい人間讃歌だと思った。
消費上等、あんたたちが見てるものが<わたし>のすべてと思うなよ、と。
個人が、特に女性が「自分語り」をコンテンツにするたびに「切り売りだ」なんだと説教が湧いてくるのが昨今のインターネット言論空間だ(僕はそれをクソだなと思っている)が、書かずには、語らずにはいられない切実さをもって言葉を絞り出している人たちすべてにとっての福音であり包摂となる歌だと思う。
「孤独を孤立させない」
これがZOCのコンセプトだという。
人はどこまで行っても孤独だ。
彼女たち6人も、彼女たちの歌を聴く人たちも、これを書いている私も、これを読んでくれているあなたも、伝わらないもどかしさの中でこれまでもこれからもずーっと、孤独を生きていく。
それぞれがそれぞれに呪いを背負って生きていくなかで、孤立しないで共にあることは可能なのか。
彼女たちの答えは、ただただひたすらに「クッソ生きてやる」ことなのだろう。この世の果てまで。
曲の後半。夜の街を駆け抜け、出会う彼女たち。
そして最後に再び高らかに歌うのだ。
family name 同じ呪いで
だからって光を諦めないよ
朝焼けの河川敷で肩を組むその姿は、何よりも美しく、眩しい。